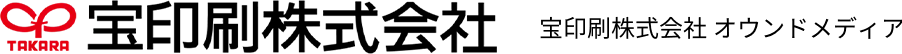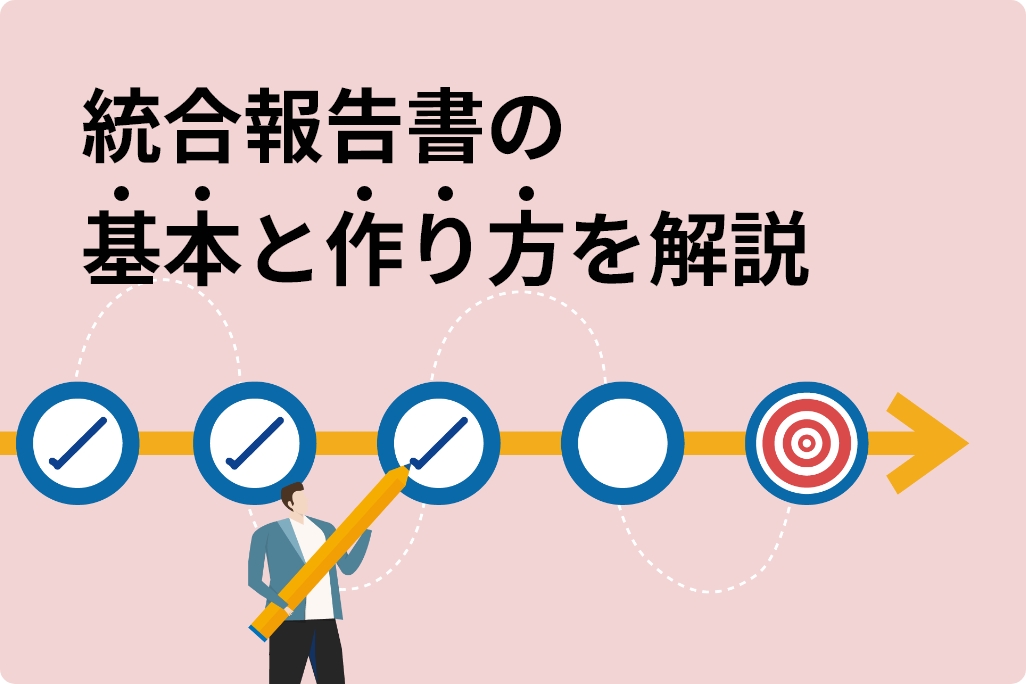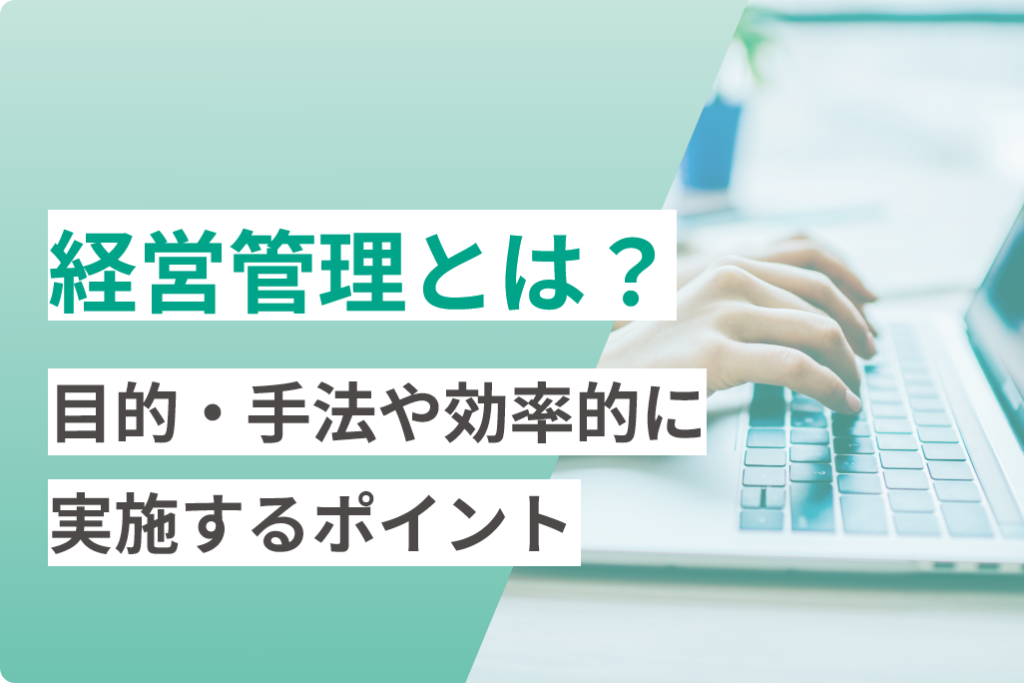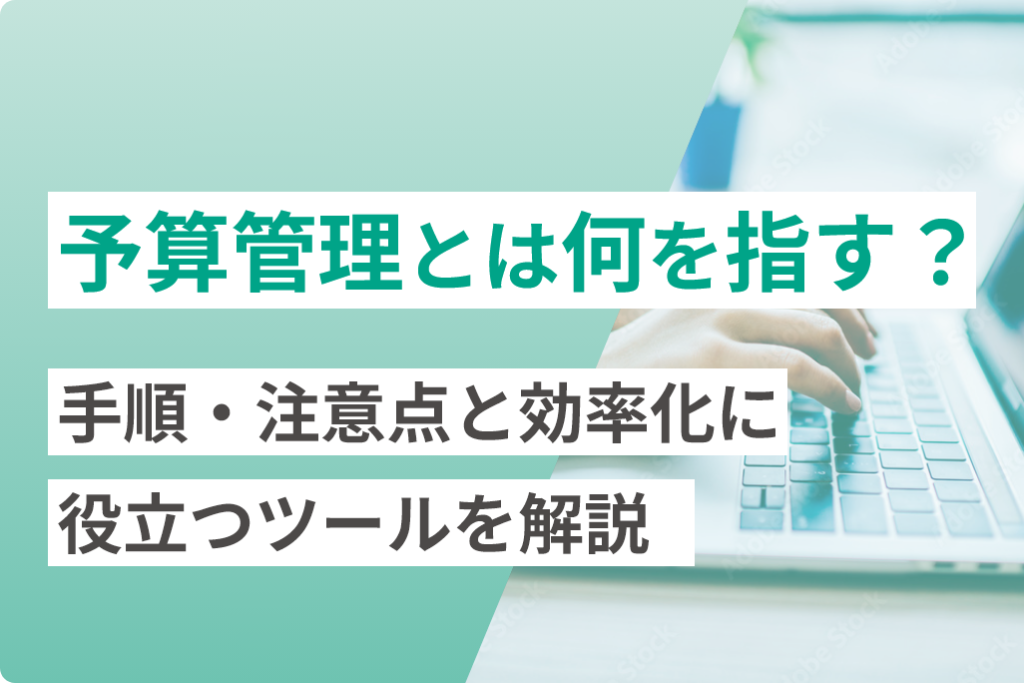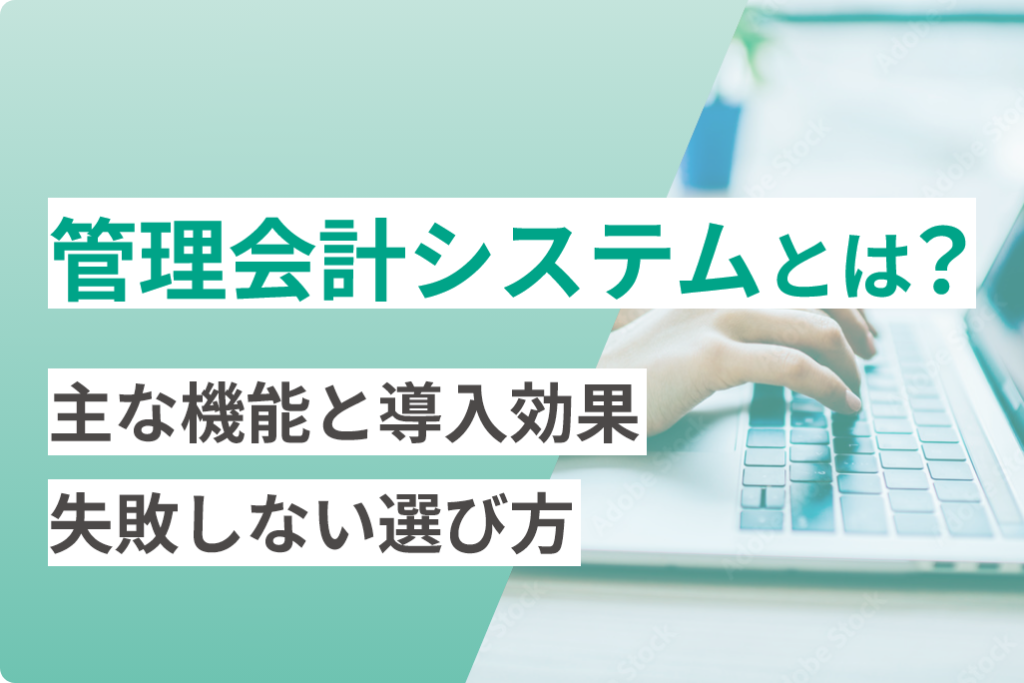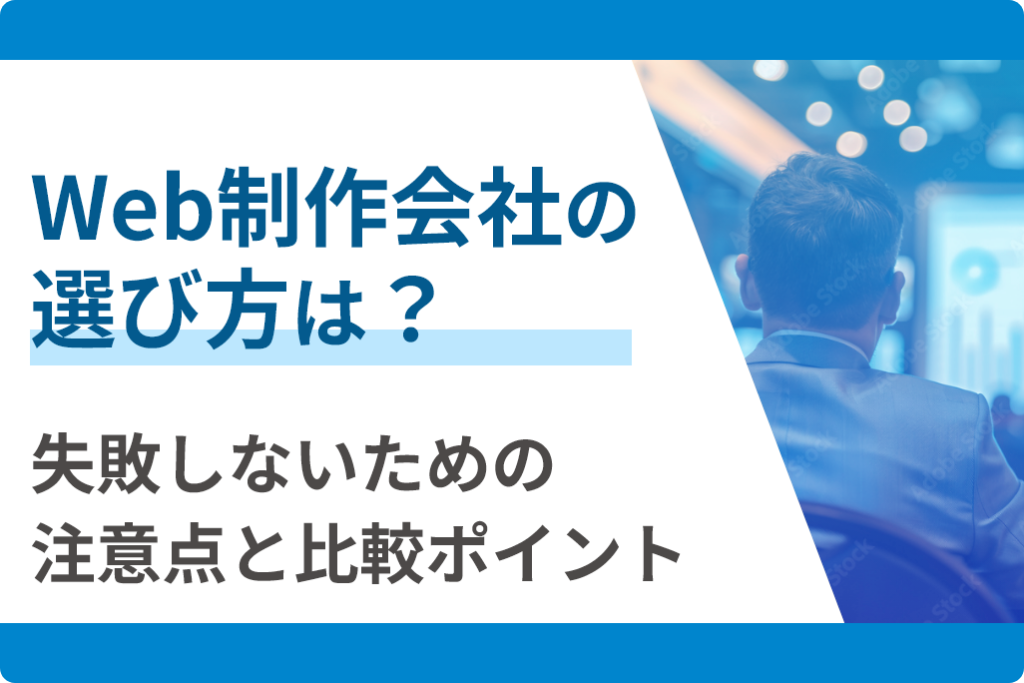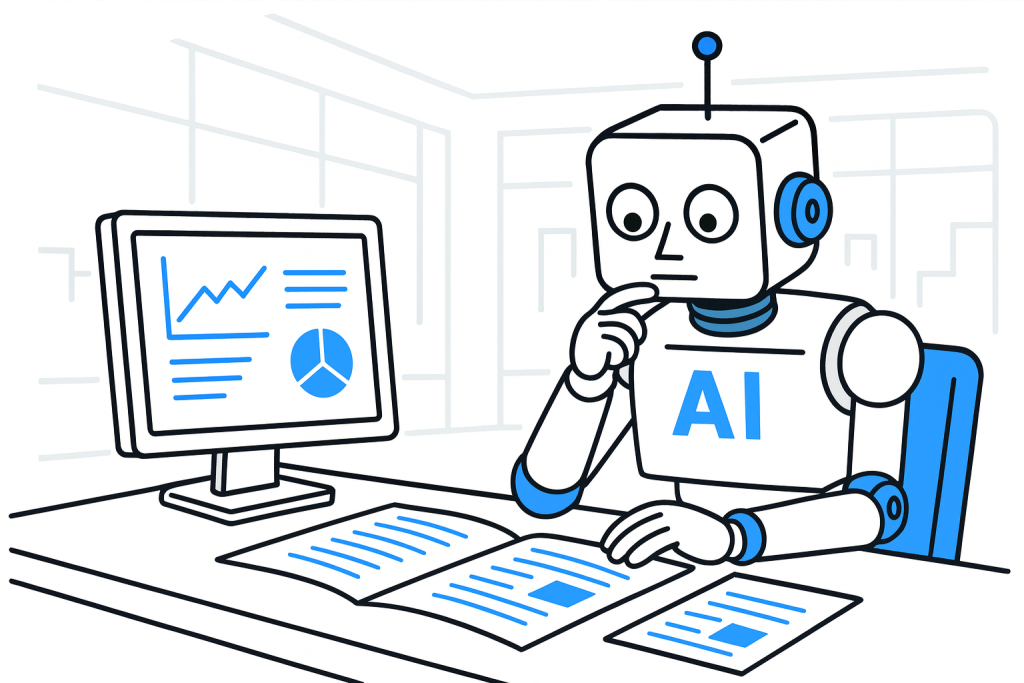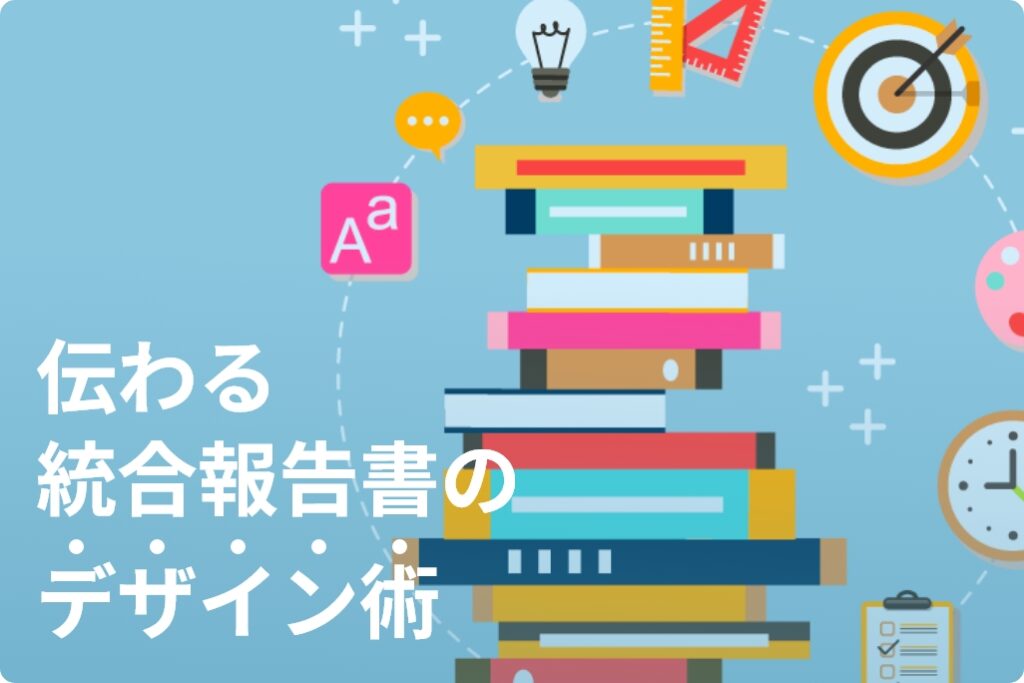「統合報告書とはそもそも何?」「何のために作るの?」
この記事のタイトルをご覧になって、同じような疑問を感じた方も多いのではないでしょうか。
統合報告書とは、企業の財務情報と、ESG(環境・社会・ガバナンス)活動などの非財務情報を統合し、企業の価値創造プロセスや長期的な成長戦略をステークホルダーに伝える媒体のこと。
企業価値を評価する上でサステナビリティ(持続可能性)への取り組みがますます重視されるようになり、その情報開示ツールとして統合報告書を制作・発行する企業が増加しています。一方、統合報告書で必要とされる知識・情報は膨大なため、理解が追い付かず、制作したもののステークホルダーへの訴求が不十分になってしまうといった課題が生じるケースも少なくありません。
そこで本記事では、統合報告書を理解するきっかけとなることを目指して、概要や作り方を整理してご説明いたします。
統合報告書とは
統合報告書の概要について、まずは次のポイントから見ていきましょう。
- 企業の財務情報・非財務情報を統合させた媒体
- 統合報告書の制作・開示は義務化されていない
- “アニュアルレポート”との違い
- “有価証券報告書”との違い
企業の財務情報・非財務情報を統合させた媒体
“統合報告書”は、企業の財務情報と非財務情報を統合させた媒体です。このうち財務情報は売上や資産など、非財務情報はESG(環境・社会・ガバナンス)やCSR(企業の社会的責任)などを指しています。
投資家や取引先、従業員、地域社会といった多様なステークホルダーに自社の本当の価値を理解してもらうためには、短期的な業績だけでなく、持続的な成長戦略、中長期的なキャッシュ創出力、そして社会・環境への貢献といった幅広い情報を提供する必要があります。
その情報提供のために活用されているのが、今回解説する「統合報告書”です。
統合報告書の制作・開示は義務化されていない
2025年時点では、日本において統合報告書の制作・開示は義務化されていません。ただ、後ほどご紹介するさまざまな理由により、統合報告書を発行する企業数は増えています。
統合報告書発行状況調査2024によると、2024年1月~12月末時点の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加しています。こういったデータからも統合報告書への関心が高まっていることがわかります。
“アニュアルレポート”との違い
“アニュアルレポート”は年次報告書のことであり、企業の財務情報を投資家や金融機関などのステークホルダーに開示するためのもの。統合報告書との大きな違いは“視点”です。アニュアルレポートは、主に過去1年間の財務実績や事業活動の報告が中心です。一方で統合報告書は、財務情報と非財務情報を企業価値に関連付けて、中長期的な企業ストーリーをステークホルダーに語るという“将来志向”の視点に特徴があります。
※関連記事
“有価証券報告書”との違い
統合報告書は、前述したように財務情報と非財務情報について、自社の経営戦略や取り組みと関連付けながら自社の企業価値を語るためのものです。
一方で、有価証券報告書はあくまで損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書などの財務諸表と注記等をまとめた報告書です(ただし、2023年3月期決算に係る有価証券報告書からサステナビリティ情報の記載が一部義務化されました)。さらに金融商品取引法第24条有価証券報告書の提出により、当該事業年度経過後、3か月以内に金融庁へ提出することが上場企業と一部の非上場企業に義務付けられている点が、有価証券報告書と統合報告書との大きな違いのひとつです。
ちなみに、有価証券報告書の主な対象も投資家などの“財務資本提供者”ですが、その内容は従業員、顧客、地域社会など、より多くのステークホルダーにとっても有益であるため、これらの人々を意識して制作されることもあります。
※関連記事
統合報告書を制作する目的・重要性

統合報告書を制作する目的・重要性として、次のようなポイントがあります。
- 中長期的な価値創出を発信する
- ステークホルダーとのコミュニケーションを円滑化する
- サステナビリティを意識した投資家に対応する
中長期的な価値創出を発信する
統合報告書の制作目的のひとつが、自社の企業価値をステークホルダーに知ってもらうことです。その企業がどのようなビジネスモデルやビジョンで事業に取り組んでいるか、持続可能性を意識しているか、将来的にどのような価値を生み出せるかといった点が、ステークホルダーの主な関心事と言えます。統合報告書では、そうした財務価値・非財務価値の双方を創出するストーリーをステークホルダーに発信することができます。
ステークホルダーとのコミュニケーションを円滑化する
適切に制作された統合報告書は、自社の価値創造につながるストーリーについて、財務情報や実績などのエビデンスを必要に応じて加えて納得できる形で伝えます。そうすることで財務資本提供者を主体とするステークホルダーからの信頼を得て、コミュニケーションを円滑にすることができます。
サステナビリティを意識した投資家に対応する
統合報告書でサステナビリティに関する自社の取り組みをしっかり伝えることで、サステナビリティを意識した投資家や資本市場からの評価を得やすくなります。その結果、必要な財務資本の提供を受けやすくなるなど、企業経営にとっての影響も生じるでしょう。
統合報告書を制作するときに意識すべきポイント

統合報告書を制作する際は、ステークホルダーに読まれる統合報告書を目指すために、次のようなポイントを意識しましょう。
- “価値創造プロセス”を明示する
- ストーリーラインを意識して構成する
- 投資判断に活用できる情報を掲載する
- 機関投資家以外の視点も考慮する
“価値創造プロセス”を明示する
統合報告書の“価値創造プロセス”は、企業が中長期的な価値を生み出す過程を示すために、後述する統合報告フレームワークで示されるような内容要素(インプット、ビジネスモデル、アウトプット、アウトカムなど)を、企業の価値創造の全体像が理解できるように分かりやすく表現したものです。そのため、統合報告書の中核をなす非常に重要なパートになります。
ステークホルダーに読まれる統合報告書を作るためには、図や概念図などを用いて価値創造プロセスを分かりやすく伝えることが大切です。ただ、それが絵に描いた餅になってしまわないように、自社の実績や取り組み内容を踏まえた現実的な内容で記載しましょう。
※関連記事
ストーリーラインを意識して構成する
自社の価値をアピールできる統合報告書を作るためには、ストーリーラインを意識した構成が欠かせません。ストーリーラインとは物語の流れを意味します。統合報告書は、単に数値やデータを羅列したものではなく、自社のストーリーを描写したものが求められます。開示した情報の背景にどのような価値観があり、どんな戦略で将来的に価値を生み出し、それを企業価値といかに連動させていくのか、一連のストーリーを描けるようにしましょう。こうした背景があって初めて、数値やデータが意味を持つようになります。
投資判断に活用できる情報を掲載する
統合報告書の主要な読者は投資家や株主などの財務資本提供者なので、投資判断に活用できる情報を掲載することが重要です。財務情報については、売上高、利益率、ROE(株主資本利益率)、ROA(総資産利益率)など、企業の財務健全性や収益性を評価するための指標が求められます。非財務情報については、マテリアリティ(重要課題)として特定したESG課題への具体的な取り組み状況、目標設定と進捗、関連するリスクと機会などの記載を意識しましょう。
機関投資家以外の視点も考慮する
統合報告書は基本的に財務資本提供者を対象として制作・開示するものですが、IFRS財団の統合報告フレームワークでは、他のステークホルダー(従業員、顧客、サプライヤー、地域社会など)にとっても有用とされています。そのため、自社が統合報告書を発行する目的や対象読者をしっかり検討し、対象者によってコンテンツのメリハリを付けることが重要です。例えば、従業員の行動変容を起こしたい場合は、人材育成や労働環境など従業員に訴求できるコンテンツを多く書くとよいでしょう。ただし、統合報告書のメインターゲットはあくまで財務資本提供者であることを忘れないようにしましょう。
統合報告書に含めるべき8つの項目

IFRS財団統合報告フレームワークでは、次の8つの内容要素を統合報告書に含めることをおすすめしています。
- 組織概要と外部環境
- ガバナンス
- ビジネスモデル
- リスクと機会
- 戦略と資源配分
- 実績
- 見通し
- 制作と表示の基礎
組織概要と外部環境
自社がどのようなビジネス環境において、どんな事業を営んでいるかについて説明します。具体的には、企業のビジネスモデル・事業内容・規模などの概要に加えて、技術動向・マクロ経済・各種規制といった外部環境に関する情報が求められます。
ガバナンス
自社のガバナンス構造は、自社の短期的・中期的・長期的な価値創造能力をどのように支えるかについて記載します。具体的には、経営の監督構造や取締役会の役割、リスク管理体制や倫理観などに言及することで、自社の企業統治体制をはっきりと伝えることができるでしょう。
ビジネスモデル
自社のビジネスモデルについて記載します。企業が価値を生み出すために欠かせない財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本の6つの資本との関連も大切です。
リスクと機会
企業の短期的・中期的・長期的な価値創造能力に影響を及ぼす具体的なリスクと機会について、取り組みや対策を併せて分かりやすく記載します。価値創造プロセスへのインパクトは大きいため、投資家の投資判断として重要な要素となるでしょう。
戦略と資源配分
自社がどこを目指し、どのように辿り着くのかについて、具体的な戦略を記載します。内容は、企業が持続的に価値を創造するための戦略と、その実行に必要な資源配分計画を示すとよいでしょう。
実績
自社が当該期間における戦略目標をどの程度達成したか、また資本に対するアウトカム(影響)について書きましょう。財務的成果だけではなく、非財務的成果についても言及することが重要です。なお、アウトカムは自社ビジネスが外部・内部に与える影響を意味するため、アウトプットと混同しないように注意しましょう。
見通し
組織がその戦略を遂行するにあたって、どのような課題や予測できない将来に直面する可能性があるか、またビジネスモデルや将来の実績への潜在的な影響はどのようなものかを記載します。外部環境の変化への対応策について言及することも重要です。
制作と表示の基礎
組織が統合報告書に含むべき情報をどのように決定し、その情報をどのように定量化または評価したかを記載します。報告書の制作に用いた基準や重要性、前提条件などの判断基準の開示が求められます。
統合報告書を制作する手順・ステップ
統合報告書を制作する手順について、次の7つのステップに分けて解説します。
- 発行目的や対象読者を想定する
- 発行時期とコストを明確化する
- 競合他社の統合報告書を集める
- 統合報告書の全体像を検討する
- 統合報告書の制作体制を構築する
- 統合報告書の制作と公開を行う
- 社内外の反響を集めて次年度の検討を行う
※関連記事
ステップ1:発行目的や対象読者を想定する
統合報告書をなぜ制作・公開するか、まずはその目的を考えましょう。これはステークホルダーに対してどのような“行動変容”を促したいかを考えることにつながります。例えば、機関投資家を対象として財務資本の提供を呼び込みたいのであれば、環境・社会・企業統治という3つの観点から自社の姿勢をアピールすることが大切です。
ステップ2:発行時期とコストを明確化する
宝印刷D&IR研究所の研究員コラムその統合報告書、本当に必要ですか?によると、統合報告書は決算終了後から6か月前後で発行される傾向にあります。3月決算の企業が多い日本においては、秋口が統合報告書の発行シーズンにあたります。
また、統合報告書を制作するためには人員やコストがかかるため、事前に考慮しておくことも重要です。社内リソースで対応する場合は担当者に負荷がかかり、外部の事業者に依頼する場合は外注費が発生します。予算とスケジュールを考えて最適な体制を検討しましょう。
ステップ3:競合他社の統合報告書を集める
統合報告書は「大量の情報を網羅すればいい」というものではありません。適切な情報量のレポートを制作するためには、同じ業種の競合他社の統合報告書を集めて、ベンチマークとすることが有用です。これにより情報過多や記載内容のブレを防ぎ、ステークホルダーに読まれる統合報告書を作りやすくなるでしょう。
ステップ4:統合報告書の全体像を検討する
統合報告書の骨組みの部分となる全体像とコンセプトを検討します。その年の統合報告書で何をステークホルダーに伝えたいかを議論したうえで、前述した「統合報告書に含めるべき8つの項目」や、経済産業省が公開している価値協創ガイダンス2.0を参考にして、必要とされる情報について理解しておきましょう。
そのうえで自社らしさや強みをアピールするために、経営層・事業責任者・現場トップなどの意見も盛り込むことも大切です。特に上層部のメッセージは、統合報告書の主要コンテンツでもあります。統合報告書の制作は、上層部を含めて全社一丸で取り組むことが大切です。
ステップ5:統合報告書の制作体制を構築する
統合報告書を制作するために、どの部署が主体となり、誰が社内をコントロールしていくのかといった制作体制も検討しましょう。統合報告書の制作は、社内の幅広い部門(経営企画、IR、サステナビリティ推進、財務、広報など)との連携・協働が不可欠です。そのため、プロジェクトチームを組成し、各部門の役割分担や情報収集のプロセス、承認フローといった運用ルールを明確に定める必要があります。また、統合報告書を制作すると、その後も毎年公表し続けることも期待されるケースもあるため、安定した体制の確立を目指しましょう。
ステップ6:統合報告書の制作と公開を行う
以上のステップが完了したら、実際に統合報告書を制作しましょう。制作中の段階でも経営層としっかりコミュニケーションを行い、フィードバックを反映することが大切です。統合報告書の完成後は、自社サイトやプレスリリースで展開しましょう。自社サイトで公開するだけではなく、プレスリリースも活用することで、より広範なステークホルダーに情報を届けることができます。
ステップ7:社内外の反響を集めて次年度の検討を行う
統合報告書を毎年制作・公開し続ける場合「よりよいものを作る」という姿勢は重要ですが、一方で「初めから完璧を目指さない」ことも大切です。統合報告書の完成後は、社内外でフィードバックを集め、良い点と改善点を把握することが大切です。制作チームで反省会を実施し、次年度のコンセプトや編集方針に反映させましょう。ブラッシュアップを重ねることで、自社の企業価値がステークホルダーに伝わり、評価につながることでしょう。
統合報告書に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書は、企業の財務情報・非財務情報を統合させたレポートです。統合報告書を公開することで、ステークホルダーとのコミュニケーションがより円滑になります。統合報告書を制作するときは、今回ご紹介した7つのステップを意識して、全社一丸となって取り組むことが大切です。ただ、質の高い統合報告書を継続的に制作・発行していくためには、専門的な知識や最新の開示トレンドに関するノウハウ、そして客観的な視点が必要で、自社リソースのみでの対応が難しい場合もあるかもしれません。
そこで統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。