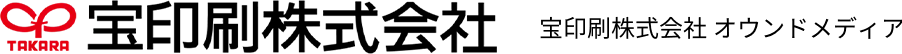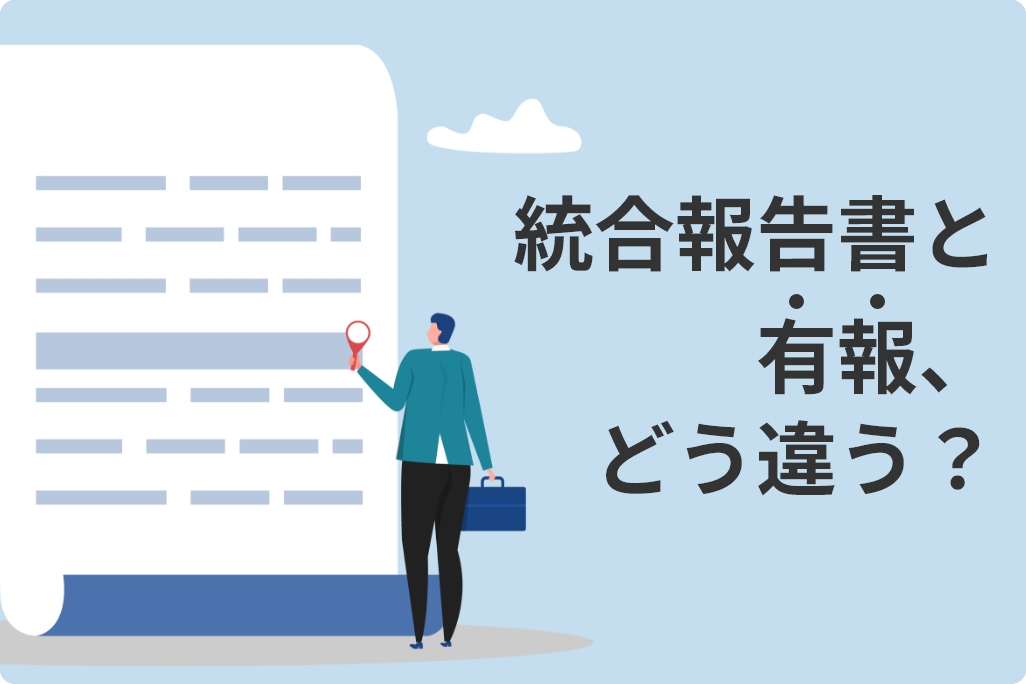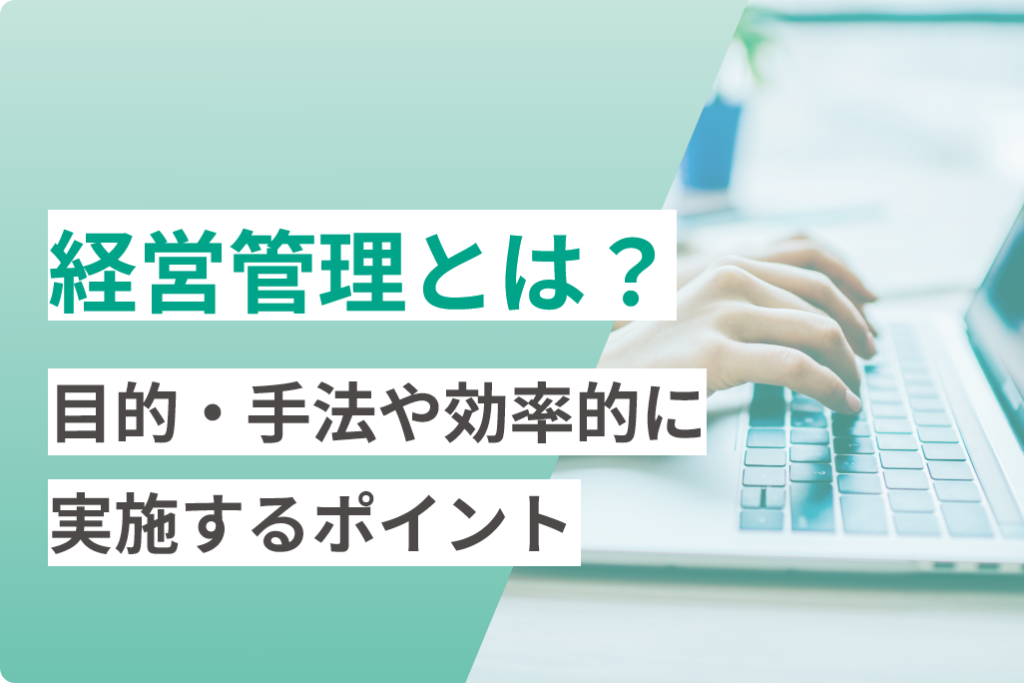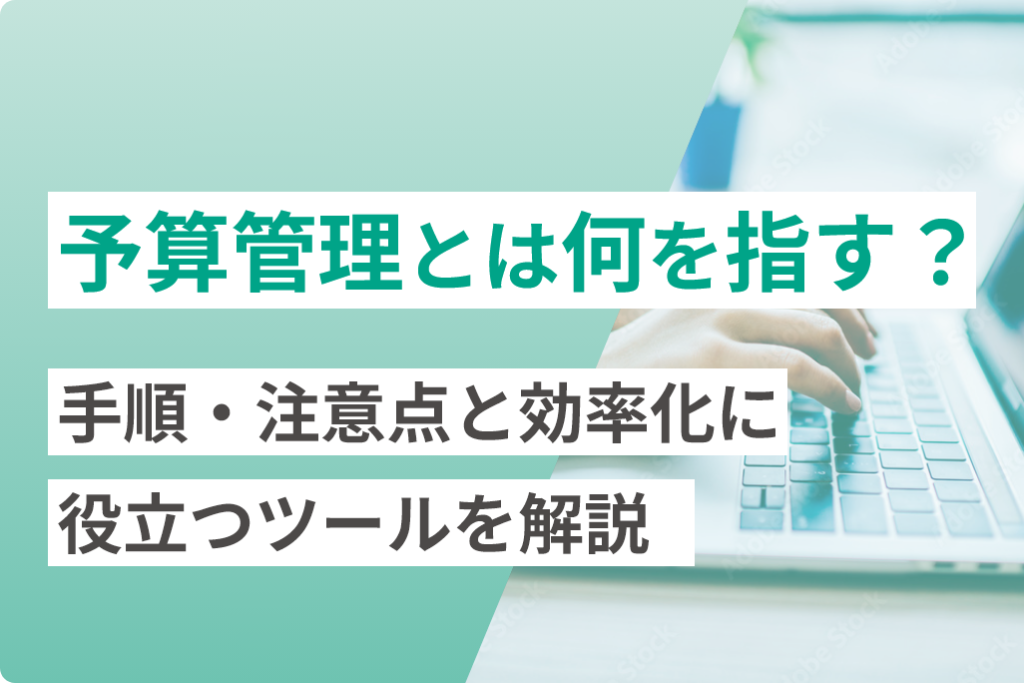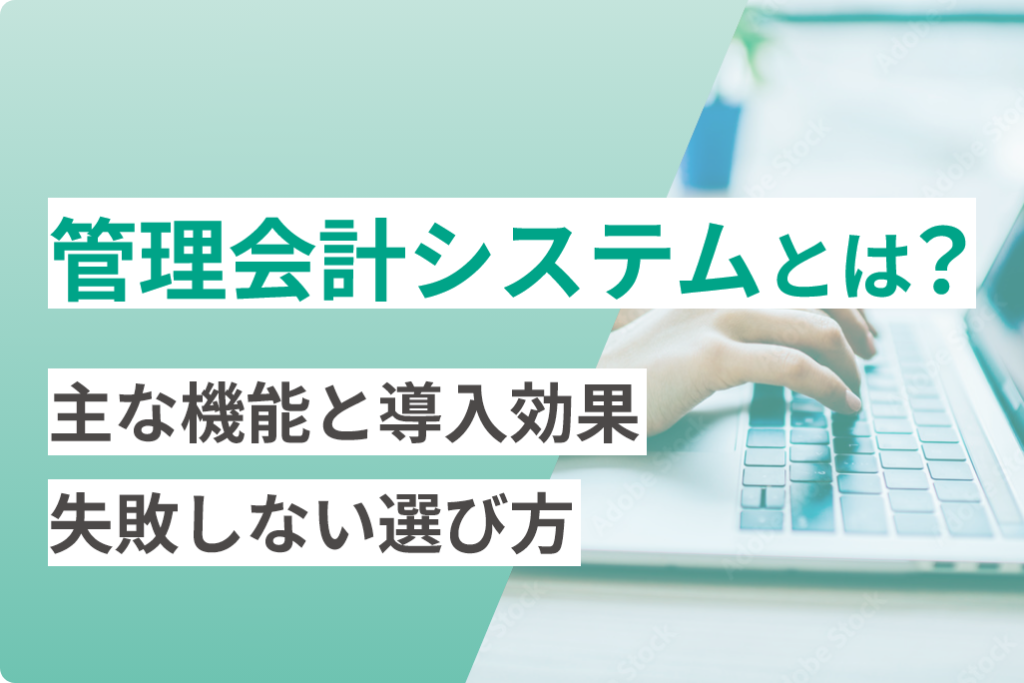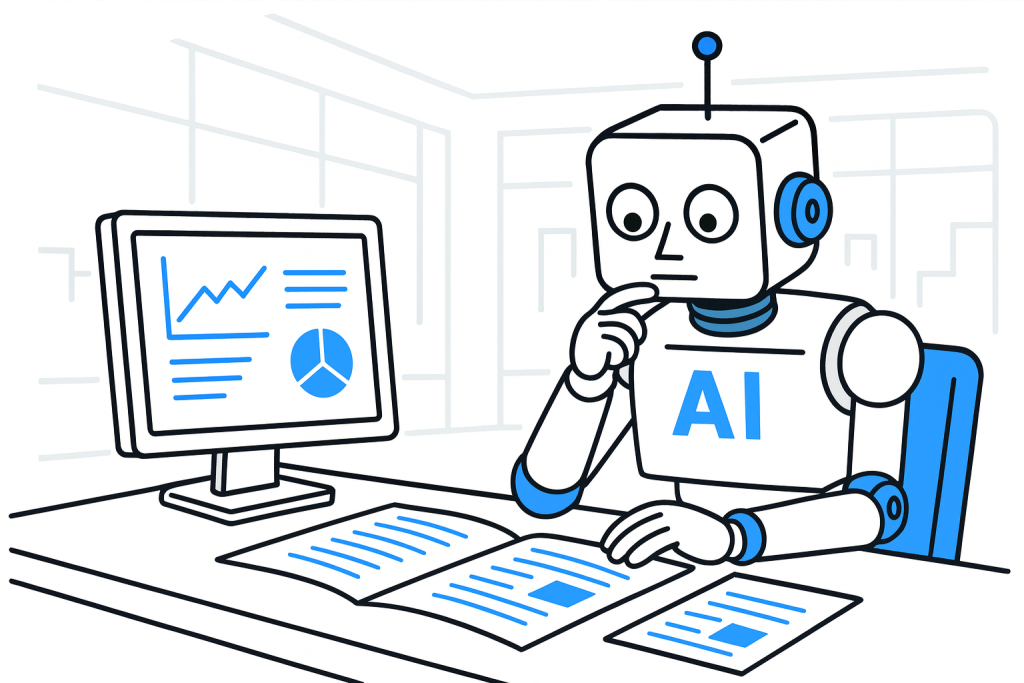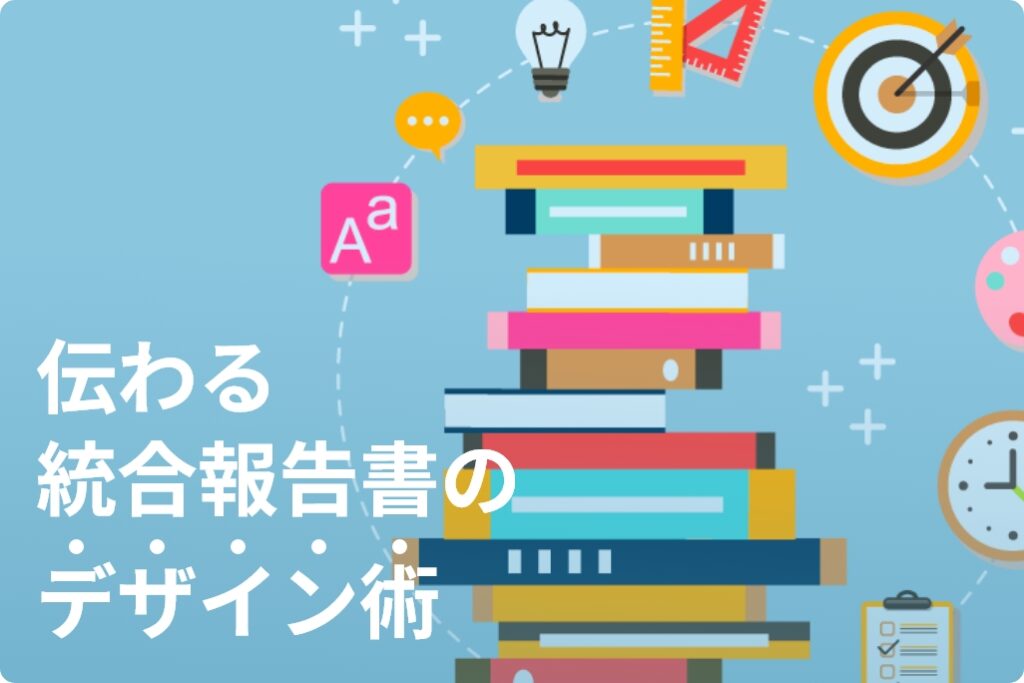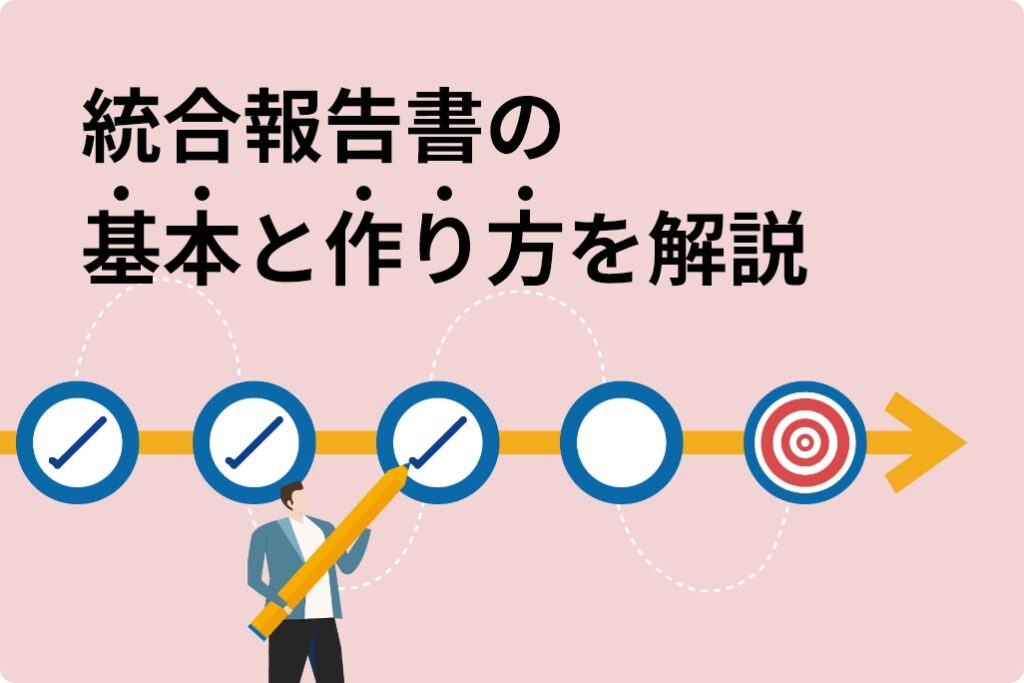統合報告書と有価証券報告書は、いずれも企業の財務情報やESG(環境・社会・ガバナンス)などのサステナビリティに関する情報を記載する点で共通点があります。しかし、両者には開示目的や主な記載内容などに明確な違いがあります。これらの違いを理解した上で、それぞれの報告書を制作・活用することが重要です。
そこで本記事では、統合報告書と有価証券報告書の違いについて解説します。
統合報告書と有価証券報告書について
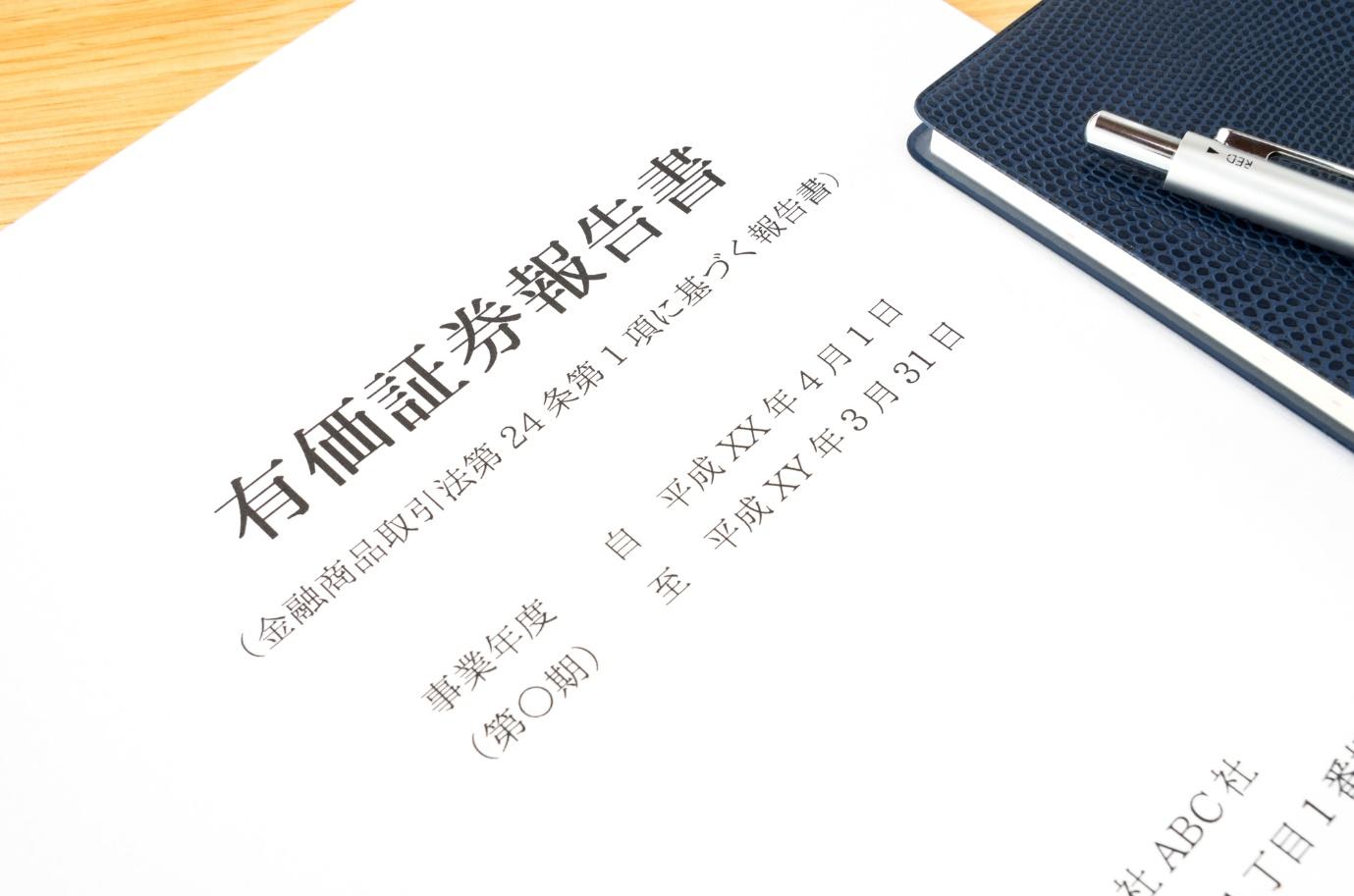
統合報告書と有価証券報告書の違いについて検討する前に、両者の概要を確認しておきましょう。
- 統合報告書とは
- 有価証券報告書とは
統合報告書とは
“統合報告書”とは、企業の財務情報と非財務情報を統合させた媒体です。財務情報は企業の売上や資産など、非財務情報はESG(環境・社会・ガバナンス)やCSR(企業の社会的責任)などのサステナビリティ情報が含まれます。
ただし、統合報告書はこれらの情報を単に併記するものではありません。統合報告書の最大の特徴は“将来思考”です。前述した非財務情報が、戦略・価値創造とどのように結びつくかを描くために、統合報告書では過去から現在、そして将来に向けた企業の価値創造ストーリーを一貫して語ります。これにより、従来の財務報告中心のレポートでは伝えきれなかった、企業の将来的な価値をステークホルダーに効果的に伝えることができます。
有価証券報告書とは
有価証券報告書は、金融商品取引法に基づき提出が義務付けられている開示書類で、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書といった財務諸表やその注記事項、事業の状況、経営方針、リスク情報などを網羅的に記載した報告書です。
投資家保護の観点などから、有価証券報告書は毎年決算後に提出することが義務付けられています。なお後述するように、有価証券報告書にはサステナビリティ情報の記載が義務付けられているため、統合報告書との違いが分かりづらいかもしれません。しかし、有価証券報告書のサステナビリティ情報はあくまで断片的で、統合報告書のような過去から将来にいたる連続性、すなわち“ストーリーライン”がないことが重要な違いです。
統合報告書と有価証券報告書との違い
統合報告書と有価証券報告書との違いについて、次の観点から解説します。
| 統合報告書 | 有価証券報告書 | |
| 開示目的 | 企業の統合的な情報を提供し、 将来的な価値創造ストーリーを語る |
企業の財務情報と断片的な サステナビリティ情報を提供する |
| 開示内容 | 財務情報と非財務情報を統合 | 財務諸表・経営分析・リスク要因など |
| 開示義務 | 開示義務はない | 上場企業や一部の非上場企業は義務化 |
| 開示場所 | 企業のコーポレートサイトなど | 金融庁のEDINETや証券取引所など |
| 開示時期 | 自由(決算後6か月程度が一般的) | 決算後3か月以内が原則 |
開示目的の違い
統合報告書と有価証券報告書は、いずれも投資家などの財務資本提供者に対し、自社の財務情報・非財務情報を開示するために制作します。ただし、統合報告書が“将来に向けた企業の姿”を描く媒体であるのに対し、有価証券報告書は原則として過去の実績の報告がメインとなります。また、有価証券報告書は金融商品取引法に基づき、上場企業や一定の条件を満たす非上場企業に提出が義務付けられています。そのため、該当する企業は法定開示書類として有価証券報告書を制作・提出します。
開示内容の違い
統合報告書は、企業の財務情報と非財務情報を統合させて開示するものであり、具体的には企業理念・成長戦略・ビジネスモデル、サステナビリティへの取り組みなどの内容を記載します。一方で有価証券報告書は、企業・事業・設備・経理の状況、また主要な取引先・関連会社の情報やリスク要因など財務情報がメインです。2023年1月の開示府令の改正で“サステナビリティ情報”の一部記載も義務付けられていますが、前述したようにあくまで断片的な情報にとどまります。統合報告書とは異なり、将来のリスク・機会・戦略的対応などの不確実情報の開示は避けられる傾向があります。統合報告書は自由演技で企業が自由な枠組みで企業活動を表現できるのに対し、有価証券報告書は規定演技として開示府令で明確に規定された枠組みで開示することも、両者の大きな違いとして挙げることができるでしょう。
開示義務の有無の違い
有価証券報告書は、金融商品取引法第24条“有価証券報告書の提出“により、当該事業年度経過後3か月以内に有価証券報告書を金融庁に提出することが、上場企業や一部の非上場企業に義務付けられています。2025年時点では、日本において統合報告書の制作・開示は義務化されていないもの、統合報告書を発行する企業数は増えています。「統合報告書発行状況調査2024」によると、2024年1月~12月末時点の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加しています。
開示場所の違い
統合報告書は、企業のIRサイトやサステナビリティサイトで公開されることや、主要なステークホルダーに冊子形式で配布されることが一般的です。一方で有価証券報告書は、企業のコーポレートサイトのIR情報ページなどに掲載されるほか、金融庁が運営する開示情報閲覧システム“EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)”や、各証券取引所のウェブサイト、場合によっては財務局でも閲覧できます。
開示時期の違い
宝印刷D&IR研究所の研究員コラム「その統合報告書、本当に必要ですか?」によると、統合報告書は決算終了後から6か月前後で発行される傾向にあります。3月決算の企業が多い日本では、秋口が統合報告書の発行シーズンです。一方で有価証券報告書は、前述したように金融商品取引法に従って、原則的には事業年度終了後3か月以内に開示されます。
統合報告書を制作・公開するメリット
有価証券報告書とは異なり、統合報告書の公開は義務付けられていないため、企業は必ずしも統合報告書を制作する必要はありません。しかし、これまでご説明した統合報告書と有価証券報告書の違いから、次のような統合報告書ならではのメリットがあります。
- 財務資本提供者と建設的な対話ができるようになる
- “統合思考”を理解・実践する機会になる
- 資本市場から正当な評価が得られやすくなる
財務資本提供者と建設的な対話ができるようになる
統合報告書を企業が制作する大きなメリットのひとつは、投資家や株主などの財務資本提供者を主体とするステークホルダーとのコミュニケーションが深まることです。統合報告書では、財務情報だけでは分からない自社の企業価値・価値創造プロセスや成長ストーリーを明確に示せるため、ステークホルダーからの信頼を醸成して建設的な対話ができるようになります。
“統合思考”を理解・実践する機会になる
統合報告書とは、財務情報と非財務情報が完全に統合された形が理想です。それを実現するためには、従来の財務諸表に焦点を当てた短期的思考から、中長期的な価値を創造できる意思決定・行動につながる“統合思考”が欠かせません。
IFRS財団の“統合報告フレームワーク”によると、統合思考とは「組織の事業・機能と資本の関係を能動的に考えること」を意味します。言い換えれば、自社の企業価値を最大化するために、社会や環境から受ける正・負の影響を自社の事業活動と結び付けて考えることです。
Integrated(統合)された情報を発信するためには「自社の価値とは何か」「自社は何を目指すのか」を明確化する必要があり、情報を共有して全社一丸となって取り組むことが大切です。
資本市場から企業情報を反映した評価が得られやすくなる
統合報告書は任意開示であるため、法令で定められた形式にとらわれず、企業が自社の長期戦略や独自の価値創造ストーリー、サステナビリティへの取り組みなどをより柔軟に、魅力的に示すことができます。そのため、規定演技で定量的な数値を示す有価証券報告書では測れないような、将来志向での企業価値を投資家にアピールでき、資本市場から企業情報を反映した評価が得やすくなるでしょう。
統合報告書の制作で重要なポイント

これまで解説したように、統合報告書と有価証券報告書は似ている部分もありますが、実際にはさまざまな点で違いがあります。統合報告書ならではのコンテンツを制作してステークホルダーを魅了するためには、次のようなポイントを意識することが大切です。
- ストーリーラインとデザインを意識する
- 投資家の関心を把握する
- 組織に統合思考を浸透させる
ストーリーラインとデザインを意識する
統合報告書を制作する際は、は単なる情報の羅列ではなく、企業理念や成長ストーリーを伝えることが大切です。そのためには、自社の経営ビジョン・ミッション・戦略の実効性について、自社の取り組みや成功事例を明示しながら、ストーリー形式で分かりやすく示す必要があります。また、ステークホルダーへの訴求力を高めるためには、伝わるデザインも意識しましょう。
投資家の関心を把握する
統合報告書のメインターゲットは、投資家や株主などの財務資本提供者です。これらの主なステークホルダーの関心は「将来的にキャッシュを創出できるかどうか」にあります。具体的に投資家が何を知りたいのかについては、投資家との1on1ミーティングなどを通じてヒアリングを重ねるといいでしょう。
組織に統合思考を浸透させる
日本企業の特性として“縦割り組織”があります。これには良い面もある一方で、統合報告書の制作においては障壁になるケースが多いです。なぜなら、Integrated(統合)された情報を発信するためには「自社の価値とは何か」「自社は何を目指すのか」を示すことが求められるからです。自社について知るためには、全社一丸となった情報共有が欠かせません。組織の活性化にも取り組まなければ、実態が伴わない表面だけの報告書になる懸念があります。
統合報告書に関するご相談は宝印刷へ!

統合報告書と有価証券報告書は、開示目的や内容に違いがあります。特に重要なポイントは、統合報告書が任意開示であり、比較的自由な形式で企業価値を表現できるのに対し、有価証券報告書は法定開示であり、定められた様式と内容で情報を開示する必要がある点です。だからこそ統合報告書は、自社ならではの価値創造力やストーリーをアピールでき、魅力的なIRツールとして注目されています。
しかしながら、統合報告書の制作には客観的な視点やノウハウが必要なので、統合報告書の作成支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。