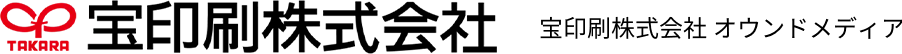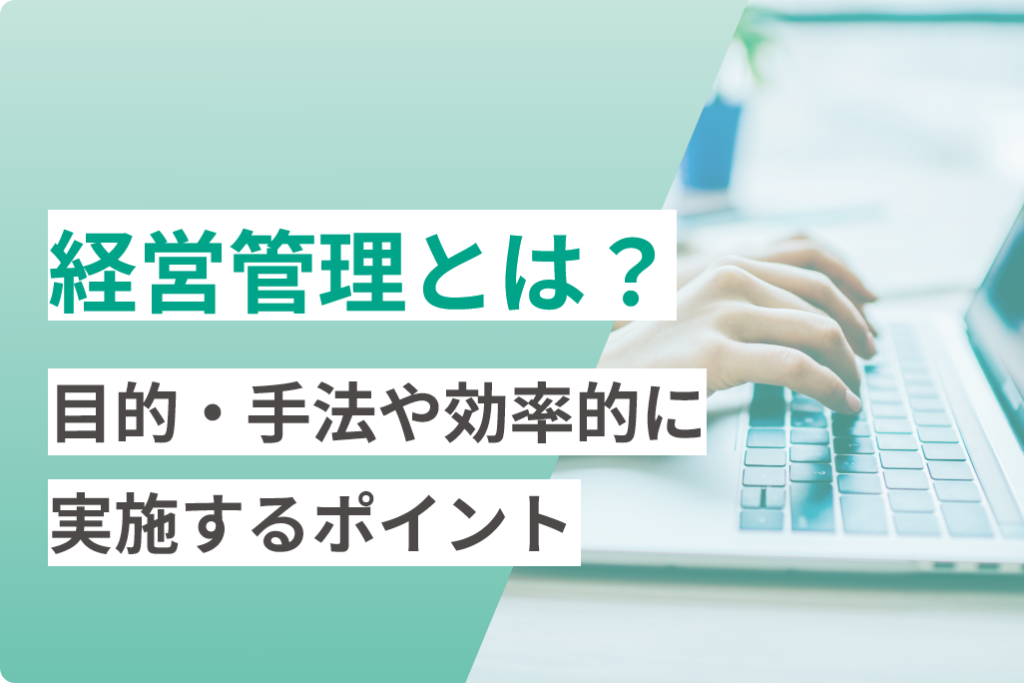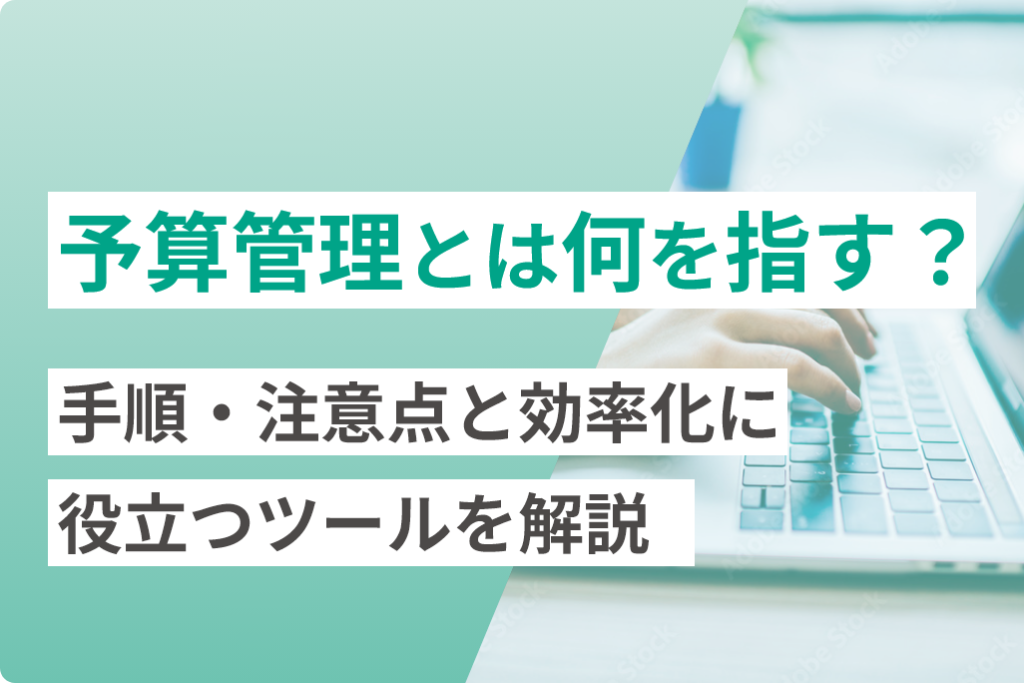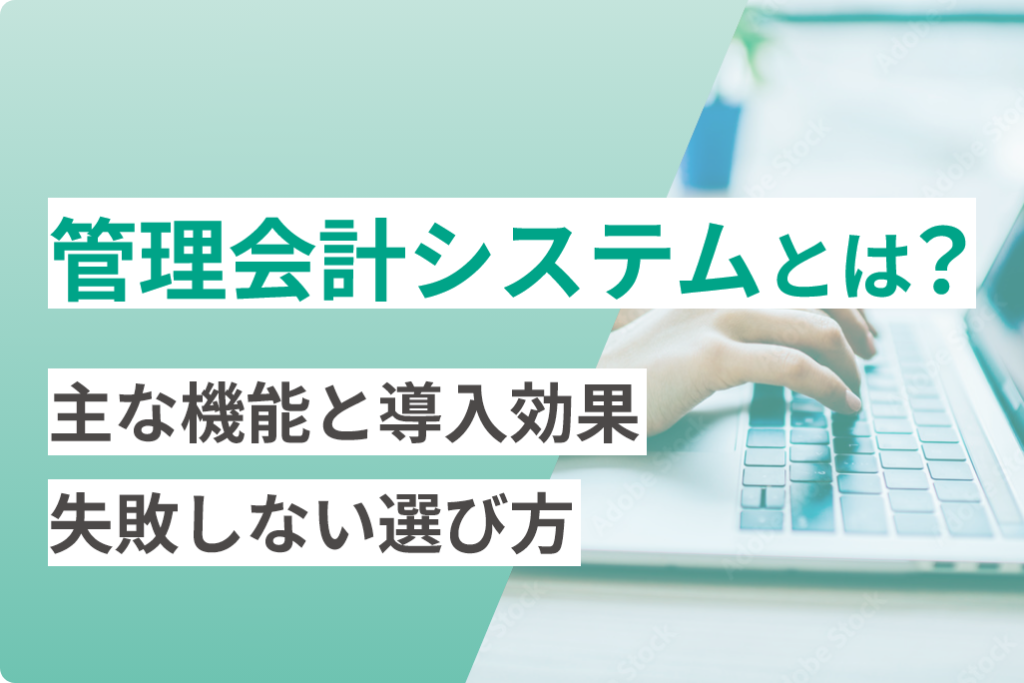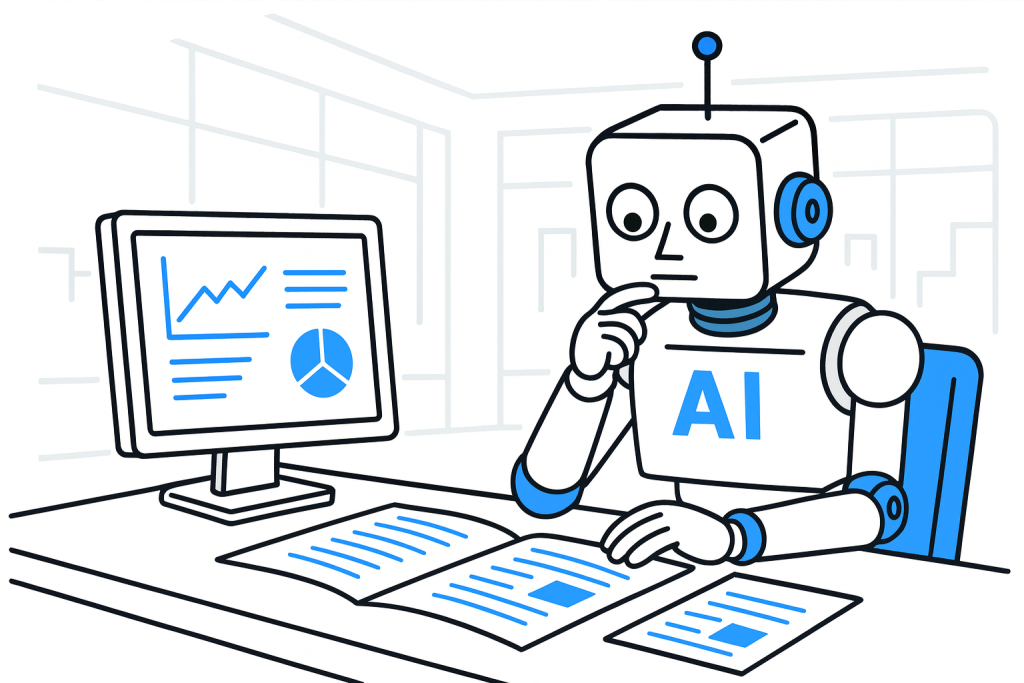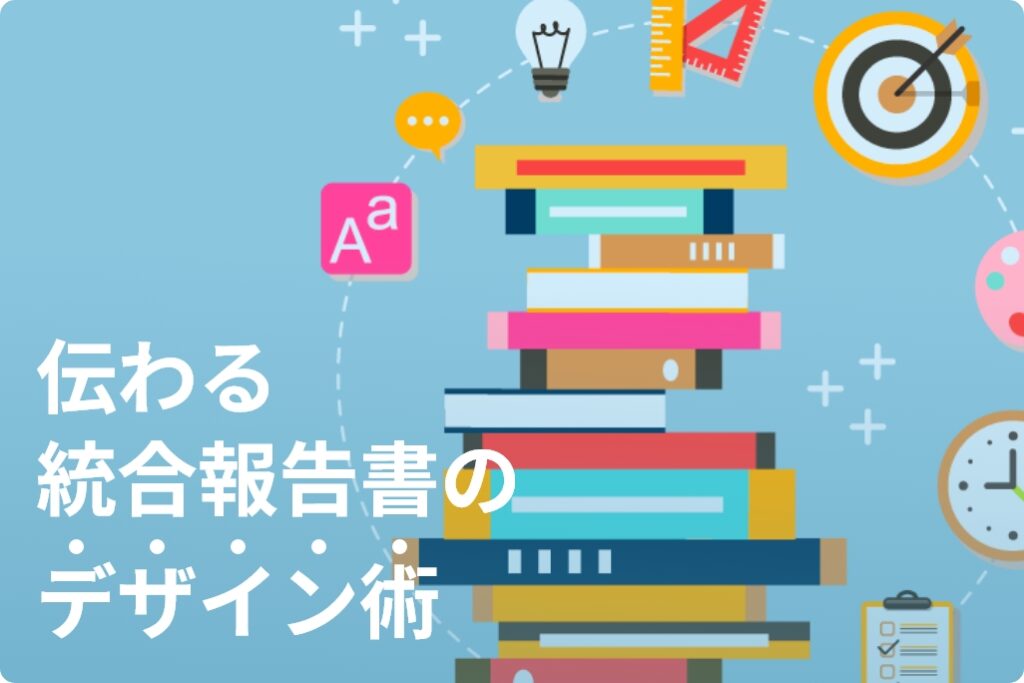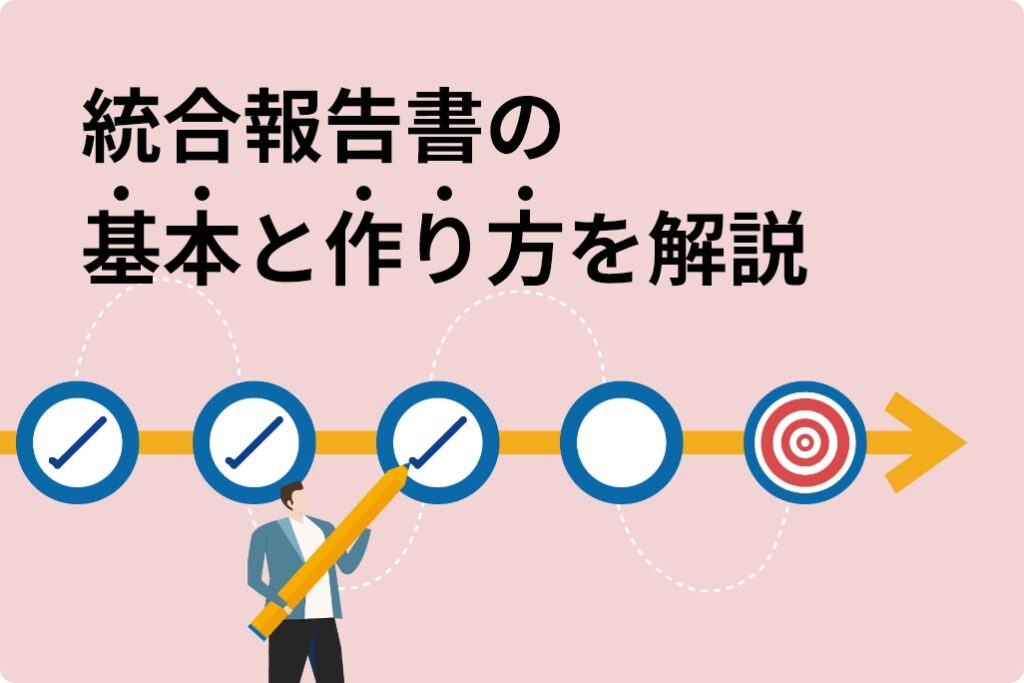“統合報告書”と“サステナビリティレポート”は、いずれも企業のESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みといった情報を含んでおり、類似している点が多いように思われるかもしれません。
しかし、両者は目的・報告内容・対象読者などに明確な違いがあり、正しく理解せずに制作すると、それぞれの報告書の本来の意義が薄れ、形式的な情報開示に留まってしまうかもしれません。
本記事では、統合報告書とサステナビリティレポートの違いについて、使い分けなども含めて解説していきます。
“統合報告書”と“サステナビリティレポート”
統合報告書とサステナビリティレポートの違いを検討する前に、まずは両者の概要を確認しておきましょう。
- 統合報告書とは
- サステナビリティレポートとは
- これらの報告書・レポートが生まれた背景
統合報告書とは
統合報告書とは、企業の財務情報と非財務情報を統合させた媒体を指します。このうち財務情報は企業の売上や資産について、非財務情報はESG(環境・社会・ガバナンス)やCSR(企業の社会的責任)に関する取り組みを示します。また企業の持続可能性についても記載するため、後述するサステナビリティレポートの内容も含むといえます。
ただし、統合報告書は財務情報と非財務情報を単に併記するのではなく、“統合思考”に基づいて両者を企業価値に関連付けて、中長期的な企業ストーリーを説明するという点に特徴があります。これにより、従来の報告書では表現し切れない企業の成長性や長期的に生み出せる価値について、社内外のステークホルダーにアピールできるようになります。
サステナビリティレポートとは
サステナビリティレポートは、持続可能な社会を実現するための取り組みについて、企業のコミットメントを開示するための報告書です。日本企業においても、サステナビリティ報告の国際的なガイドラインである“GRIスタンダード”などを参照して制作されることが多く、ステークホルダーは企業の持続可能性への取り組みや非財務的な側面における価値創造(またはリスク)を評価することができます。
なお、前述の統合報告書が財務情報と非財務情報を統合して示すのに対し、サステナビリティレポートは主に非財務情報に焦点を当てており、詳細な財務諸表は通常含まれません。
これらの報告書・レポートが生まれた背景
サステナビリティレポートが生まれた要因が、CSR(企業の社会的責任)への関心の高まりです。1997年の京都議定書の採択を契機に、企業にも温室効果ガスの排出削減など具体的な対応が求められるようになり、翌年以降に大手メーカーを中心に環境報告書が発行されるようになりました。
2000年代になると各企業が“CSRレポート”、つまり企業のCSRへの取り組み状況を示す報告書を発行し始めました。日本においては従来は環境問題が主要テーマでしたが、次第に社会問題や人権問題などにも焦点が当たり、やがて“サステナビリティ(持続可能性)”という概念が提唱されるようになると、企業はより包括的な持続可能性に注力し、そのコミットメントを示すサステナビリティレポートを発表するようになりました。
一方で統合報告書は、財務情報だけでは企業を正しく評価できないことが増えたため、従来の報告書に代わるものとして注目されるようになりました。統合報告書においても前述した持続可能性は大きなテーマであるため、サステナビリティに対する自社の取り組みについて記載します。
統合報告書とサステナビリティレポートの違い

統合報告書とサステナビリティレポートの違いについて、次の観点から解説します。
| 統合報告書 | サステナビリティレポート | |
| 目的 | 自社の持続可能性・長期戦略や価値創造プロセスの開示 | 企業の非財務情報に 絞り込んで提供する |
| 内容 | 財務情報や非財務情報の統合 | 企業の社会的責任や 持続可能性がメイン |
| 主な対象 | 投資家や株主などの 財務資本提供者 |
より広いステークホルダー |
| 義務 | いずれも義務化されていない | |
| 視点 | 長期的な戦略 および持続的な成長 |
環境や社会への 企業の取り組み |
制作目的
統合報告書もサステナビリティレポートも、いずれも自社の企業価値や持続可能性をステークホルダーに周知したり、自社に対する投資を呼び込んだりするために制作します。
しかし後述するような内容の違いから、統合報告書は自社の長期戦略・持続可能性や価値創造ストーリー、サステナビリティレポートは主に持続可能性に絞り込んだ内容を記載することが特徴です。これらの報告書を読むことで投資家や株主など、さまざまなステークホルダーが企業との関係性を検討できるようになります。
報告内容
統合報告書は、企業の財務情報・非財務情報を統合させたものであり、具体的には企業理念や成長戦略、ビジネスモデルや持続可能性などについて記載します。一方でサステナビリティレポートは非財務情報、特にCSRやサステナビリティに関する内容に特化しており、その点では統合報告書よりも詳細であるといえるでしょう。
報告対象
統合報告書は、主に投資家や株主などの財務資本提供者を報告対象とするのに対し、サステナビリティレポートはより幅広いステークホルダーが対象です。具体的には、株主や投資家のほかに顧客・取引先・従業員、地域社会や行政機関などさまざまな利害関係者が該当します。
ただ統合報告書の記載内容は財務資本提供者以外のステークホルダーにも有益であるため、従業員に企業ビジョンを浸透させたり求職者に自社の魅力をアピールしたりするなど、さまざまな目的で活用されるケースもあります。
開示義務
2025年時点では、日本において統合報告書とサステナビリティレポートのいずれも、制作・開示は義務化されていません。しかし、統合報告書を発行する企業数は増えており、“統合報告書発行状況調査2024」によると、2024年1月~12月末時点の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加しています。
制作視点
統合報告書は企業のサステナビリティ(持続可能性)を意識した視点で制作しますが、財務情報も含む中長期的な戦略および持続的な成長にも焦点が当てられている点がポイントです。一方でサステナビリティレポートでは、環境や社会に対する企業の取り組みが重視されます。企業を取り巻く幅広いステークホルダーに影響を与えるトピックに関する取り組みを報告します。
統合報告書やサステナビリティレポートを制作するメリット

統合報告書とサステナビリティレポートは、いずれもサステナビリティに関する情報を記載するという点では類似しています。こうした特性から、企業が統合報告書・サステナビリティレポートを制作・発行することで、次のようなメリットを得ることができると考えられます。
- 企業イメージの向上につながる
- ステークホルダーとの対話が深まる
- 資本市場に自社の情報を提供できる
企業イメージの向上につながる
統合報告書やサステナビリティレポートを制作することで、持続可能性に対する自社の取り組みをステークホルダーに示すことができます。近年では投資家・株主のみならず、顧客や従業員、就職活動をしている学生など、多様なステークホルダーがサステナビリティへの関心を高めています。統合報告書・サステナビリティレポートの発行により、ステークホルダーに対して社会的な責任を示すとともに、透明性をアピールし、良好な企業イメージを形成できるでしょう。
ステークホルダーとの対話が深まる
統合報告書やサステナビリティレポートを適切に制作することで、企業のサステナビリティやESGへの取り組みを客観的に伝えることができます。報告書で示す情報の透明性は、企業の価値観・実績を示す手段となり、ステークホルダーの信頼獲得につながります。その結果、投資家や株主などの財務資本提供者を主体とするステークホルダーと、建設的な対話ができる関係を築けるのです。
資本市場に自社の情報を提供できる
統合報告書やサステナビリティレポートを公開することで、サステナビリティに関心の画る投資家に必要な情報を提供できます。これにより、資本市場と企業情報の非対称性を解消して投資家の関心を惹きつけ、資金調達の円滑化につながることが期待できるでしょう。
統合報告書とサステナビリティレポートの使い分け方

これまで説明してきた通り、統合報告書とサステナビリティレポートは制作目的や構成内容などが異なりますが、非財務情報については両者の使い分けが難しいケースがあるでしょう。統合報告書とサステナビリティレポートの内容に重複が多くなると、両者を分けて発表する意味がなくなり、かえって自社の実績や取り組みが希薄であるかのように思われかねません。
そこで統合報告書を制作する場合は、次のようなポイントを意識することが大切です。
- “統合思考”を理解する
- 基本的に“自社”に焦点を当てる
“統合思考”を理解する
統合報告書は、財務情報と非財務情報が完全に統合された形が理想です。そのためには、財務諸表に焦点を当てた短期的思考から、中長期的な価値を創造するための意思決定と行動につながる“統合思考”が欠かせません。
IFRS財団の“統合報告フレームワーク”によると、統合思考とは「組織の事業・機能と資本の関係を能動的に考えること」を意味します。すなわち、自社の企業価値を最大化するために、社会・環境から受ける正と負の影響を、自社の事業活動と結び付けて考えることが大切になります。
基本的に“自社”に焦点を当てる
サステナビリティレポートでは、CSRやESGといった社会に対する取り組みに焦点が当てられており、自社が社会に与えている正負両面のインパクトに関する内容が求められます。言い換えれば、自社の競争力よりも社会全体の持続可能性というテーマで、自社の存在意義を説明するためのものがサステナビリティレポートです。
一方で統合報告書は、財務諸表に代表される財務情報やビジネスプラン・戦略などが含まれることからも分かるように、自社の競争力や中長期的に生み出せる価値をアピールすることが重要になります。つまり、統合報告書は自社に焦点を当てて、自社としての持続可能性をアピールするための媒体ということになります。
組織に統合思考を浸透させる
企業の持続可能性を担保するためには、業績はもちろん企業文化やガバナンスのような、非財務的な要素も重要になります。そのため数値だけではなく、他社と比べて自社のユニークな取り組みや体制などについて、統合報告書でアピールすることも大切です。
完全にIntegrated(統合)された情報を発信するためには「自社の価値とは何か」「自社は何を目指すのか」を示す必要があります。しかし、日本企業において見られがちな部門間の壁(縦割り組織)を乗り越え、組織全体のコミュニケーションを活性化させ、統合思考を組織文化として根付かせる努力をしなければ、報告書の内容が実態と伴わない表面的なものになる可能性があります。そのため、全社一丸となって情報を共有するための体制や仕組みの構築が大切です。
統合報告書を制作する方法
統合報告書を制作する方法として、次の2つの選択肢が考えられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的や状況に合わせたものを選ぶことが大切です。
- 社内リソースで制作する
- 外部業者を活用して第三者意見を取り入れる
社内リソースで制作する
自社の社内リソースで統合報告書を制作する場合は、自社ならではの魅力を媒体に反映させやすくなります。前述したように、理想的な統合報告書の制作には統合思考の実践が欠かせず「自社自身のことをどこまで理解できているか」が重要なので、そこを理解した報告書制作ができることは大きなメリットです。
ただし、統合報告書の制作には多岐にわたる情報を整理して分かりやすく伝える必要があるため、知見のあるメンバーを起用した専門チームが必要になるかもしれません。その場合は人的リソースの圧迫につながることに注意が必要です。
外部業者を活用して第三者の視点を取り入れる
統合報告書の制作には、専門知識が欠かせません。そこで外部業者を活用して第三者意見を取り入れることで、より客観的で良質な統合報告書を制作できるようになります。ただし外部業者やコンサルタントの選定時は、専門性・経験・コンプライアンスに関する知識などに加えて自社ビジネスへの理解が重要なので、自社に最適なパートナーを選びましょう。
統合報告書の制作に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書とサステナビリティレポートは、いずれもサステナビリティ情報を記載しますが、統合報告書は自社の持続可能性・長期戦略・価値創造プロセスに焦点を当てていることが特徴です。このポイントを意識することで、ステークホルダーに自社の中長期的な価値をアピールするという、統合報告書ならではの成果が得やすくなるでしょう。しかし、統合報告書の制作には専門的な知識やノウハウが必要になるため、自社リソースだけでは対応できないケースが少なくありません。
そこで統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。