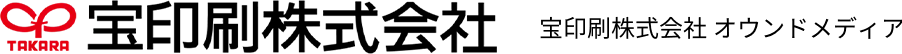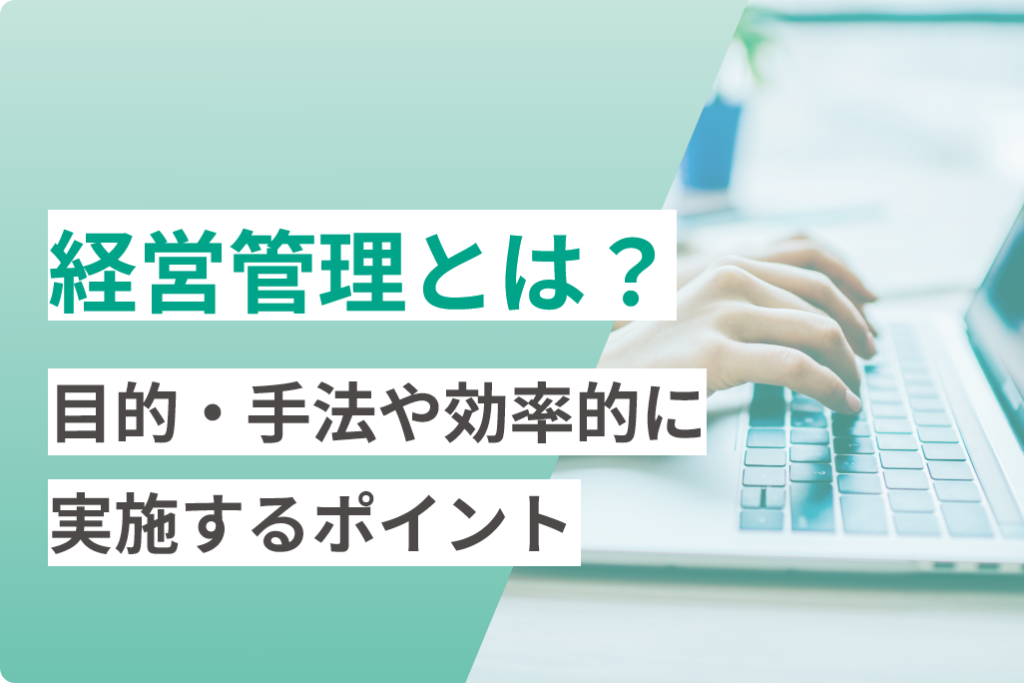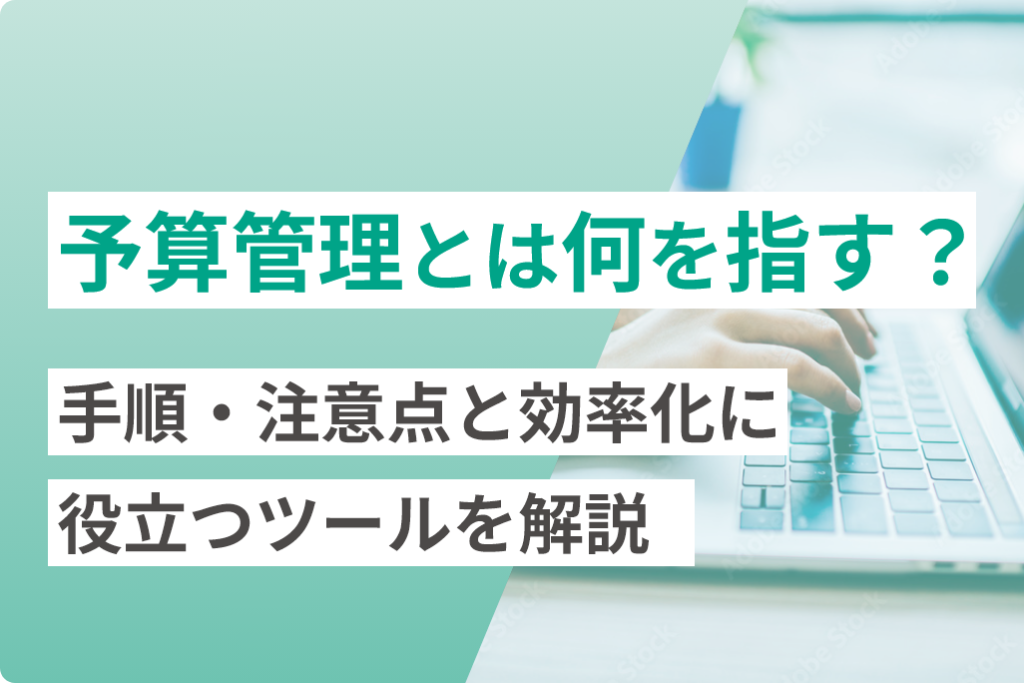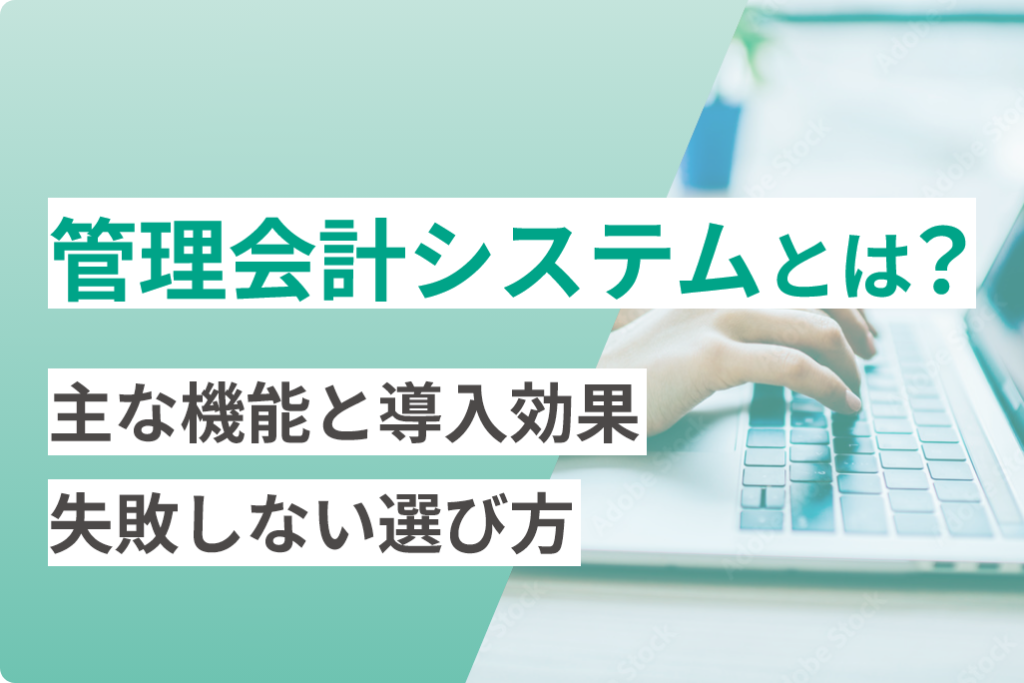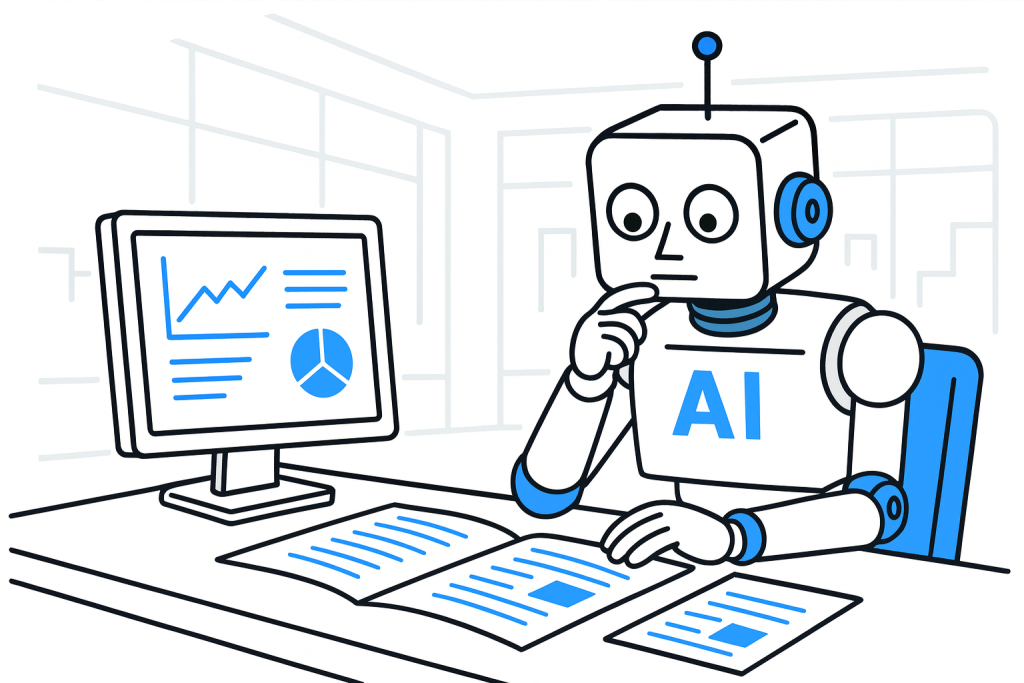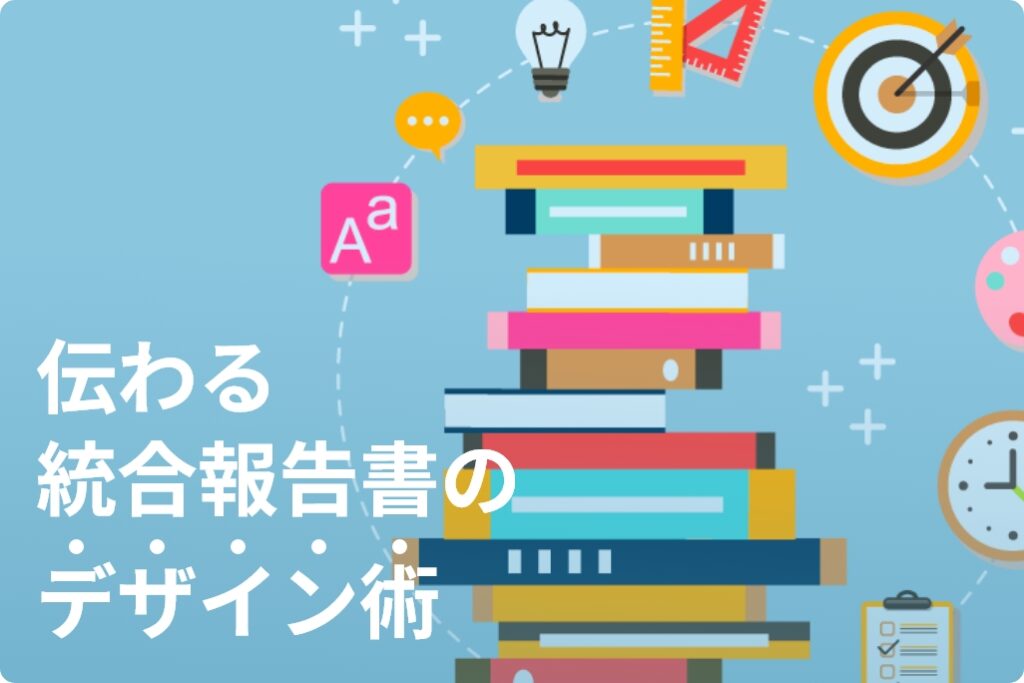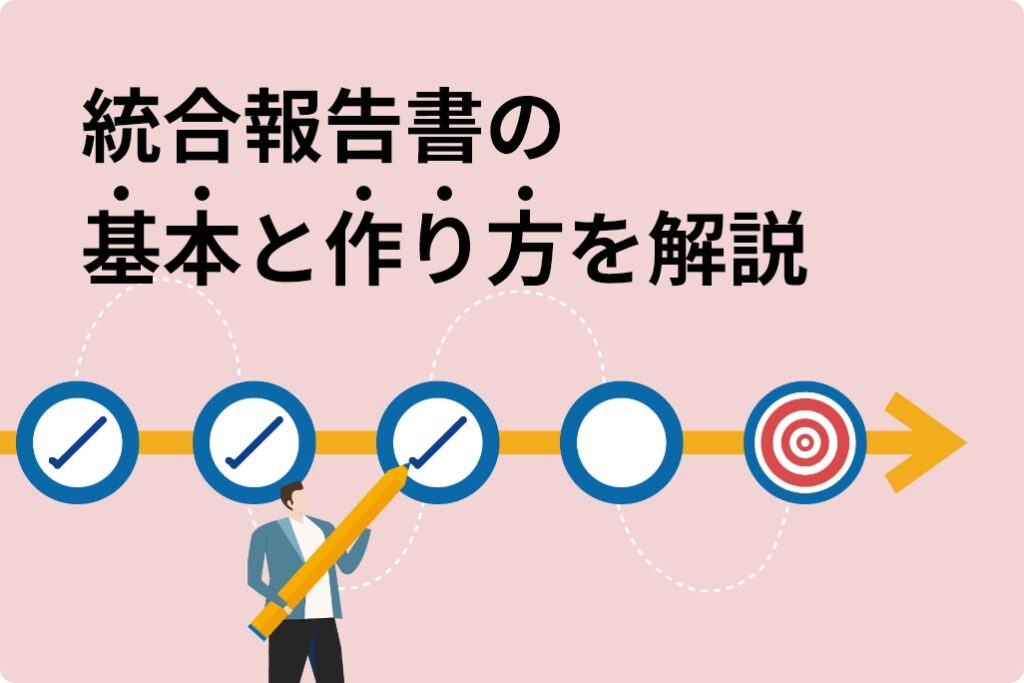企業の活動内容や成果をステークホルダーに伝え、理解を深めてもらうために“統合報告書”や“アニュアルレポート”といった情報開示ツールを活用する企業が増えています。
統合報告書とアニュアルレポートは、類似している部分もありますが、その目的や主な記載内容、対象読者などには明確な違いがあります。これらの違いを理解した上で、それぞれの報告書を作成・活用することが大切です。
本記事では、統合報告書とアニュアルレポートの違いや、統合報告書ならではのコンテンツづくりのポイントについて解説します。
統合報告書とアニュアルレポートの概要

統合報告書とアニュアルレポートの違いについて検討する前に、まずは概要を確認しておきましょう。
- 統合報告書とは
- アニュアルレポートとは
- 公開先は自社サイトが一般的
統合報告書とは
統合報告書は、企業の財務情報と非財務情報を統合させた媒体です。財務情報は企業の売上や資産など、非財務情報はESG(環境・社会・ガバナンス)やCSR(企業の社会的責任)に関する取り組み状況などを示します。
単に財務情報と非財務情報を並べて記載するのではなく、これらの情報を“統合思考”に基づいて企業の価値創造プロセスの中で有機的に結びつけ、過去・現在・未来にわたる中長期的な成長ストーリーとして説明する点に本質があります。環境や社会などに対する企業の取り組みを統合報告書で示すことで、従来の報告書では表現できない企業の強みをステークホルダーにアピールできます。
アニュアルレポートとは
アニュアルレポートとは、主に企業の過去1年間の財務実績や事業活動の成果を株主や投資家などのステークホルダーに報告するために活用される年次報告書です。アニュアルレポートには、損益計算書(PL)や貸借対照表(バランスシート)、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表が含まれます。
投資家や株主に対して企業の財務的なパフォーマンスを開示し、意思決定をサポートすることがアニュアルレポートの目的です。ただし、近年ではアニュアルレポートでも非財務情報について記載するケースもあり、統合報告書と混同されやすくなっています。
両者の大きな違いは視点です。基本的に年度単位の財務報告に主眼が置かれたアニュアルレポートに対し、統合報告書は自社の経営戦略・価値創造について長期的視点からステークホルダーに示します。
公開先は自社サイトが一般的
統合報告書とアニュアルレポートは、いずれも自社のコーポレートサイトにPDFファイルを掲載するなど、広く入手できる形にすることが一般的です。そのため、株主・投資家・金融機関などの財務資本提供者はもちろん、取引先の企業や求職者・消費者など広範なステークホルダーが企業の詳細情報を知ることができるようになっています。
統合報告書とアニュアルレポートの違い
統合報告書とアニュアルレポートとの違いについて、次の観点から検証していきましょう。
| 統合報告書 | アニュアルレポート | |
| 目的 |
自社の持続可能性・長期戦略や |
過去1年間の財務情報の透明性を担保 |
| 内容 | 財務情報や非財務情報の統合 | 財務情報や経営分析がメイン |
| 義務 | いずれも開示義務はない | |
| 視点 |
長期的な戦略および |
短期的な財務成果や1年間の業績の視点 |
制作の目的
企業が統合報告書を作成する主な目的は、自社がどのようにして社会に価値を提供し、持続的に成長していくのか、そのプロセスと将来性(価値創造ストーリー)を、財務情報と非財務情報を統合して多角的に示すことです。企業の持続可能性や長期戦略に重点を置くため、財務情報のみならずサステナビリティに関する情報が多く含まれます。
一方で、アニュアルレポートを作成する主な目的は、投資家や株主に対して企業の財務情報を報告することです。投資家や株主などの財務資本提供者を主な対象者とする点では統合報告書と同じですが、アニュアルレポートは企業の財政状態や経営成績、キャッシュ・フローといった財務情報が中心となる点が特徴です。
報告内容
統合報告書は、前述したように企業の財務情報と非財務情報を統合させて、ステークホルダーに開示します。アニュアルレポートとは異なり、非財務情報にも重点が置かれている点が特徴です。例えば、事業活動に影響を与える気候変動への対応状況や競争優位を支える人材の確保・育成など、自社が中長期的に価値やキャッシュを創造し続けるための取り組みが含まれます。
アニュアルレポートは主に財務情報が中心となるため、損益計算書や貸借対照表(バランスシート)、キャッシュ・フロー計算書といった財務諸表に加え、それらに対する経営陣からの報告や分析などが詳細に記載されます。
報告対象
統合報告書とアニュアルレポートは、いずれも株主や投資家などの財務資本提供者を主要な対象者とします。ただし、統合報告書に記載される企業の情報は、顧客・取引先・従業員、地域社会や行政機関など、より広いステークホルダーにとっても有益なものです。
したがって、企業が統合報告書を作成する目的によっては、財務資本提供者に加えてほかのステークホルダーも対象とするケースもあります。一方でアニュアルレポートの場合は、基本的には投資家や金融機関に対象をしぼって作成されます。
開示義務
2025年時点では、日本において統合報告書とアニュアルレポートのいずれも、作成・開示は義務化されていません。しかし、統合報告書を発行する企業数は増えており、「統合報告書発行状況調査2024”に記載したように、2024年の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加しています。なお、有価証券報告書では企業のサステナビリティ情報の開示が2023年に一部義務化されました。統合報告書でもサステナビリティ情報を記載することから、その流れで統合報告書の発行数も年々増えているという背景が考えられます。
制作視点
統合報告書は、企業の“持続可能性”に注目していることが特徴です。短期的な財務的成果も求められますが、長期的に価値・キャッシュを創出できる企業であると示すことが、統合報告書では重視されます。一方でアニュアルレポートは、あくまでその年の財務的成果に焦点を当てて制作するため、ESGやCSRなどのサステナビリティ情報は二次的な扱いとなることが多くなっています。
統合報告書が必要とされる理由

前述したように、統合報告書の発行件数は年々増加傾向にあります。統合報告書は、他の開示書類とは異なる独自の役割を担っており、企業が達成した成果だけでなく、将来にわたる価値創造ストーリーや持続的な成長戦略をステークホルダーに包括的に伝える上で、非常に重要なツールとなっています。
統合報告書が企業とステークホルダーに必要な理由について、次の観点から説明します。
- ステークホルダーとの信頼関係を強化するため
- 持続可能性へのコミットメントを表明するため
- 統合思考を実践する重要性が高まっているため
ステークホルダーとの信頼関係を強化するため
企業が統合報告書を作成・開示することで、財務資本提供者に代表されるステークホルダーとの信頼関係を強化できます。投資家や金融機関が投資判断を行う際は、財務上の成果だけではなく企業の信頼性が重視されます。統合報告書で持続可能性や価値創造プロセスを透明化することで、自社のガバナンスを示し、ステークホルダーからの理解と支持を得ることができるでしょう。
持続可能性へのコミットメントを表明するため
統合報告書では、自社の社会的・環境的な取り組みについて記載するため、持続可能性へのコミットメントをステークホルダーにアピールできます。これにより、ESG投資などサステナビリティを重視する投資家に対して、企業の取り組みに関する具体的な情報を提供し、資本市場からの適切な評価や建設的な対話の促進につながります。
統合思考を実践する重要性が高まっているため
統合報告書とは、財務情報と非財務情報が完全に統合されていることが理想です。それを実現するためには、従来の財務諸表に焦点を当てた短期的思考から、中長期的な価値を創造できる意思決定・行動につながる“統合思考”が欠かせません。
IFRS財団の“統合報告フレームワーク”によると、統合思考とは「組織の事業・機能と資本の関係を能動的に考えること」を意味します。言い換えれば、自社の企業価値を最大化するために、社会や環境から受ける正・負の影響を自社の事業活動と結び付けて考えることです。
Integrated(統合)された情報を発信するためには、「自社の価値とは何か」「自社は何を目指すのか」を明確化する必要があり、全社一丸となって情報を共有して取り組むことが大切です。
統合報告書を開示するメリット
前述したように、統合報告書とアニュアルレポートには作成目的や内容・視点など、さまざまな点で違いがあります。こうした点から、統合報告書を開示することで次のようなメリットがあると考えられます。
- 財務資本提供者とのコミュニケーションの質が向上する
- 投資家・資本市場と企業の情報ギャップを減らす
- 自社の価値創造プロセスの明確化と共有につながる
財務資本提供者とのコミュニケーションの質が向上する
統合報告書を開示することで、投資家や株主などの財務資本提供者に対し、自社の価値創造プロセスをアピールできます。自社が将来的にキャッシュ・価値を生み出すための戦略や取り組みを明示することで、ステークホルダーと建設的なコミュニケーションができるようになるでしょう。統合報告書にトップメッセージを記載することで、経営陣の熱意やコミットメントをアピールすることも可能です。
投資家・資本市場と企業の情報ギャップを減らす資本
投資家や資本市場が保有する情報は限られているため、企業の情報とのギャップが生じるケースがあります。統合報告書を通じて、企業の持続可能性(サステナビリティ)に対する戦略や具体的な取り組みを開示することで、ステークホルダーに適切な情報を提供できます。これは財務資本提供者との建設的な対話と信頼の醸成はもちろん、資本市場と自社間の情報ギャップの軽減にもつながります。これにより、資本市場から自社が受ける評価の変化も期待できるでしょう。
自社の価値創造プロセスの明確化と共有につながる
統合報告書を作成する過程で欠かせないのが、自社がどんな姿を目指し、将来的に価値を生み出すために、何にどのように取り組むかを考えることです。その過程で自社のビジネスモデルや戦略、成長機会やリスクなどを改めて分析し、将来志向で見つめ直す機会が得られます。こうして明確化された“価値創造プロセス”を統合報告書に反映することで、ステークホルダーに自社の将来的な価値をアピールするとともに、社内でも全体の共通認識として共有することができます。
統合報告書に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書とアニュアルレポートの主な違いが目的と内容です。統合報告書は自社の持続可能性・長期戦略・価値創造プロセスが主題であるのに対し、アニュアルレポートは過去1年間の業績や財務的な透明性を担保するためのものです。こうした違いを意識して統合報告書を制作することで、自社の企業価値をステークホルダーにアピールしやすくなるでしょう。しかし、統合報告書の制作には専門的な知識やノウハウが必要になるため、自社リソースだけでは対応できないケースが少なくありません。
そこで統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。