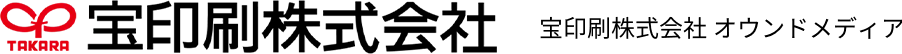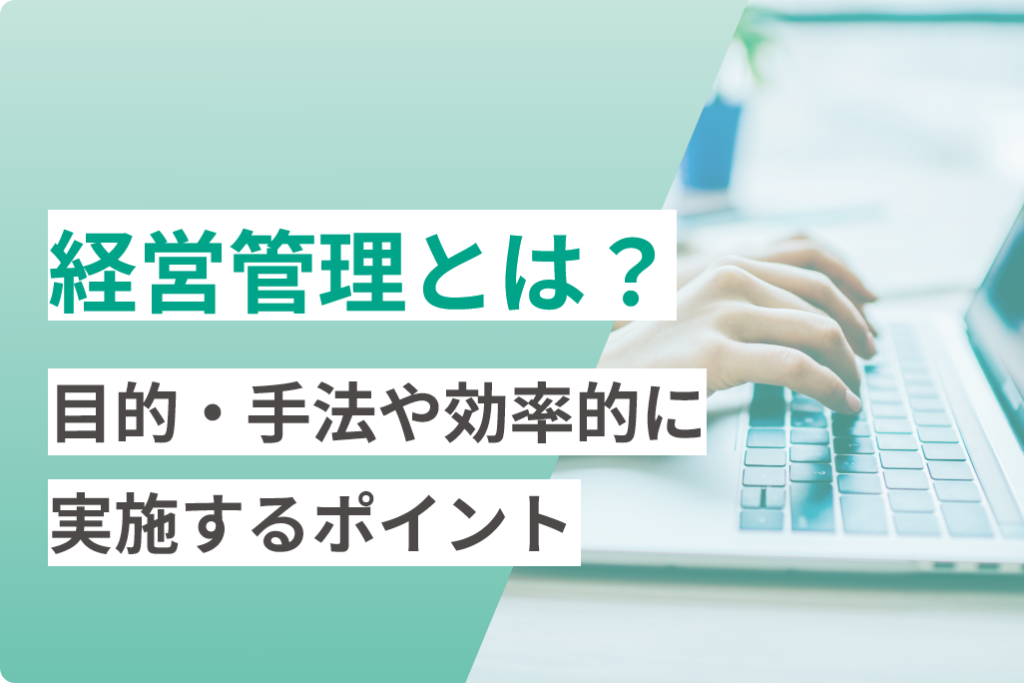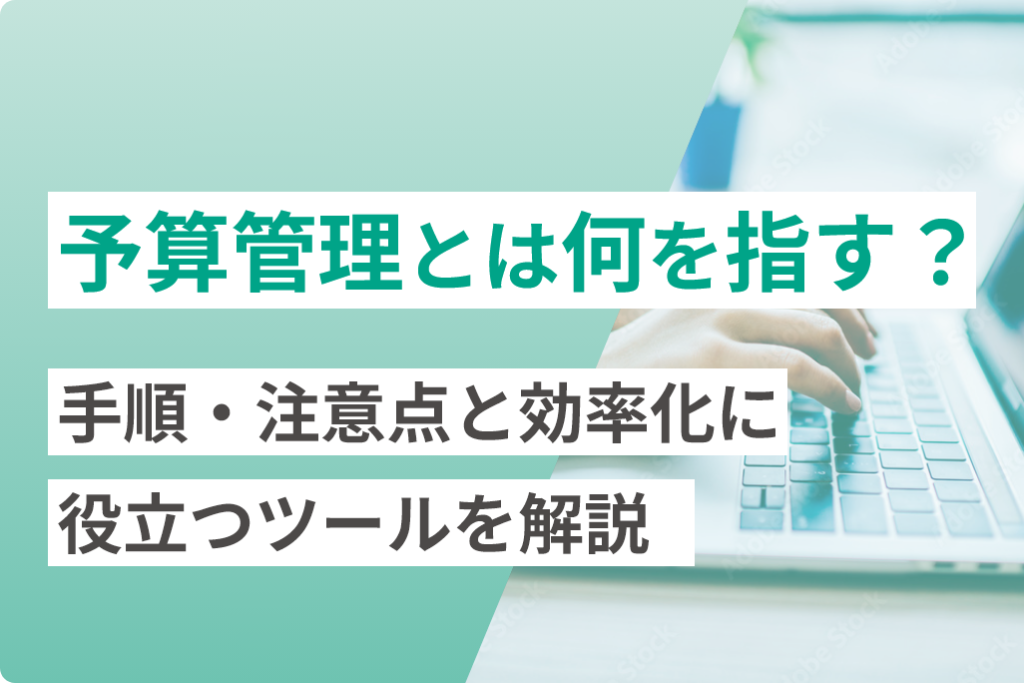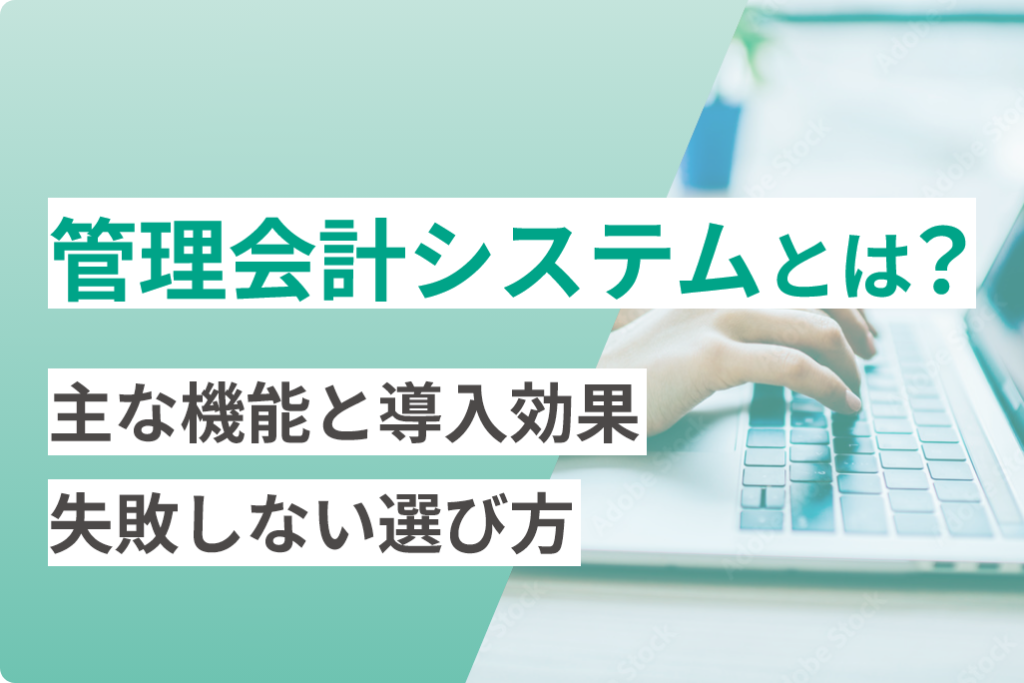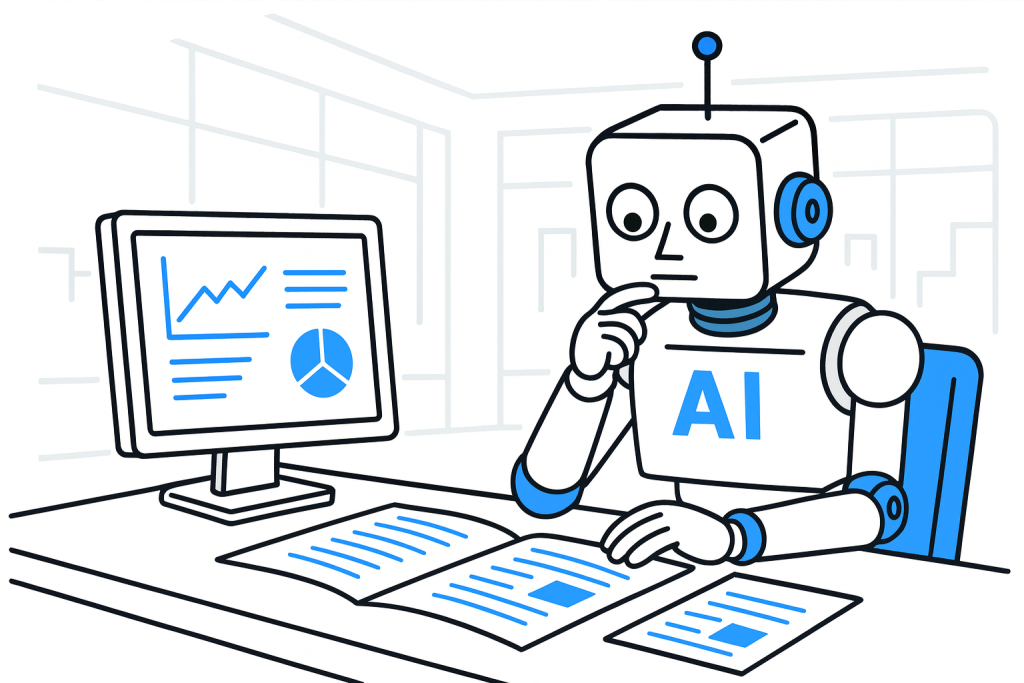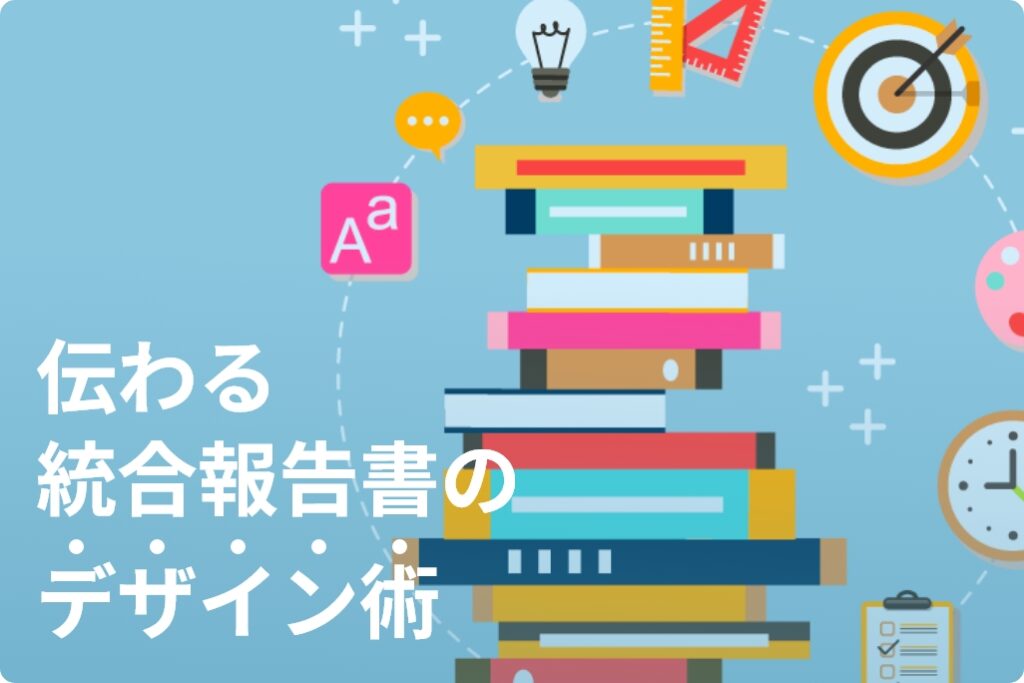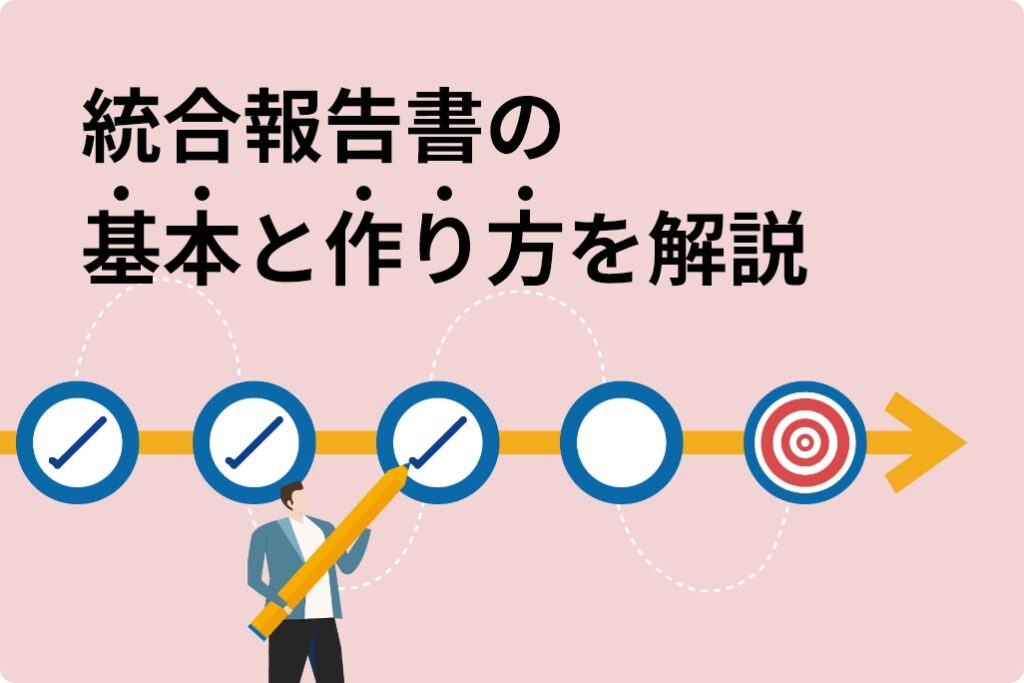多岐にわたる内容が記載される統合報告書は、情報量が多い分、専門知識がないと読み解くのは難しいと感じるかもしれません。一方、統合報告書ならではの視点や読み解き方を知れば、企業に関する情報をより深く、適切に理解する助けになります。
本記事では、統合報告書の見方をできるだけわかりやすく整理してご説明しようと思います。
統合報告書とは
統合報告書の見方を理解するためには、まず「統合報告書とは何か」知っておく必要があります。そのため統合報告書の次のポイントを確認しましょう。
- 企業の財務情報・非財務情報を統合させた媒体
- 企業の目指している姿と長期的に生み出す価値が分かる
- 統合報告書を作成・公開する企業は増加傾向にある
- 各企業のコーポレートサイトで公開されている
企業の財務情報・非財務情報を統合させた媒体
統合報告書とは、企業の財務情報と非財務情報を統合させた媒体で、“IR(Investor Relations)情報“のひとつです。
IR情報は、本来は企業が投資家に向けて経営状況や財務状況について発信するものですが、近年では投資家以外にも取引先や求職者といった広いステークホルダーが見るケースも増えています。
統合報告書に記載される財務情報は売上や資産といった定量的なデータが中心であり、非財務情報はCSR(企業の社会的責任)活動などのサステナビリティ情報が中心です。また、売上やCSR活動といった情報を併記するだけではなく、両方の要素を企業価値と関連付けて将来志向の企業価値向上ストーリーとして語るのが統合報告書の役割です。
企業の目指している姿と長期的に生み出す価値が分かる
統合報告書には、その企業が将来的に目指す理想像を軸に現状を分析した内容が記載されています。そして、その理想を達成する過程で生じると想定される課題にどのように取り組むか、その方針や戦略を示しています。
統合報告書の重要な論点として、ESG(環境・社会・ガバナンス)やCSR(企業の社会的責任)などの課題に対し、企業がどう向き合うかという点があります。これらの情報で、読者に自社ならではの活動や持続的な成長戦略を伝え、中長期的にどんな価値を創造できるかを理解してもらえます。
各企業のコーポレートサイトで公開されている
統合報告書は各企業の公式サイトで公開されており、一般的にPDF形式などで閲覧できます。ただ、後述するように統合報告書の開示は法令等で義務化されていないので、どの企業でも必ず公開されているとは限らないことに注意しましょう。
作成する企業は増加傾向にある
2025年時点では、日本で統合報告書の作成・開示は義務化されていません。ただ、ステークホルダーとのコミュニケーションを深める目的で統合報告書を発行する企業は増えつつあるんです。
統合報告書発行状況調査2024によると、2024年1月~12月末時点の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加しています。
企業の統合報告書を見るべき理由

統合報告書に記載される情報は多岐にわたるため「投資家や株主などの専門家のためのもの」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、統合報告書は、下記のような理由により取引先や求職者といったステークホルダーにとっても価値のある媒体といえます。
- 企業のビジョンや事業を理解できる
- 企業の正確な一次情報を得ることができる
- 企業の“求める人材“を把握する
- 同業他社との比較検討がしやすくなる
企業のビジョンや事業を理解できる
統合報告書を読むことで、その企業が何を目指して事業を営んでいるかが分かります。具体的にどのような思想・ビジョンを掲げて、どんな価値を生み出す存在になろうとしているのか、将来志向の情報が統合報告書には掲載されています。
企業の正確な一次情報が得ることができる
現在ではインターネット上でさまざまな情報が得られますが、根拠のない誤ったものも少なくありません。例えば、ニュースやSNSなどで伝えられる二次的な情報が、実際には事実と異なるといったケースも見受けられます。統合報告書などのIR情報は企業が自ら公開する一次情報なので、より正確な情報を伝えることができます。
企業の“求める人材“を把握する
企業が統合報告書を作成する目的によっては、求職者や従業員を対象にしたコンテンツが掲載されている場合があります。そこに人材育成や労働環境などの情報が含まれていれば、就職や転職を目指す求職者が、求人へ応募する際の判断に役立つでしょう。
同業他社との比較検討がしやすく
複数の企業の統合報告書を確認することで、掲載されている財務情報や非財務情報をもとにさまざまな観点から比較しやすくなります。ただ、統合報告書は構成や内容の自由度が高い媒体であるため、比較検討を目的とする場合には記載形式が整備されている“有価証券報告書“のほうが向いているケースもあります。
統合報告書を読み解くポイント

統合報告書を読み解くために、次のようなポイントを意識しましょう。
- トップメッセージを重視する
- 財務情報を分析する
- 企業の歴史と価値観を理解する
- 価値創造プロセスを評価する
- 成長戦略とガバナンスを把握する
- マテリアリティを見極める
トップメッセージを重視する
統合報告書では、主に前半部分に社長(CEO)や経営陣などの“トップメッセージ“が記載されることが多くあります。トップメッセージには、ビジョンと価値観の明確化やステークホルダーへのコミットメントなど、これからの企業の将来像を示す重要な要素が含まれています。
また経営の持続可能性に関する記述についても確認することが大切です。例えば、将来の経営環境の展望や事業モデルの変革イメージのような、統合報告書でしか読めない経営陣の考え方が記載されていれば、統合報告書全体の記載内容や企業価値評価における信頼度を高めることができると言えるでしょう。
財務情報を分析する
財務担当役員(CFO)のメッセージでは、企業のキャッシュフロー、つまり稼ぐ能力に関する見通しが記載されます。その稼ぐ力を強化するための投資戦略や、ESG課題への取り組み(例:環境負荷低減目標)といったサステナビリティ戦略との整合性も確認しておきましょう。
企業の歴史と価値観を理解する
多くの統合報告書では沿革図が示されており、いくつかのフェーズに区切って現在にいたるまでの企業の変遷が説明されます。受け継がれてきた価値観や理念を知ることで、企業の商品・サービスに対する理解が深まり、さらにその企業の将来の姿を想像しやすくなるでしょう。
価値創造プロセスを評価する
“価値創造プロセス“は、企業が長期的に生み出そうとしている価値について、関連するさまざまな要素を図表でわかりやすく示すものです。例えば、自社が目指す将来、創出する社会的価値、それを支えるインプット(研究開発力、人的資本、製造資本など)、事業活動、アウトプット、そして最終的なアウトカム(影響)といった要素で構成されます。価値創造プロセスを読み解くことは、統合報告書を理解する重要なポイントになります。
※関連記事
統合報告書の“価値創造プロセス”とは?含めるべき要素やポイントを解説
成長戦略とガバナンスを把握する
価値創造プロセスを実現するためには、しっかりとした成長戦略とガバナンスが欠かせません。成長戦略の項目では持続的な価値創造と利益成長に向けたロードマップやその進捗状況が、そしてガバナンスの項目では持続的な成長を支える経営体制やその実効性について理解することができます。
マテリアリティを見極める
マテリアリティとは、さまざまな社会課題に対する企業の優先順位を意味します。企業が成長することと社会がより良くなることの双方を目指したときに、何を重視して取り組むのかを定めたものです。この項目を確認することで、企業がどのような社会課題を重視して向き合おうとしているのかが分かります。
統合報告書の見方として理解しておきたい考え方

統合報告書の見方として、次のような考え方は特に重要です。
- 時系列の概念
- 多軸的な説明
- ストーリーライン
- アウトカム
時系列の概念
統合報告書には、企業が過去から現在に至るまで、どのような価値観のもとに事業活動を行ってきたかが記載されています。その情報から企業の風土や価値観を知ることができます。さらに、長い歴史のなかで事業が円滑に進まなくなったときに、どのように解決したか、その課題解決力なども見えてくるかもしれません。
多軸的な説明
統合報告書では、企業のビジョンや成長戦略などについて、CEO・CFO・役員など複数のポジションの担当者から語られることがあります。それぞれの言葉に矛盾がなく、納得のいく説明や実現可能性の高い戦略が語られていれば、その企業の信頼性は高いと判断できます。
ストーリーライン
統合報告書は、単に数値やデータを羅列しているだけのレポートではありません。前述したように、統合報告書は財務情報と非財務情報を企業価値に関連付け、中長期的な企業の企業価値向上ストーリーを説明するものです。この点を理解して統合報告書を読むことで、企業がどのような背景や目的で情報を開示し、どのような理念のもと社会・環境と関わりながら成長していきたいと考えているのか、一貫したストーリーで読むことができます。
アウトカム
統合報告書には、アウトプットの結果としてもたらされる“アウトカム(影響)“が記載されています。企業の資本は“インプット“として活用され、事業活動を通じて製品・サービス・副産物などのアウトプットに変換されます。さらにその結果として生じるのが、企業の事業活動が各種資本(財務資本、人的資本など)や社会・環境、ステークホルダーに与える正と負両方のアウトカムです。アウトカムが明確に示されている統合報告書を発行している企業は、自社が社会や環境に対して与える影響を真剣に考えているといえるでしょう。
見方を意識して統合報告書の作成を意識しよう
ここまで解説してきた統合報告書の見方は、企業が統合報告書を作成する際にも役立ちます。作成する際は、これまで述べてきた読者の視点や読み解き方のポイントを活かし、次のような点を意識してみましょう
- 価値創造プロセスを明示する
- さまざまな視点を考慮する
- “読みやすさ“を最優先にする
価値創造プロセスを明示する
統合報告書の価値創造プロセスは、企業が中長期的な価値を生み出す過程を示すものです。統合報告書に記載すべきとされている要素を一枚絵に落とし込んだものであり、統合報告書のサマリーといえるでしょう。ステークホルダーに伝わる統合報告書を作るには、図表などを用いて価値創造プロセスを分かりやすく明示することが大切です。ただし、それが絵空事になってしまわないように、自社の実績や取り組みを踏まえた現実的な内容を記載しましょう。
さまざまな視点を考慮する
統合報告書は主に投資家や株主などの財務資本提供者を対象としていますが、IFRS財団が示す国際統合報告フレームワークの考え方にもあるように、その情報は従業員、顧客、地域社会など広範なステークホルダーにとっても有益です。そのため、自社が統合報告書を発行する目的や対象読者を精査して、必要とされるコンテンツを掲載することが大切です。例えば、従業員の行動変容を目指す場合は、人材育成や労働環境などで従業員にアピールするとよいでしょう。ただし、統合報告書の主要な読者層はあくまで財務資本提供者なので、情報開示の優先順位は考慮しましょう。
“読みやすさ“を最優先にする
統合報告書は、機関投資家や株主のような“プロ“だけが読むものではなく、今回解説したように投資家以外に取引先や求職者などが読むこともあります。そのため、こだわり抜いて作った報告書が、必ずしもステークホルダーに良い印象を与えるとは限りません。どうしても複雑にならざるを得ない部分もあるかもしれませんが、できるだけ分かりやすく、読みやすくなるように心掛けましょう。
統合報告書に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書の読者は、価値創造プロセスや成長戦略・ガバナンスなどの項目を見て、その一貫性や実現可能性を判断します。どれだけ見栄えの良い表現で飾っても、自社の価値や持続可能性と真剣に向き合っていない統合報告書は、ステークホルダーから評価されないでしょう。
このように、統合報告書の制作には客観的な視点やノウハウが必要なので、統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。