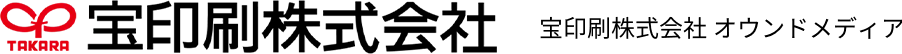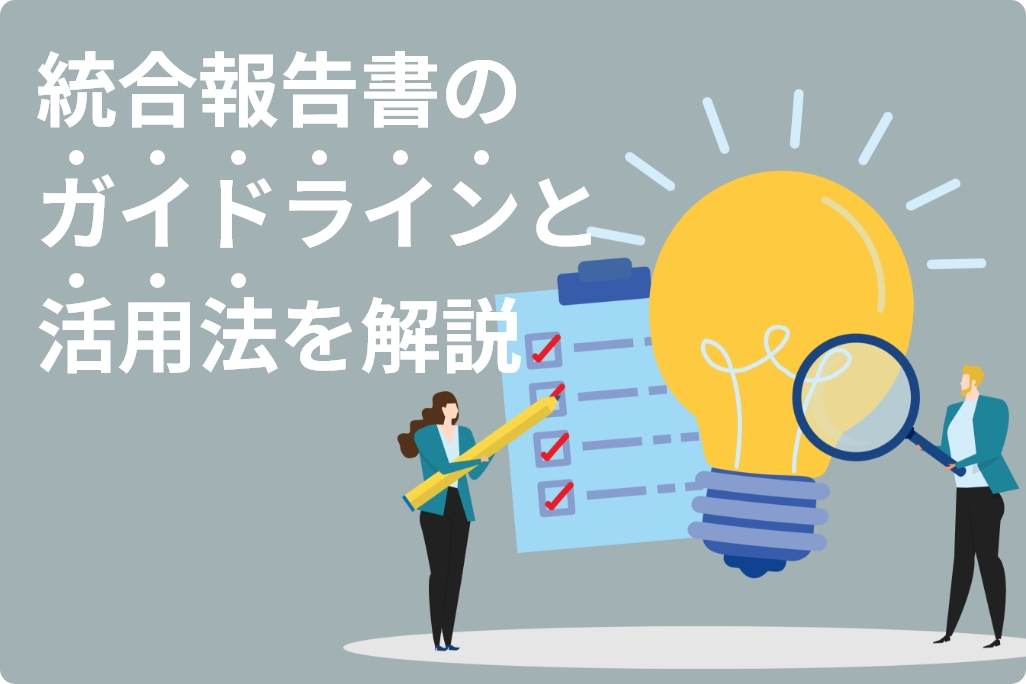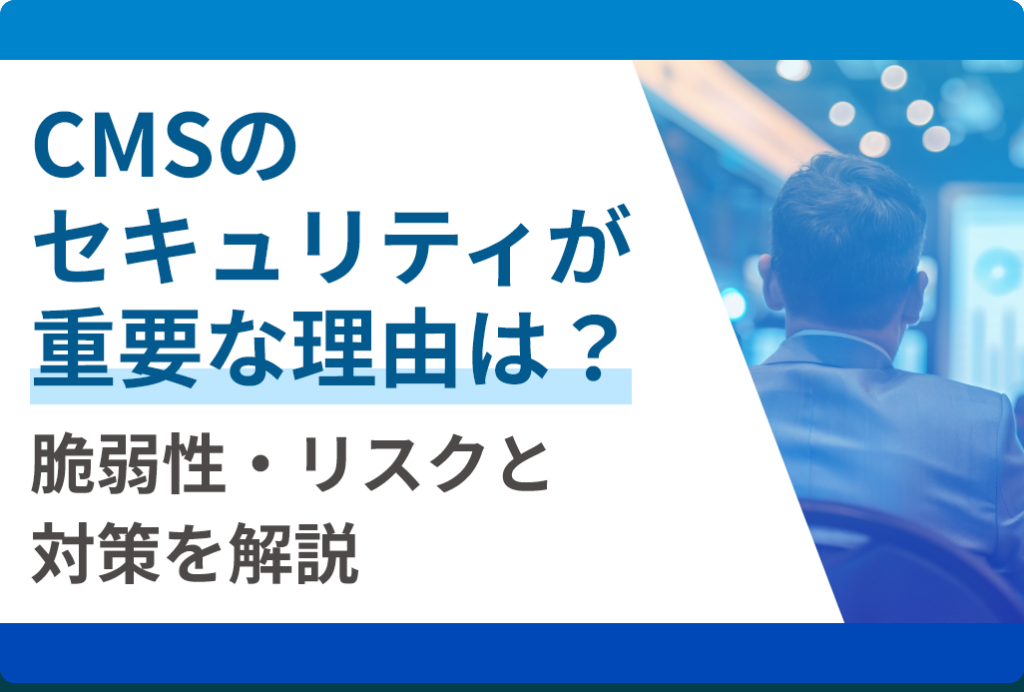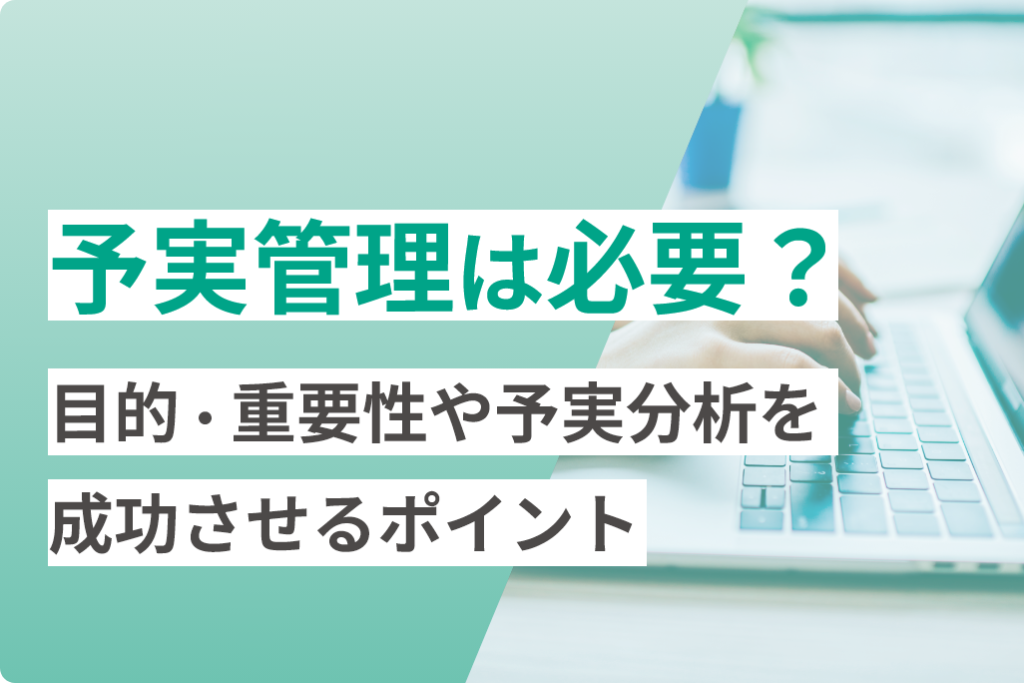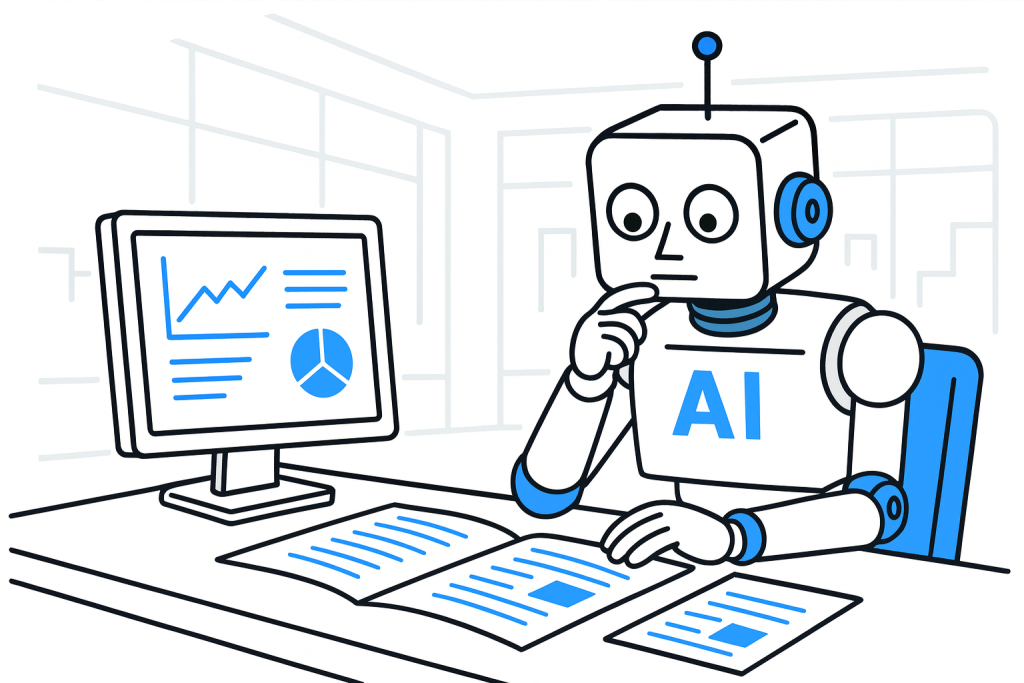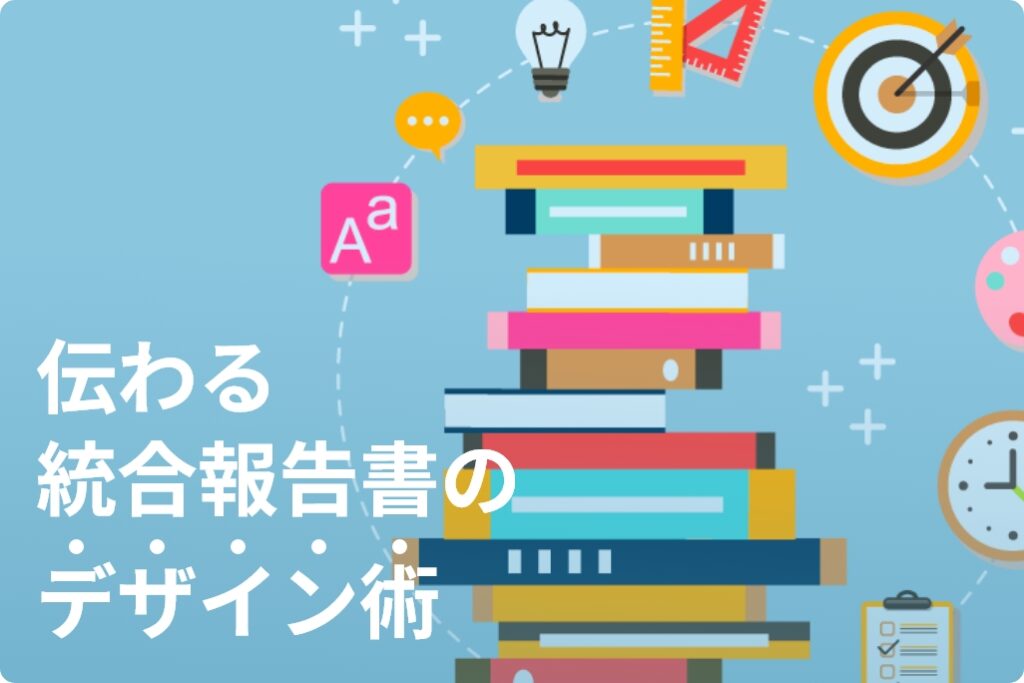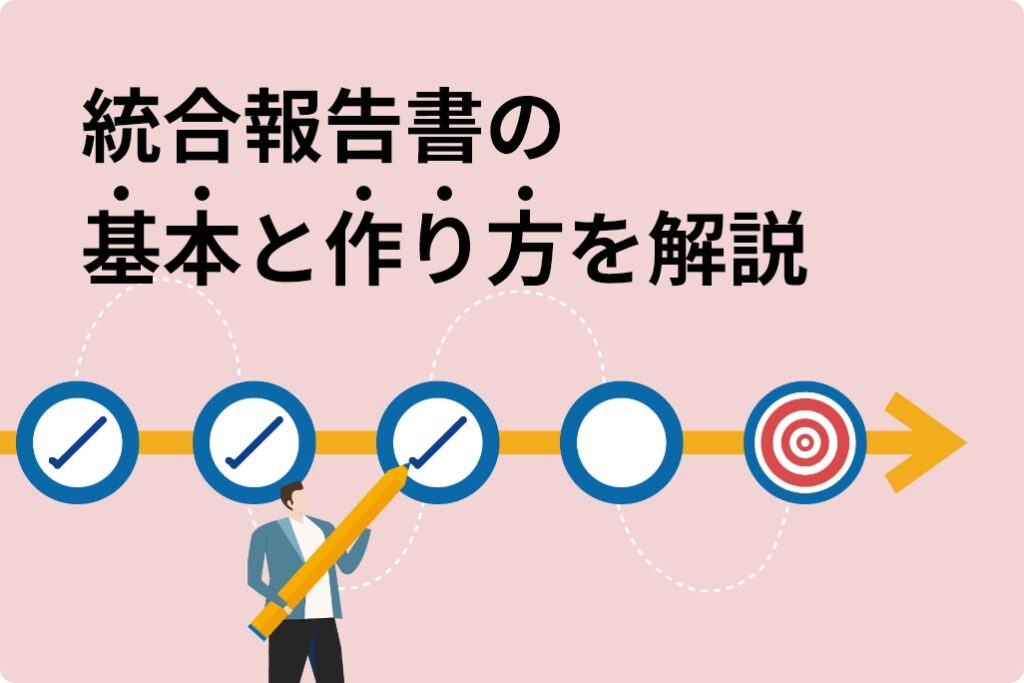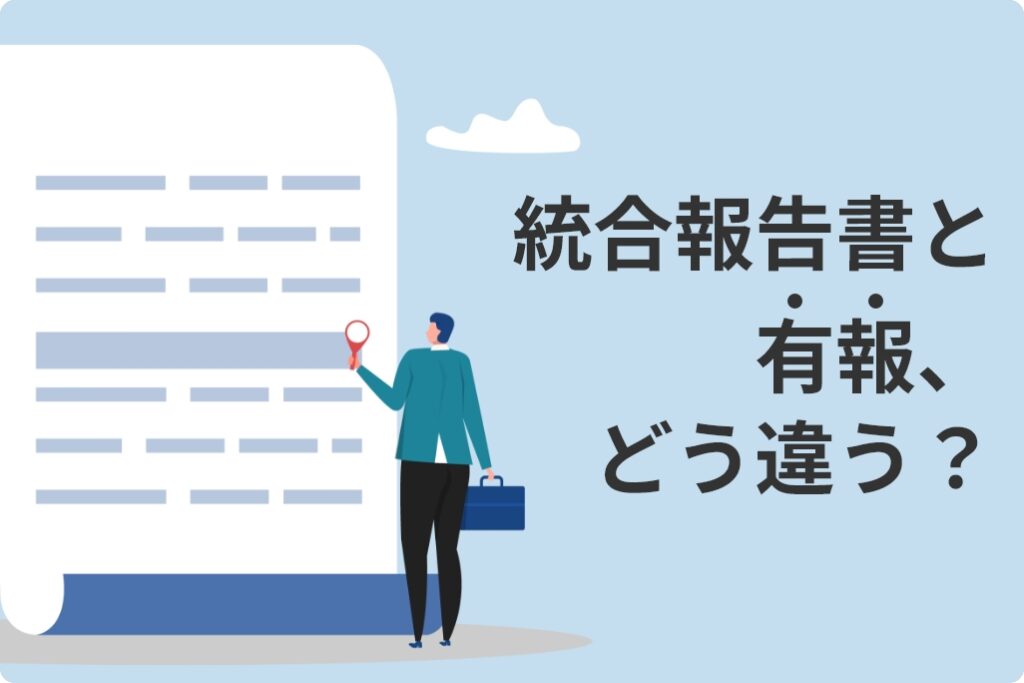統合報告書は、企業の財務情報と非財務情報を統合的に開示し、自社の価値創造ストーリーや長期的な成長戦略をステークホルダーに伝えるための重要な媒体です。
しかし、その作成には、専門的な知識や多岐にわたる情報、そして“統合思考”といった特有の考え方が求められるうえ、明確なフォーマットは定められていないため、担当者にとっては、かえって困難に感じたり、具体的な進め方に悩んだりするケースもあることでしょう。
統合報告書の制作で意識すべき思考や含めるべき情報などを示す手がかりとして、ガイドラインがあります。ガイドラインをしっかりと活用することは、魅力的で伝わりやすい統合報告書を作る手助けになります。
そこで本記事では、統合報告書のガイドラインや重要なポイントについて解説します。
統合報告書のガイドラインとは
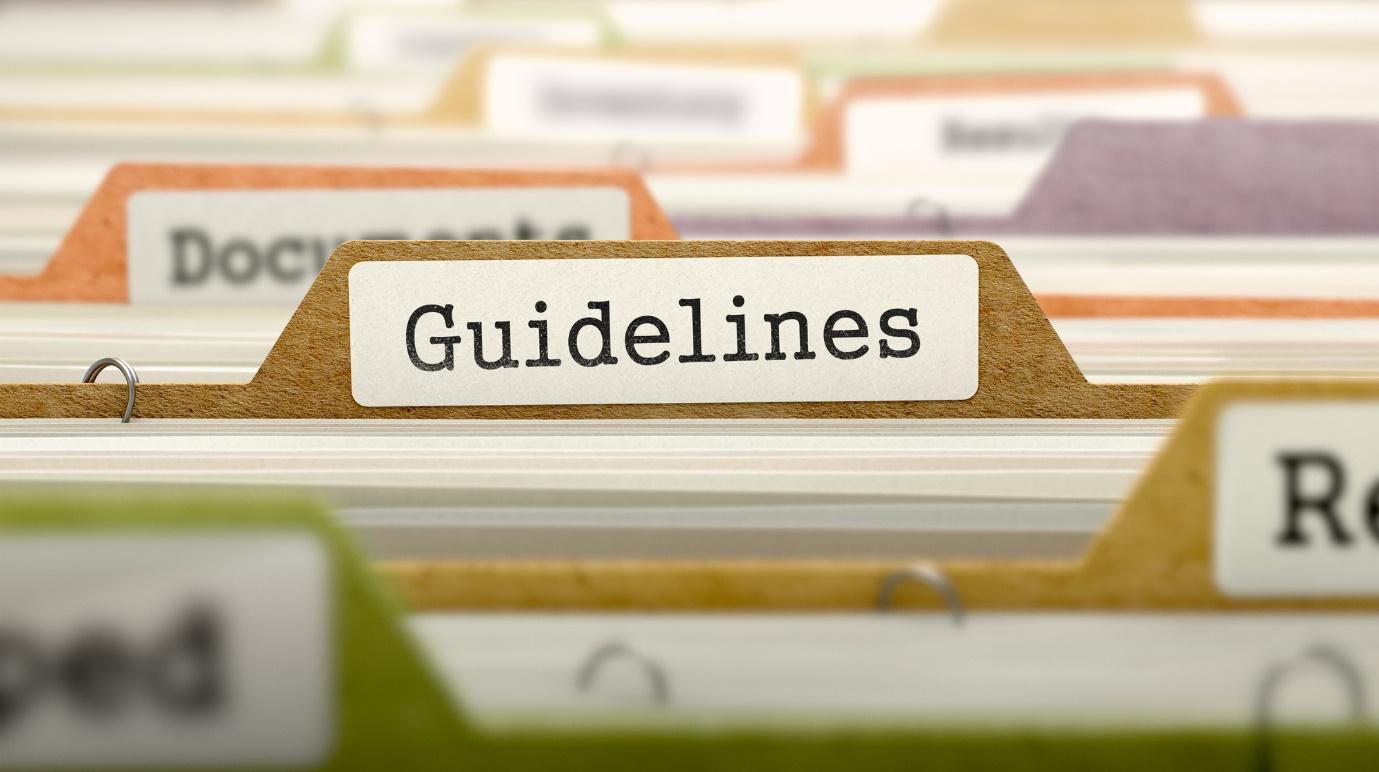
統合報告書のガイドラインについて、まずは次のポイントから見ていきましょう。
- 統合報告書の作成原則や要素をまとめたもの
- 定期的に改正・アップデートが行われている
統合報告書の作成原則や要素をまとめたもの
ガイドラインは、企業が統合報告書を作成する際の指針となります。詳細は後述しますが、統合報告書で要求される項目は多岐かつ広範にわたるため、抜け漏れが生じやすい傾向があります。統合報告書に求められる内容を網羅できていなければ、主たる読者である株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、自社の長期的な企業価値や持続的な成長可能性を十分に伝えることができません。統合報告書の発行などステークホルダーとの対話のためのガイドラインは、IFRS財団や経済産業省などによって公開されており、ステークホルダーとのコミュニケーションの醸成をサポートしています。ガイドラインを活用することで、ステークホルダーとの対話をより効果的に深めることができます。
定期的に改正・アップデートが行われている
統合報告書のガイドラインは、定期的に改正やアップデートが続けられています。例えば、従来は財務情報で測られていた企業価値がサステナビリティも意識され始めたように、企業価値の判断基準は時代によって変化します。こうした変化に統合報告書が対応できるように、ガイドラインは必要に応じて更新されるため、常に最新のものを参照することが大切です。
統合報告書のガイドラインの種類
統合報告書の発行などステークホルダーとの対話のためのガイドラインの例として、次の2種類があります。
- IFRS財団の“統合報告フレームワーク”
- 経済産業省の“価値協創ガイダンス”
IFRS財団の“統合報告フレームワーク”
IFRS財団が2021年に公開した統合報告フレームワークは、統合報告書作成の国際的な指針となっています。
これは、2013年にIIRC(国際統合報告評議会、現在はIFRS財団に統合)が公表した“国際統合報告フレームワーク”の改訂版(2021年発行)であり、例えばアウトプットとアウトカム(影響)の定義の明確化や、価値創造だけでなく価値の維持・毀損に関する記述の重要性などが強調されています。
統合報告フレームワークの目的は、統合報告書で求められる内容を記載し、その基礎となる概念を説明することにあります。特に、企業がいかにして短期・中期・長期にわたり価値を創造し、維持し、あるいは毀損するのか(価値創造能力)をステークホルダーが理解するための情報を特定し、その開示を促す点に特徴があります。
経済産業省の“価値協創ガイダンス”
経済産業省の価値協創ガイダンスは、厳密には統合報告書のためのガイドラインではありません。このガイダンスは、決算説明会や個別対話(1on1ミーティング)など、企業と投資家との間の建設的な対話を促進することを主眼として策定されました。しかし、価値創造のプロセスが分かりやすく説明されているなど、有益な情報が含まれています。そのため、統合報告書の作成にあたっては、前述した統合報告フレームワークと合わせて、価値協創ガイダンスを活用することが効果的です。なお、価値協創ガイダンスは2017年に初版が策定されましたが、サステナビリティを意識した企業価値創造の観点を盛り込んだ改訂版が、“価値協創ガイダンス2.0”として2022年に公開されました。
統合報告フレームワークの特徴
統合報告フレームワークは、次の3つの観点から統合報告書の検討を推奨している点に特徴があります。
- 統合思考(Integrated Thinking)
- 指導原則(Guiding Principles)
- 内容要素(Content Elements)
統合思考(Integrated Thinking)
統合報告フレームワークでは、統合報告書を作成する際に“統合思考”が重要であることを明示しています。統合報告書は、財務情報と非財務情報を統合させたものが理想ですが、そのためには組織内の事業・機能と資本の関係について、組織が能動的に考える必要があります。これが統合報告書の中核となる統合思考です。統合思考が組織内に浸透することで、従業員を含めた企業全体の行動が変化し、企業価値が向上すると考えられています。
指導原則(Guiding Principles)
統合報告フレームワークでは、統合報告書を作成する際の基礎となる指導原則を設定しており、以下の7つの項目があります。
| 戦略的焦点と将来志向 | 組織の戦略と長期的な価値創造能力、および資本の利用・影響について記載する |
| 情報の結合性 | 長期的な価値創造能力に影響する要因や関連性について明示する |
| ステークホルダーとの関係性 | 組織と主要なステークホルダーとの関係性、およびそのニーズへの対応について示す |
| 重要性(マテリアリティ) | 組織の価値創造能力に実質的な影響を与える要素に関する情報を提供する |
| 簡潔性 | 情報量ではなく“簡潔さ”を重視して作成する |
| 信頼性と完全性 | 重要な情報について、正と負のバランスを意識しながら正確に示す |
| 首尾一貫性と比較可能性 | 期間を超えて首尾一貫した情報であると同時に、ほかの組織と比較できるようにする |
内容要素(Content Elements)
統合報告フレームワークでは、統合報告書に含まれるべき情報を“内容要素”として定義しています。次の8つの内容要素は相互排他的なものではなく、相互に関連し合っていることを意識することが大切です。
| 組織概要と外部環境 | 組織が何を行うか、組織はどのような環境で事業を営むのか |
| ガバナンス | 組織のガバナンス構造は、組織の短期・中期・長期の価値創造能力をどのように支えるのか |
| ビジネスモデル | 組織のビジネスモデルはどういうものか |
| リスクと機会 | 組織の短期・中期・長期の価値創造能力に影響を及ぼす具体的なリスクと機会は何であり、組織はそれらに対しどのような取り組みを行っているか |
| 戦略と資源配分 | 組織はどこを目指し、どのようにそこに辿り着くのか |
| 実績 | 組織は当該期間における戦略目標をどの程度達成し、資本への影響に関するアウトカムは何であるか |
| 見通し | 組織が戦略を遂行するにあたり、どのような課題・不確実性に直面する可能性が高く、結果として生じるビジネスモデルや将来の実績への潜在的な影響はどのようなものか |
| 作成と表示の基礎 | 組織はどのように統合報告書に含む事象を決定し、それらの事象はどのように定量化または評価されるか |
また、上記の内容要素を一枚絵の価値創造プロセスとして、統合報告書のコンテンツとして分かりやすく示すこともあります。価値創造プロセスについて、次の記事も併せてご参照ください。
価値協創ガイダンスの特徴
前述のように、価値協創ガイダンスは厳密には統合報告書のガイドラインではありませんが、企業価値向上のための投資家との対話や自社の非財務情報の開示において、次の6つの要素が重要だとしています。そのため統合報告を作成する際も、これらのポイントを意識してみるといいでしょう。
- 価値観
- 長期戦略
- 実行戦略(中期経営戦略など)
- 成果(パフォーマンス)と重要な成果指標(KPI)
- ガバナンス
- 実質的な対話・エンゲージメント
価値観
“価値観”は、社会課題を解決するために企業・従業員が取るべき行動の判断軸となります。統合報告書を作成する際は、自社固有の価値観を明確化したうえで、持続的な価値創造プロセスにおいてどのような社会課題を解決していくかを検討することが大切です。価値観を定めることで、自社の存在価値を再認識し、価値創造プロセスを見直すきっかけとなり、さらに経営陣のみならず従業員との共通認識とすることで、全体的なエンゲージメントを高めることも可能です。
長期戦略
“長期戦略”では、先ほどの価値観に基づいて長期ビジョンを策定します。その際は、長期ビジョン、ビジネスモデル、リスクと機会の3つの要素を意識して、どのように社会に価値を提供して企業価値を向上させていくかを検討しましょう。これは、産業構造や事業環境などの変化に対応し、長期的・持続的な価値創造を実現するために重要な要素となります。
実行戦略(中期経営戦略など)
“実行戦略(中期経営戦略など)”は、先ほどの長期戦略を実現するための取り組みです。企業の経営資源・ステークホルダーとの関係を維持・強化することが目的です。自社の足下の財政・経営の状態や長期的なリスク・機会を分析し、長期戦略の具体化に向けた戦略を策定・実行することが求められます。長期戦略の策定時と外部環境が変化している場合は、方向性が正しいかどうか再検討することも大切です。また、自社を取り巻くさまざまなリスクに対応するために、サステナビリティも実行戦略に取り組んで対外的にアピールしましょう。
成果(パフォーマンス)と重要な成果指標(KPI)
“成果(パフォーマンス)と重要な成果指標(KPI)”は、自社の価値観を踏まえた長期戦略・実行戦略により、どの程度の価値を創出できたかを示す指標です。自社のビジョンやミッション、長期的な見通しについてどれだけ魅力的に語っても、結果を出さなければステークホルダーの信頼を得ることはできません。そのため、企業はKPIによる長期戦略の進捗・成果を評価し、今後に向けたブラッシュアップを行う必要があります。KPIの設定理由や価値観・重要課題とのつながり、戦略における位置づけなどについて、ステークホルダーに説明できることが望ましいです。
ガバナンス
“ガバナンス”は、長期戦略と実行戦略の策定・推進・検証を行い、企業価値を持続的に高めるために企業行動を規律する仕組みです。このガバナンスを実効的で持続可能なものにすることで企業の信頼性が高まり、ステークホルダーから投資が受けやすくなります。具体的には、経営陣が持つ役割分担を明確に公表して、その機能を実効的に果たしていくことが大切です。さらに、現在の企業体制を構築した理由や、それが長期戦略の実現や価値創造にどう寄与するかを説明できるのが理想的だとされています。
実質的な対話・エンゲージメント
“実質的な対話・エンゲージメント”は、企業の価値創造プロセスの全体像と構成要素について、企業とステークホルダーが双方向的な対話を行うことです。ステークホルダーからの支援は、企業にとって極めて影響力が強く、企業が成長しながら持続的な価値創造を実現するために欠かせません。これまで解説した5つの要素、すなわち“価値観”から“ガバナンス”までについてステークホルダーに適切な形で示すことで、相互に発展的な関係を構築できるようになるでしょう。
統合報告書のガイドラインを活用すべき理由

次のような理由から、企業が統合報告書を作成する際は、前述した“統合報告フレームワーク”や“価値協創ガイダンス”などのガイドラインを活用すべきだといえます。
- 必要な情報を網羅しやすくなる
- “統合思考”を実践しやすくなる
- ステークホルダーへの訴求力が高まる
必要な情報を網羅しやすくなる
統合報告書で求められる要素は多く、網羅できていなければ自社の未来志向的な価値をステークホルダーに適切に伝えることはできません。統合報告書のガイドラインを参照することで「どんな情報が必要か」「どんなマインドで作成すべきか」を知り、作成時の羅針盤となることでしょう。ただし、統合報告フレームワークの指導原則において“簡潔性”が示されているように、統合報告書を単に情報を並べるだけではなく、あくまで簡潔に分かりやすくまとめることが大切です。
“統合思考”を実践しやすくなる
統合報告書は、財務情報と非財務情報を統合させたものであるべきです。しかし、単に財務情報主体の“アニュアルレポート”と、非財務情報をまとめた“サステナビリティレポート”を足し合わせたようなものでは不十分です。
統合報告フレームワークでは、これを“Combined Report(結合した報告書)”と呼び“Integrated Report(統合した報告書)”と明確に区別しています。統合報告のガイドラインを参照することで、統合報告書の中核である“統合思考”への理解が深まるでしょう。
ステークホルダーへの訴求力が高まる
統合報告書の大きな目的のひとつが、投資家や株主などの財務資本提供者に代表されるステークホルダーとの対話を深めることです。その本質を理解せずに制作を進めると、形式だけ合わせた統合報告書になり、ステークホルダーに対する説得力・訴求力に乏しいものになってしまいます。投資家との建設的な対話を重視する価値協創ガイダンスの視点を取り入れることで、ステークホルダーの期待に応え、よりエンゲージメントを深めるための魅力的な統合報告書を作成することができるでしょう。
魅力的な統合報告書を作るために

せっかく統合報告書を制作しても、ステークホルダーの関心を惹くことができなければ意味がありません。魅力的な統合報告書を作るために、次のようなポイントも意識しましょう。
- 適切なボリュームを意識する
- ストーリーラインを表現する
- アウトカムにも言及する
- 外部業者を活用して第三者意見を取り入れる
適切なボリュームを意識する
統合報告書を作成する際は、適切なボリュームを意識しましょう。ESG/統合報告研究室の「統合報告書発行状況調査(2025年2月発行)」によると、統合報告書の総ページ数の分布は次のようになっています。
| 総ページ数 | 企業数 | 割合 |
| ~40 | 100 | 8.7% |
| 41~60 | 257 | 22.3% |
| 61~80 | 377 | 32.8% |
| 81〜100 | 231 | 20.1% |
| 101~ | 185 | 16.1% |
60ページを超える企業は69.0%であり、2023年の66.5%から2.5ポイント増加しています。人的資本を中心とするサステナビリティ情報開示の充実化を図ったことで、ページ数が増えたと推察されます。ただし、ページ数が増えると内容がまとまりづらく読者の負担も増えるため、基本的には60~80ページ前後にまとめるのが無難です。
ストーリーラインを表現する
統合報告書は、単に数値やデータを羅列すればいいものではありません。読まれる統合報告書を作るためには、全体の構成や流れ、つまりストーリーラインを意識する必要があります。開示した情報の背景にどのような価値観があり、どんな戦略で将来的に価値を生み出し、それを企業価値といかに連動させていくのか、一連のストーリーラインを描けるようにしましょう。こうした背景があって初めて、数値やデータが意味を持つようになります。
アウトカムにも言及する
アウトプットだけではなく、その結果としてもたらされる影響である“アウトカム(影響)”にも言及することが重要です。統合報告フレームワークでは、資本はインプットとして活用され、事業活動を通じて製品・サービス・副産物などの“アウトプット”に変換されます。その結果として生じるのが、資本の内部的および外部的影響である“アウトカム”です。統合報告書では、アウトカムについて正と負の両面について記載することが推奨されています。
外部業者を活用して第三者意見を取り入れる
これまで解説したように、統合報告書の作成にはさまざまな事前知識が必要です。さらに、自社に関する膨大な情報を整理し、ステークホルダーに分かりやすく伝える必要があるため、自社リソースだけで行うことが難しいケースは少なくありません。そこで、外部業者を活用して第三者意見を取り入れることで、より客観的で質の高い統合報告書を作成できるようになるでしょう。専門知識と経験が豊富な専門家のコンサルティングを受けることで、自社の価値を最大限にアピールできる統合報告書を作成できます。
統合報告書に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書には明確なフォーマットは定められていませんが、今回ご紹介した“統合報告フレームワーク”や“価値協創ガイダンス”を参考にすることで、自社の企業価値を訴求できる統合報告書を制作しやすくなるでしょう。しかし、統合報告書の制作には専門的な知識やノウハウが必要になるため、自社リソースだけでは対応できないケースが少なくありません。
そこで統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。