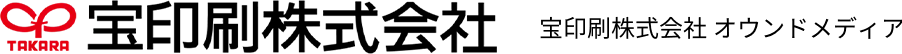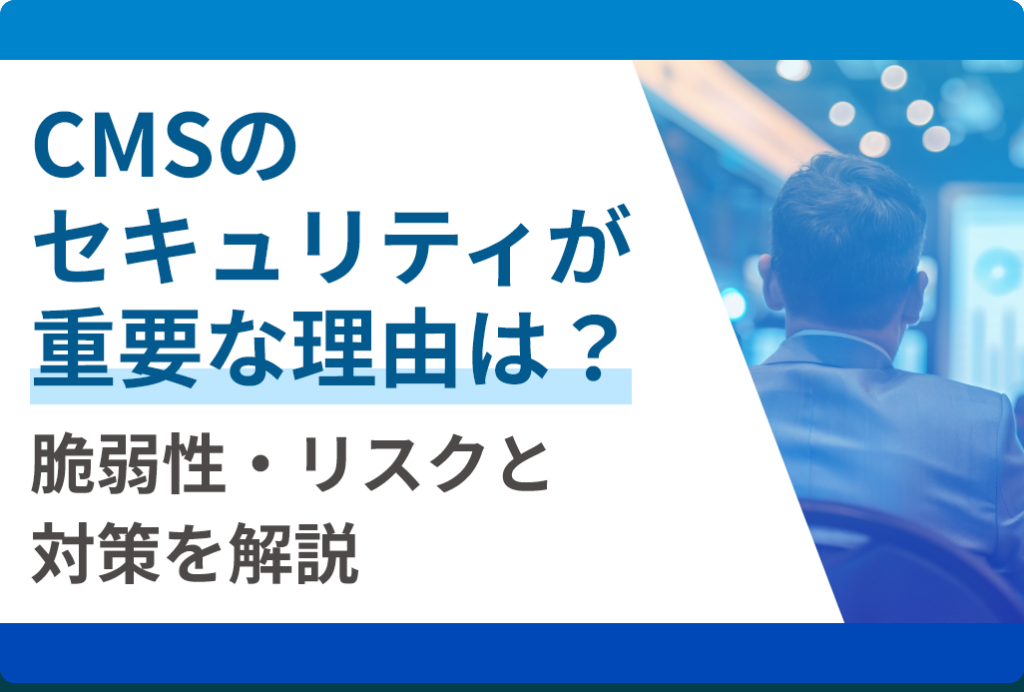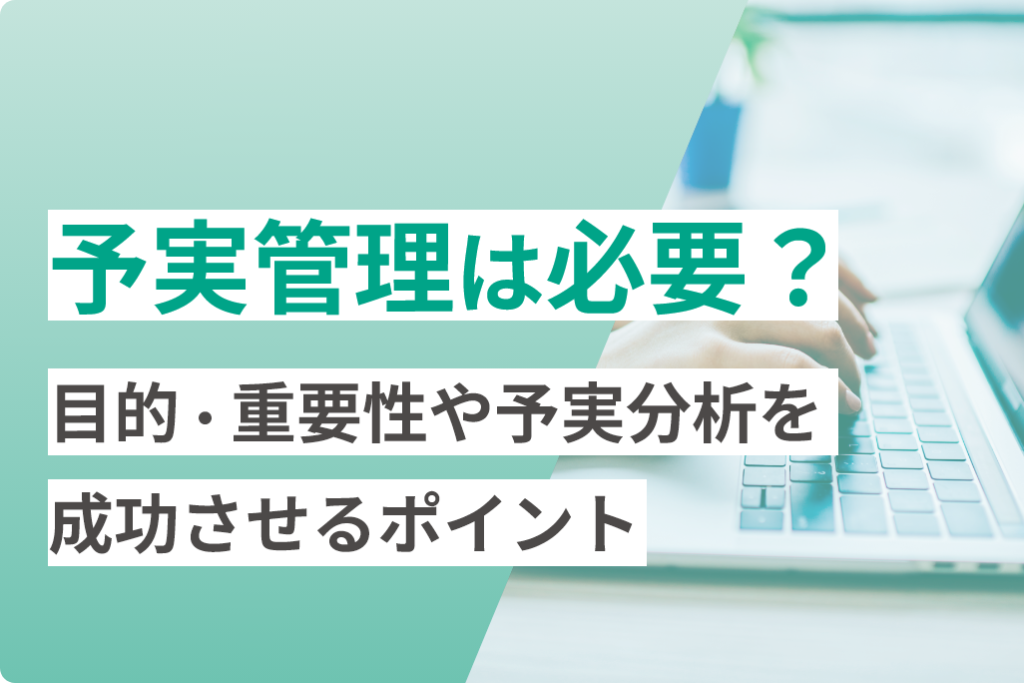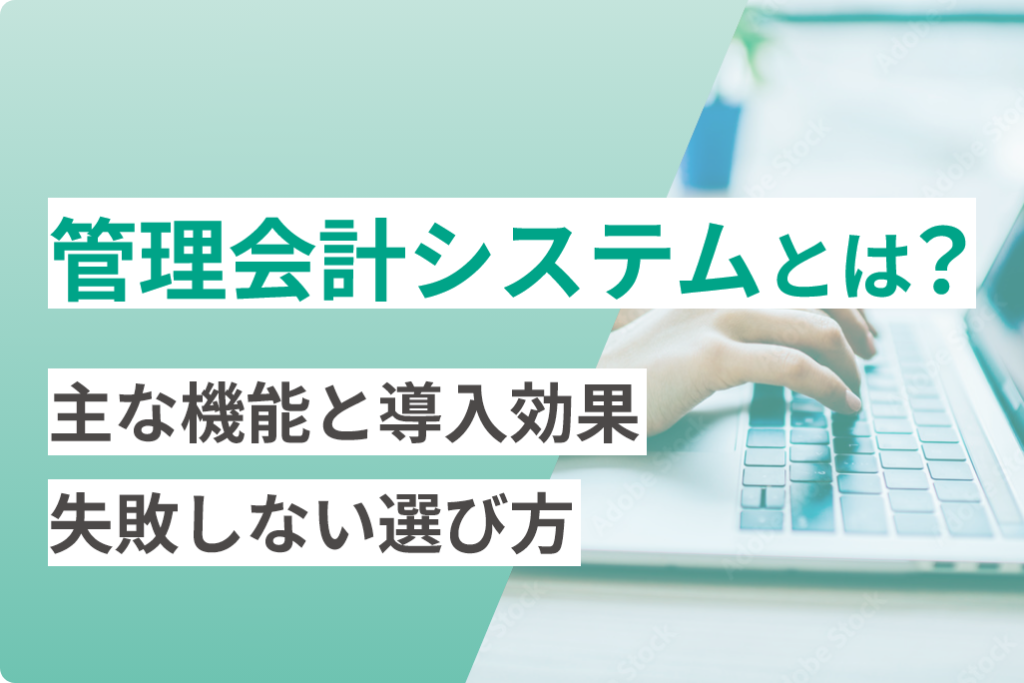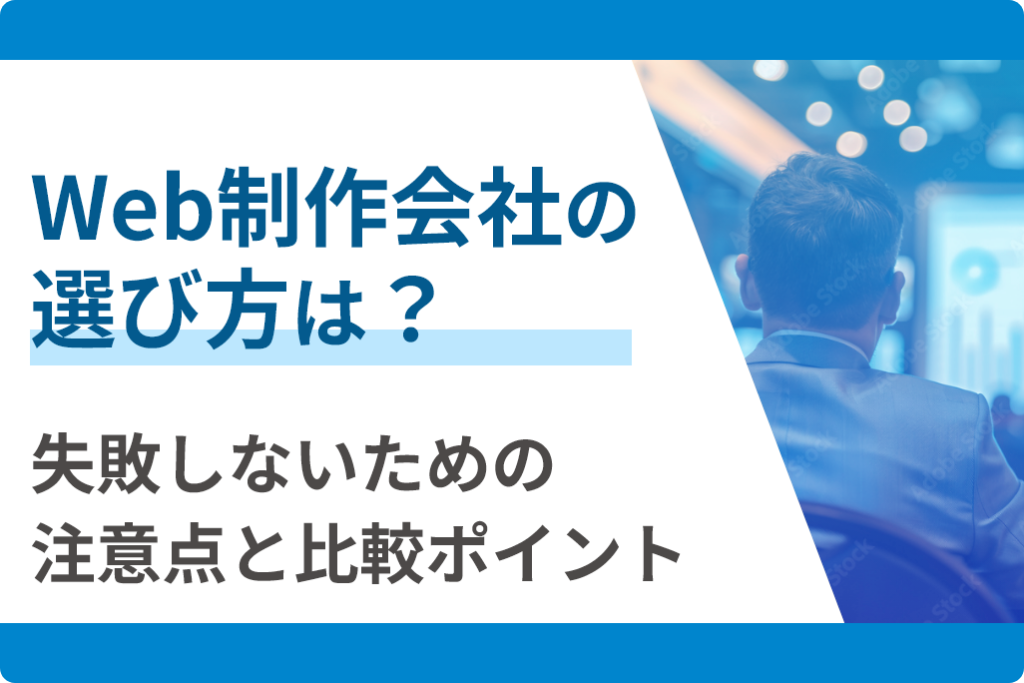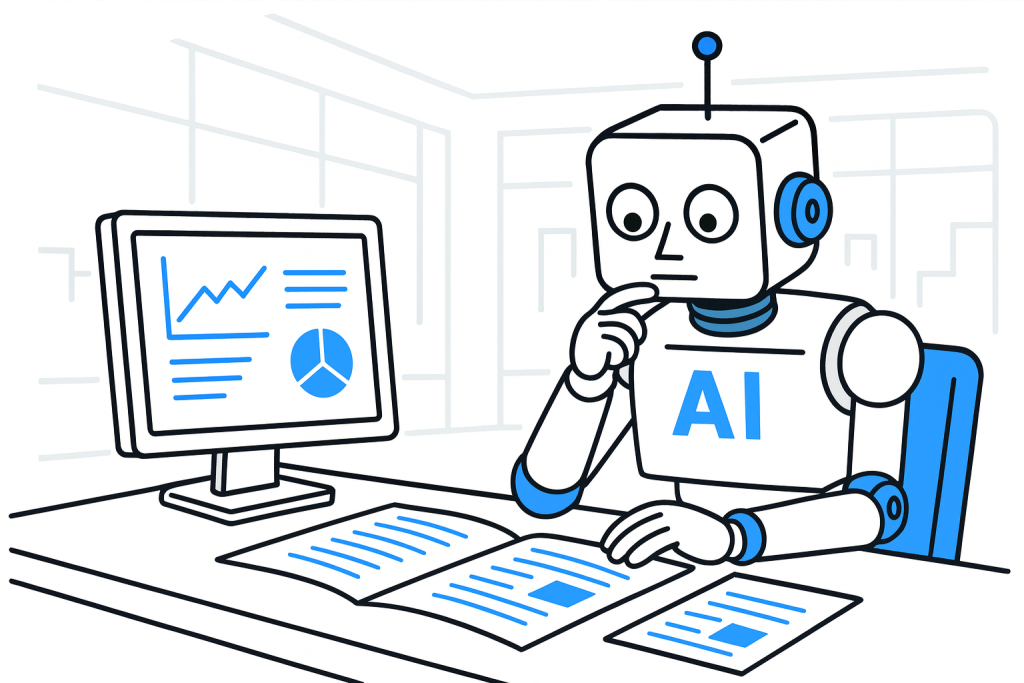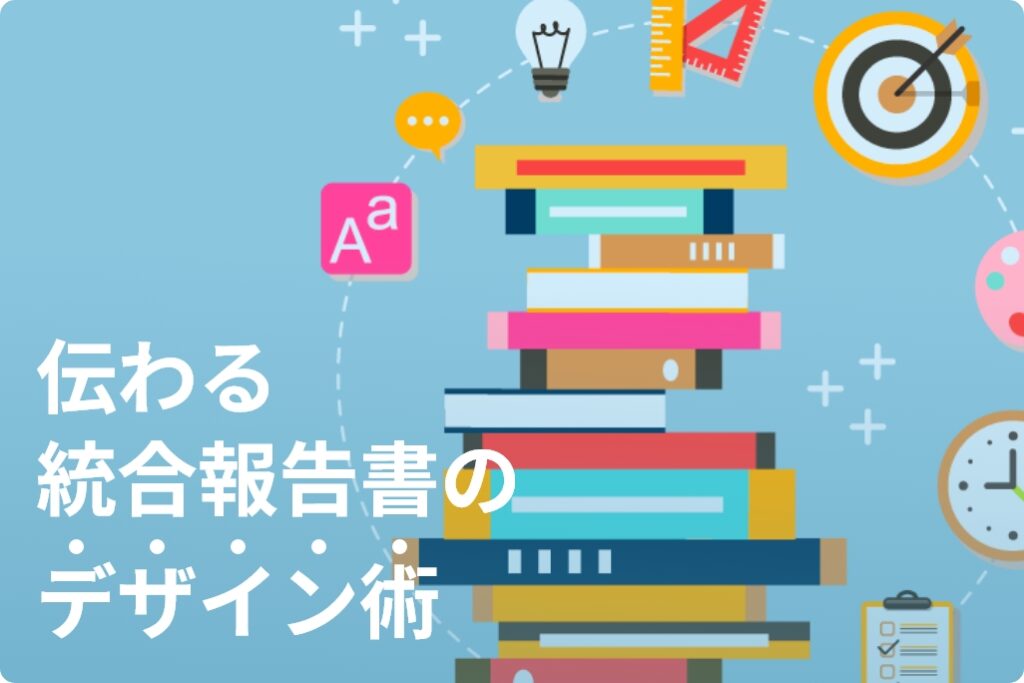サステナビリティに対する関心の高まりなどを背景に、統合報告書を制作・公開する企業が増えています。しかし、統合報告書の制作では多岐にわたる情報や専門的な知見が必要になり、十分な理解がないまま進めることで「制作方法が分からない」「制作しても十分な効果がない」といった課題に直面する場合もあります。
そこで本記事では、統合報告書の制作方法や制作するうえで意識したいポイントを解説します。
統合報告書とは
まずはじめに統合報告書の概要を次のポイントから見ていきます。
- 財務情報・非財務情報を統合させた媒体
- 有価証券報告書やアニュアルレポートとの違い
- 制作時に参照すべき2種類のガイドラインがある
財務情報・非財務情報を統合させた媒体
統合報告書とは、企業の売上や資産などの財務情報と、ESG(環境・社会・ガバナンス)やCSR(企業の社会的責任)に代表される非財務情報を統合した媒体のことです。統合報告書は、短期的な業績や収益だけではなく、企業の中長期的な価値の創造力を伝えることが求められます。そのため、財務情報と非財務情報をただ併記するのではなく、統合思考に基づいて財務情報と非財務情報を企業価値に関連付け、中長期の企業ストーリーを説明することが大切です。
なお、2025年時点では統合報告書の制作・開示は義務化されていませんが、統合報告書発行状況調査2024によると、2024年1月~12月末時点の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加しています。
アニュアルレポートや有価証券報告書との違い
“アニュアルレポート”は年次報告書のことであり、企業の財務情報を投資家や金融機関などのステークホルダーに開示します。また“有価証券報告書”は企業の財務情報を示し、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書など、財務諸表と注記などに絞り込んでまとめます。有価証券報告書に関しては、金融商品取引法第24条有価証券報告書の提出により、上場企業と一部の非上場企業に提出が義務付けられています。これらの報告書と統合報告書との違いについては、下記の記事にまとめていますので併せてご参照ください。
※関連記事
統合報告書とアニュアルレポートの違いを徹底比較|目的・内容・活用法をわかりやすく解説
統合報告書と有価証券報告書の違いを徹底比較|企業が押さえるべき実務ポイントと活用法
制作時に参照したい2種類のガイドライン
統合報告書は記載項目やフォーマットなどが定められておらず自由演技の報告書となっています。だからこそ、制作の指針が定まりにくいケースもありますが、制作時の参考になるものとして、IFRS財団統合報告フレームワークと経済産業省の価値協創ガイダンス2.0といったガイドラインがあります。それぞれの特徴や活用するコツについては、次の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。
統合報告書のガイドラインとは?フレームワークの概要や目的を解説
統合報告書を制作する目的・重要なポイント
統合報告書を制作する目的・重要なポイントとして、次のようなものが挙げられます。
- 投資家などの財務資本提供者に企業価値向上ストーリーを説明する
- 自社の価値をステークホルダーへ周知する
- 資本市場に自社の情報を提供する
投資家などの財務資本提供者に企業価値向上ストーリーを説明する
統合報告書の主な目的は、投資家などの財務資本提供者に対して、自社の中長期的な“企業価値向上ストーリー”を伝えることです。自社がどのような思想とビジョンを持ち、何を目指してビジネスを営み、どんな価値を生み出せる存在になろうとしているのか、そのストーリーを将来志向で表現するのが統合報告書です。言い換えれば、単に数値や情報を羅列しただけのものは、統合報告書としては十分ではないということです。
自社の価値をステークホルダーへ周知する
前述した“企業価値向上ストーリー”は、いわば自社が長期的に生み出せるであろう価値について、これまでの歴史で培われてきた価値観やビジョン、具体的に得た成果と関連付けて説明することです。これにより、財務価値・非財務価値の双方について、中長期的な価値創出といった将来志向の観点からステークホルダーへ情報を発信できます。
資本市場に自社の情報を提供する
投資家などの財務資本提供者はその企業について限られた情報しか知らないため、資本市場と企業では保有している情報が非対称になります。近年では、サステナビリティに関する企業の取り組みを企業評価に反映する投資家が増えているため、統合報告書でサステナビリティに関する自社の取り組みを開示することが大切です。これにより、資本市場と企業の間の情報の非対称性を解消し、資本市場における良い評価へとつなげることができるでしょう。
統合報告書の効果的な制作ステップ

続いて、効果的な統合報告書の制作手順・作り方について、7つのステップに分けて解説します。
- 制作目的や対象読者を想定する
- 制作時期とコストを明確化する
- 競合他社の統合報告書を集める
- 統合報告書の全体像を検討する
- 統合報告書の制作体制を構築する
- 統合報告書の制作と公開を行う
- 社内外の反響を集めて次年度の検討を行う
ステップ1:制作目的や対象読者を想定する
統合報告書をなぜ制作・公開するか、まずはその目的を検討しましょう。これはステークホルダーに対して「どのような行動変容を促したいか」と考えることにつながります。例えば、機関投資家を対象として財務資本の提供を呼び込みたいのであれば、環境・社会・企業統治という3つの観点から自社の姿勢をアピールすることが有効になるでしょう。
ステップ2:制作時期とコストを明確化する
宝印刷D&IR研究所の研究員コラムその統合報告書、本当に必要ですか?によると、統合報告書は決算終了後から6か月前後で発行される傾向にあります。3月決算の企業が多い日本においては、秋口が統合報告書の発行シーズンとなっています。統合報告書を制作するためには人員やコストがかかるため、時期から逆算して、事前に想定しておくことが重要です。社内リソースで対応する場合の担当者にかかる負荷、外部の事業者に依頼する場合の外注費などについて検討しておきましょう。
ステップ3:競合他社の統合報告書を集める
統合報告書は、大量の情報を網羅すればいいというものではありません。適切な情報量のレポートを制作するためには、同じ業種の競合他社の統合報告書を集めて、ベンチマークとすることが効果的です。これにより情報過多や記載内容のブレを防ぎ、ステークホルダーにとっても読みやすい統合報告書を作ることができるでしょう。
ステップ4:統合報告書の全体像を検討する
統合報告書の骨組みとなる全体像とコンセプトを検討します。その年の統合報告書で何をステークホルダーに伝えたいかを議論したうえで、こちらの記事で解説している「統合報告書に含めるべき8つの項目」や、経済産業省が公開している価値協創ガイダンス2.0を参考にして、必要とされる情報について理解しておきましょう。また自社らしさや強みをアピールするために、経営層・事業責任者・現場トップなどの意見も盛り込むことが大切です。上層部のメッセージは、統合報告書の主要コンテンツにもなるため、全社を巻き込んで取り組む姿勢が必要です。
ステップ5:統合報告書の制作体制を構築する
統合報告書のコンテンツ制作のために、どの部署が主体となり、誰が社内をコントロールしていくのかといった制作体制を計画しましょう。統合報告書の制作には、社内の幅広い部門との連携・調整が必要なため、担当者の選任や運用ルールの策定なども必要になります。また、統合報告書を制作するとその後も毎年公表し続けることも期待されるため、安定した制作体制の構築を心がけましょう。
ステップ6:統合報告書の制作と公開を行う
以上のステップが完了したら、実際に統合報告書を制作しましょう。制作中の段階でも経営層とのディスカッションを緊密に行い、フィードバックを反映することが大切です。統合報告書の完成後は、自社サイトで公開するだけではなく、プレスリリースも活用することで、より幅広いステークホルダーへ情報を届けることができます。
ステップ7:社内外の反響を集めて次年度の検討を行う
統合報告書を毎年制作・公開し続けていくとなると、段階的に「よりよいものを作る」という姿勢が求めらることでしょう。そのためには統合報告書の完成後は社内外で積極的に配布して、フィードバックを集め、良い点と改善点を把握することが大切です。制作チームで反省会を実施し、次年度のコンセプトや編集方針に反映させましょう。ブラッシュアップを重ねることで、自社の企業価値がよりステークホルダーに伝わり、評価されることにつながります。
統合報告書の制作に欠かせないマインド

統合報告書の制作に取りかかるときは、次のようなマインドを持つことを意識しましょう。
- ステークホルダーとのコミュニケーションを重視する
- 経営戦略との一貫性を保つ
- 客観的な指標を用いる
- 長期的視点を持つ
ステークホルダーとのコミュニケーションを重視する
統合報告書は、ステークホルダーとのコミュニケーションを意識して、コンテンツを制作することが大切です。統合報告書の主な想定読者は、投資家や株主などの財務資本提供者です。そのため、価値創造につながるストーリーやエビデンスを適切に開示して伝えなければ、ステークホルダーの納得を得るのは難しくなるかもしれません。また一方で、IFRS財団統合報告フレームワークでも示されているように、統合報告書の情報は財務資本提供者以外のステークホルダーにも役立つものです。自社が想定する読者層がどんな情報を求めているか、優先順位を付けたうえで意識して統合報告書を制作するようにしましょう。
経営戦略との一貫性を保つ
企業のビジョン・ミッションや長期的な価値創造プロセスが、統合報告書全体で矛盾なく示されることも重要です。この観点が欠けると、統合報告書の信頼性が失われて、自社に対するステークホルダーの評価も低下してしまいます。例えば「環境に優しい製品開発が経営戦略の柱」と記載しているにも関わらず、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量などのデータが示されていない場合は、信頼できる統合報告書とは言えないかもしれません。
客観的な指標を用いる
統合報告書の透明性・信頼性を高めるためには、客観的な指標の活用も重要です。そのため、定性的・定量的な情報を具体的に示す指標を設定し、取り組み内容と成果を数値として可視化しましょう。特に非財務情報は定性的な概念が多いため、投資家が評価しやすい合理的なエビデンスを示すことが求められます。例えば、単にダイバーシティを推進しているというのではなく、女性管理職や外国籍従業員の比率の推移を記載することで信頼性が高まります。
長期的視点を持つ
統合報告書は、将来志向の企業価値向上ストーリーを描くものなので、長期的な視点が欠かせません。現状の財務情報・非財務情報を羅列するだけでは、統合報告書の意味がなくなります。企業の将来的な方向性や目標を明確に示すことで、ステークホルダーの理解と信頼が得やすくなります。
統合報告書の制作を成功に導くためのポイント
統合報告書の制作に成功するためには、次のようなポイントを意識することが大切です。
- 最初から完璧を目指さない
- 社内の協力を得る
- 外部の力をうまく活用する
最初から完璧を目指さない
統合報告書の制作は高いレベルの内容が求められるため、最初から上手くいくとは限りません。どのような企業であっても、初期の統合報告書にはさまざまな課題があり、ステップを踏んでブラッシュアップを続けています。最初から完璧を目指そうとすると、制作が間に合わなくなったり、躊躇して進行できなくなったりしてしまう場合もあるので、注意しましょう。
社内の協力を得る
統合報告書を制作するうえで「自社の価値とは何か」「自社は何を目指すのか」といった企業全体としての指針を示すことが求められます。そのためには全社一丸で取組み、情報を共有する必要があります。ひとつの部署で制作するのではなく、関係部署の情報を得るために社内啓蒙に励んで、統合報告書を制作するための協力体制を築くことが大切です。
外部の力をうまく活用する
統合報告書の制作は、多岐にわたる情報を整理して分かりやすく伝える必要があるため、自社リソースだけで行うことは難しいケースがあります。無理して社内リソースで対応しようとすると、担当者の業務負担が増したり、客観性に乏しい内容になったりしてしまいます。一方で、外部事業者に統合報告書の制作を丸投げしたとしても、自社ビジネスに関する理解が浅いことなどにより、うまくいかないケースもあります。そのため自社の実情に合った外部パートナーを選び、上手く活用していくことが大切です。
“読まれる統合報告書”制作のポイント

せっかく統合報告書を制作しても、それがステークホルダーに読まれなければ意味がありません。そこで読まれる統合報告書を制作するために、次のようなポイントも意識しましょう。
- 適切なボリュームを意識する
- ストーリーラインとデザインを意識する
- 投資家の視点を取り入れる
- アウトカムを明確に開示する
適切なボリュームを意識する
統合報告書の制作にあたり適切なページ数を検討想定しましょう。なお株式会社宝印刷D&IR研究所 ESG/統合報告研究室の統合報告書発行状況調査(2025年2月発行)によると、統合報告書の総ページ数の分布は次のようになっています。
| 総ページ数 | 企業数 | 割合 |
| 〜40 | 99 | 8.7% |
| 41〜60 | 257 | 22.3% |
| 61〜80 | 377 | 32.8% |
| 81〜100 | 231 | 20.1% |
| 101〜 | 186 | 16.1% |
60ページを超える企業は69.0%であり、2023年の66.5%から2.5ポイント増加しました。人的資本を中心とするサステナビリティ情報開示の充実化を図ったためと推察されます。このようなデータやと入れたい内容などを考慮して、適切なボリュームを想定しましょう。
ストーリーラインとデザインを意識する
統合報告書は、企業理念や企業価値向上ストーリーを伝えるために制作することが大切です。単なる情報の羅列になってしまわないようにするために、自社の経営ビジョン・ミッション・戦略の実効性をストーリー形式で分かりやすく示す必要があります。自社の取り組みや成功事例を明示すると共に、伝わりやすいデザインを意識して統合報告書を制作しましょう。
投資家の視点を取り入れる
統合報告書は基本的に“財務資本提供者”を対象として制作・開示するものなので、投資家が必要とする情報を記載することが大切です。前述したように、経営戦略との一貫性を保ちながら客観的な指標を示すことで、投資家が必要とする情報を効果的に提供しましょう。
アウトカムを明確に開示する
アウトプットだけではなく、その結果としてもたらされる影響である“アウトカム(影響)”を明示することが重要です。アウトプットとアウトカムは混同してしまいやすいので注意が必要です。IFRS財団統合報告フレームワークでは、資本はインプットとして活用され、事業活動を通じて製品・サービス・副産物などの“アウトプット”に変換されます。さらにその結果として生じるのが、資本の内部的および外部的“アウトカム”です。
統合報告書を制作する手法
統合報告書を制作するリソースとして、大きくわけて社内と社外の2つが考えられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的や状況に合わせたものを選ぶことが大切です。
- 社内リソースで制作する
- 外部業者を活用して第三者意見を取り入れる
社内リソースで制作する
社内リソースで統合報告書を制作する場合は、自社について深く理解している社内担当者が携わることで、自社ならではの魅力を反映させやすくなります。理想的な統合報告書は、自社の価値や強みをステークホルダーにしっかり伝えることができるもの、社内リソースを活用できれば大きなメリットとなるでしょう。ただし、統合報告書で必要とされる情報を整理して分かりやすくまとめるためには、知見のあるメンバーを起用した専門チームが必要になるかもしれません。その場合はリソースの圧迫につながることに注意が必要です。
外部業者を活用して第三者意見を取り入れる
統合報告書の制作には、専門知識が欠かせません。そこで外部業者を活用して第三者意見を取り入れることで、より客観的で良質な統合報告書を制作できるようになります。ただし、専門性・経験・コンプライアンスに関する知識などに加えて、ビジネスへの理解度も重要となるため、自社に合う外部業者・コンサルティングを選定しましょう。
統合報告書の制作に関するご相談は宝印刷へ!

統合報告書を制作するときは、目的・読者・制作期間・コストなどを検討したうえで、コンセプトの決定と制作体制の構築を行うことが大切です。統合報告書は最初から完璧なものが作れるわけではないため、公開後は社内外の反響を集めて改善点を洗い出し、ブラッシュアップを重ねるようにしましょう。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。