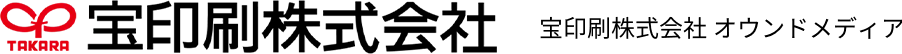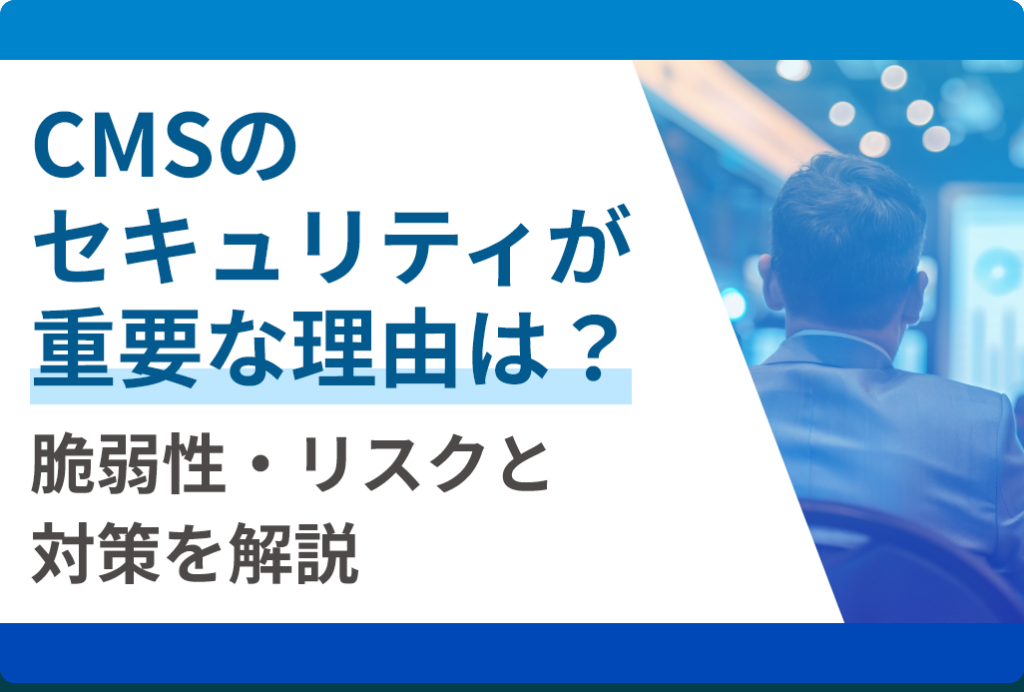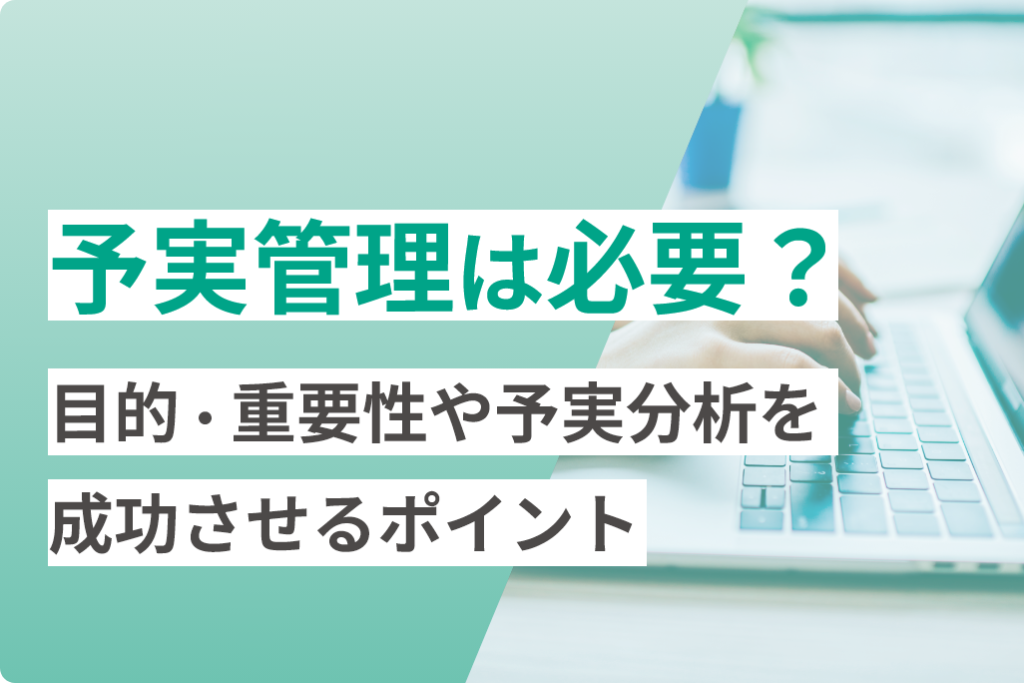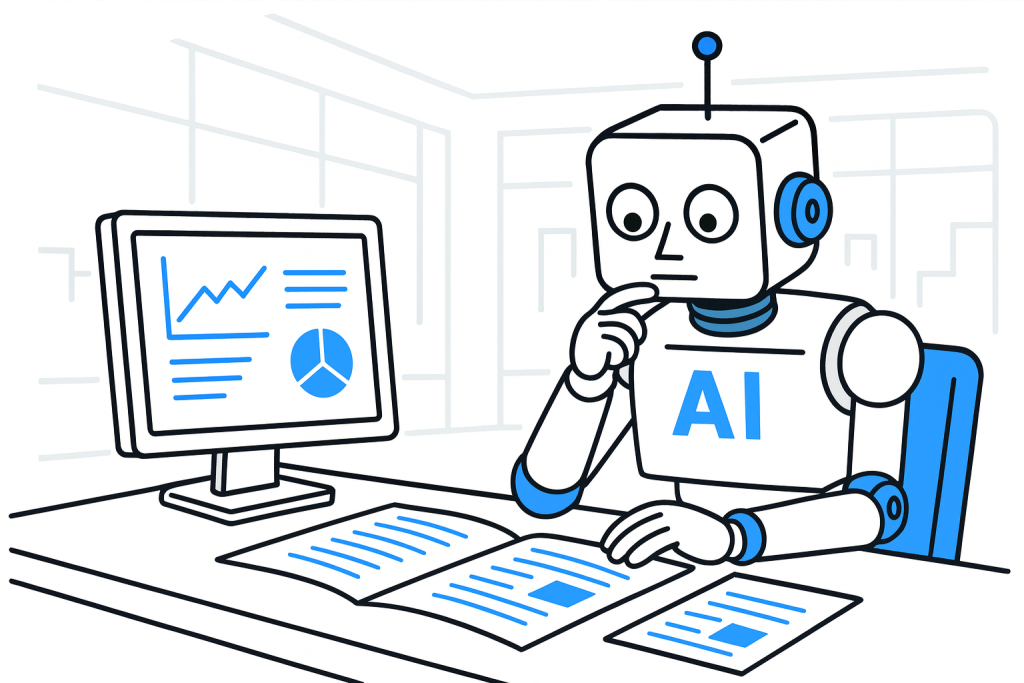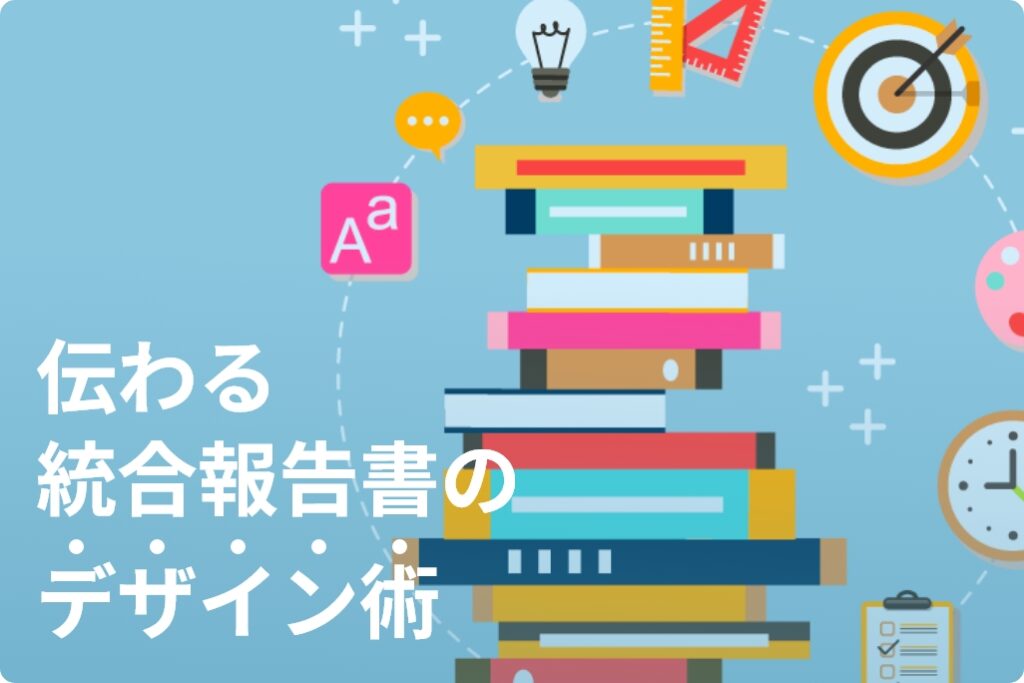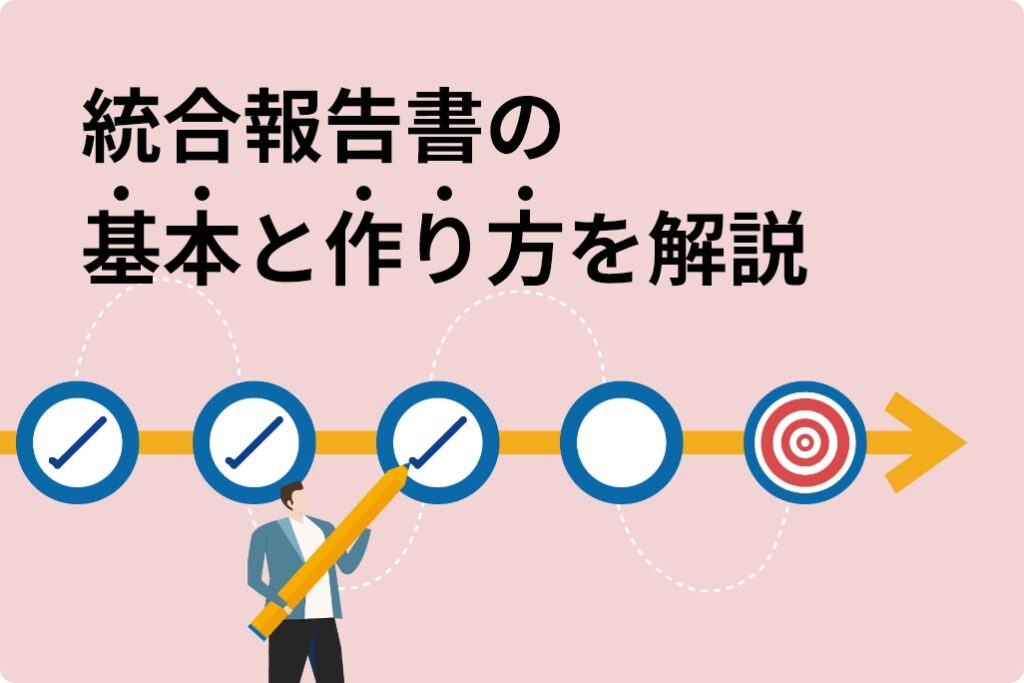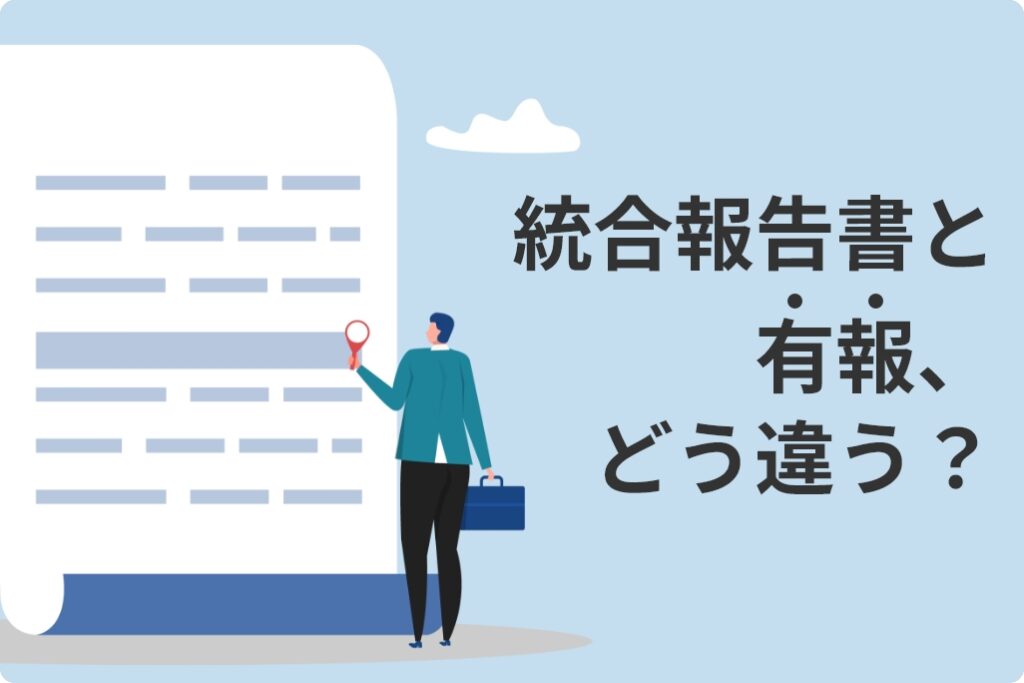統合報告書には明確なフォーマットやルールが存在しないため、各社がそれぞれの目的やブランドイメージに合う形式で作成しています。
しかし、どのような統合報告書においても特に重要性が高く、ステークホルダーが注目する要素のひとつが“価値創造プロセス”です。価値創造プロセスは、企業の将来志向での企業価値向上ストーリーを表現するものですが、具体的に分からない点もあると思います。そこで本記事では、統合報告書で重要な価値創造プロセスについてご説明します。
統合報告書の“価値創造プロセス“とは
統合報告書の“価値創造プロセス”について、次のポイントから解説します。
- 企業の中長期的な企業価値向上ストーリーを示す一枚絵
- 経済的価値の創出や社会的・環境的な影響を可視化する
企業の中長期的な企業価値向上ストーリーを示す一枚絵
統合報告書の“価値創造プロセス”とは、企業が中長期的な価値を生み出す過程を示すもので、価値創造ストーリーとも呼ばれています。もともとはIFRS財団の統合報告フレームワークで、統合報告書に記載すべきとされている内容要素を一枚絵に落とし込んだもので、組織概要と外部環境、ガバナンス、ビジネスモデル、リスクと機会、戦略と資源配分、実績、見通し、作成と表示の基礎の8つの内容要素からなります。統合報告書は、自社の企業価値を将来志向でステークホルダーに示すため、価値創造プロセスは、統合報告書の中核をなす概念図といえるでしょう。
経済的価値の創出や社会的・環境的な影響を可視化する
企業は財務資本・人的資本・知的資本など、さまざまな資本を活用してビジネスを行っています。統合報告書の価値創造プロセスでは、いかにこれらの資本を組み合わせて経済的価値を創出し、社会的・環境的な影響を与えるかを可視化します。図表や画像を活用し、ステークホルダーにストーリー性をもって分かりやすく説明することが可能です。
統合報告書で価値創造プロセスを示すメリット

統合報告書で価値創造プロセスを示すことで、企業にとって次のようなメリットがあると考えられます。
- 自社が生み出す価値を時間軸で伝えることができる
- 自社の取り組みに独自性を演出できる
- 自社が向かうべきベクトルを再認識できる
自社が生み出す価値を時間軸で伝えることができる
自社の情報を単に羅列するだけでは、時間軸や背景、項目ごとの関連性などを正確にイメージすることは困難です。価値創造プロセスとして図式化することで、過去・現在・未来という時間軸における企業のパーパスや戦略などを、ストーリー性を持たせて表現できるようになります。その結果、企業のビジネスがどのように成り立っており、将来的にどんな価値を生み出すかを伝えることができます。
自社の取り組みに独自性を演出できる
各企業のビジョンや戦略、サステナビリティへの取り組みなどは、似通った部分も多く、ステークホルダーにとっては、他社と何が違うのかと伝わりにくい場合もあります。前述したように、価値創造プロセスでは時間軸や背景なども示すため、そこに独自性が生まれやすくなります。似たような取り組みであっても、それを選択した経緯や理念は企業ごとに異なり、そのプロセスをステークホルダーに訴求できるのが価値創造プロセスなのです。
自社が向かうべきベクトルを再認識できる
価値創造プロセスを作成する際は、自社のさまざまな情報について時間軸・背景をもとに組み立てるため、それらを整理する必要があります。例えば、過去から現在に至るまでの流れでは、自社の歴史や現在のビジネス・資本などが該当します。現在から将来に至るプロセスでは、具体的な成長戦略・パーパスや資本の変化などが焦点となるでしょう。こうしたストーリーを作成する過程で、「自社は何のために存在しているのか」を見直し、再検討することで、向かうべきベクトルを改めて認識することにもつながります。
統合報告書の価値創造プロセスを作成するポイント

統合報告書の価値創造プロセスを作成する際は、次のポイントを意識しましょう。
- 自社の資本を言語化する
- メガトレンドを把握する
- ビジネスモデルを定義する
- サステナビリティの論点を設定する
- アウトカムを記載する
自社の資本を言語化する
企業の資本は財務資本と非財務資本に大別され、さらに非財務資本は、人的資本、知的資本、製造資本、社会・関係資本、自然資本の5種類に分かれます。これら6つの資本について整理して、自社の強みとして簡潔に言語化しましょう。近年では、非財務資本が企業の競争力・価値創出の重要な要素と考えられているため、その内容や活用状況をインプットとして具体的に、可能であれば定量的に記載することが重要です。
メガトレンドを把握する
メガトレンドとは、政治・経済・社会などに重大な影響を与えるような出来事や潮流を意味する言葉です。具体的には、気候変動や人口動態、テクノロジーや武力衝突といったものが当てはまります。中長期的な企業価値を創造するためには、目先の数値目標の達成だけではなく、自社を取り巻く外部環境を把握することが不可欠です。メガトレンドを把握することは、企業価値を創出するための前提であり、考慮したうえで価値創造プロセスに反映させることが重要です。
ビジネスモデルを定義する
自社の強みとして言語化した資本をインプットとし、活用して事業活動を通じてどのようなアウトプット(製品・サービスなど)を生み出すのか、そしてそれが最終的にどのようなアウトカム(社会・環境・ステークホルダーへの影響)につながるのかを定義することも大切です。さらに自社の強みや競争優位性、もしくはビジョンや目指す姿を価値創造プロセスの記載要素とすることで、ステークホルダーに対してよりわかりやすく訴求することができます。
サステナビリティの論点を設定する
サステナビリティの項目を価値創造プロセスと関連付けて、自社が社会・環境にどのような価値を提供できるのか、またどのような影響を受けるのかを社内で話し合い、定義しましょう。例えば、コーポレート・ガバナンスは直接の利益獲得に結び付かないかもしれませんが、企業の価値創造能力を支える経営基盤となります。自社が環境や社会にどのような価値を提供できるのか、また影響を受けるのかを議論し、ガバナンスの面から記載することも大切です。
アウトカムを記載する
“アウトプット”と“アウトカム”は混同されやすい概念です。IFRS財団の統合報告フレームワークによると、“アウトプット”は企業の製品・サービスそのものを指し、“アウトカム”は企業の事業活動が資本やステークホルダーに与える正負の影響を意味します。内部的なアウトカムとしては、従業員のモラルや組織の評判、収益・キャッシュフローなど、外部的なアウトカムとしては、顧客満足度やブランドロイヤリティ、社会・環境への影響などが該当します。また、アウトカムは正と負の両面を記載することも重要です。
価値創造プロセスを実現するために

統合報告書で提示する価値創造プロセスは、単なる理想であってはいけません。実現しなければ、絵に描いた餅となり、ステークホルダーの信頼を失ってしまうことになりかねません。だからこそ、次のようなポイントを意識して統合報告書の価値創造プロセスを作成することが大切です。
- 経営陣の想いを込める
- マテリアリティを明確化する
- 価値創造プロセスを従業員に浸透させる
- 常にブラッシュアップを重ねる
経営陣の想いを込める
多くの統合報告書では、企業のトップや経営陣のメッセージが記載されています。自社の価値創造ストーリーへの想いを、経営陣自身の言葉で雄弁に語ることで、実現に向けた熱意や重みが伝わりやすくなります。
マテリアリティを明確化する
価値創造プロセスを実現性のあるものにするためにはマテリアリティ、つまり企業が取り組むべき重要課題や領域を明確にすることが大切です。サステナビリティの取り組みを進める際は、リスクと機会の両側面からアプローチする必要があり、それに対応するための打ち手の議論が欠かせません。マテリアリティを特定することで、成長機会の拡大やリスク軽減につながるでしょう。
価値創造プロセスを従業員に浸透させる
統合報告書の価値創造プロセスを実現するためには、従業員にも共通認識として浸透している必要があります。経営陣だけが理解していても、従業員が動かなければ価値創造への道のりは険しいでしょう。従業員が価値創造に向けたストーリーを理解して共感することで、現場の意識改革につながり、組織全体のパフォーマンスが高まるのです。
常にブラッシュアップを重ねる
価値創造プロセスは、統合報告書の膨大な情報をまとめる必要があり、最初から完璧なものが作れるとは限りません。そのため、統合報告書の制作後は社内外で積極的に配布して、制作チームで成果を検討し、改善点を次年度の制作方針に反映させることが大切です。経営や事業を取り巻く環境の変化を把握したうえでステークホルダーとの対話を重ね、自社のパーパス・戦略の見直しも含めて価値創造プロセスをブラッシュアップしていきましょう。
統合報告書の価値創造プロセス事例
ここでは、統合報告書の価値創造プロセスについてTAKARA & COMPANYの事例を参考にご説明します。

冒頭で解説したように、統合報告書の価値創造プロセスは、統合報告書の中核をなす概念図であるため、読者が直感的に理解できるようにまとめることが重要です。
本事例では、まず企業活動に欠かせない6つの資本、すなわち、人的資本、知的資本、社会・関係資本、製造資本、財務資本、自然資本について簡潔にまとめたうえで、それを投入して実行される中期経営計画を提示しています。その結果として、ページ右側に自社・ステークホルダーおよび社会に提供できる価値を具体的に提示しています。SDGs17の目標と関連づけることで、将来的に創造しようとしている価値について、読者の理解やイメージを深めている点もポイントです。
また、統合報告書のサマリーである価値創造プロセスでは、可能な限りシンプルな一枚絵を提示する必要があります。ただし、リスクと機会、マテリアリティ、ガバナンスなど簡潔な表現が困難な部分については、本事例のように他ページへの導線を設けて詳細な解説を委ねましょう。
本事例の価値創造プロセスは、決して複雑な構成ではなく、あくまでシンプルにまとめています。デザイン性や見た目のインパクトを意識することは大切ですが、読者の理解をサポートできるような構成を最優先させることで読まれる統合報告書を目指しています。
統合報告書に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書で価値創造プロセスを示すことで、自社がこれから生み出す価値を時間軸で表現できるようになり、投資家への訴求力が増します。ただし、価値創造プロセスが絵空事にならないように、価値創造プロセスを従業員に浸透させる取り組みや、ブラッシュアップを重ねる意識が重要です。
自社リソースのみで統合報告書を制作することが難しい場合は、統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所」を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。