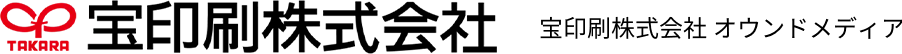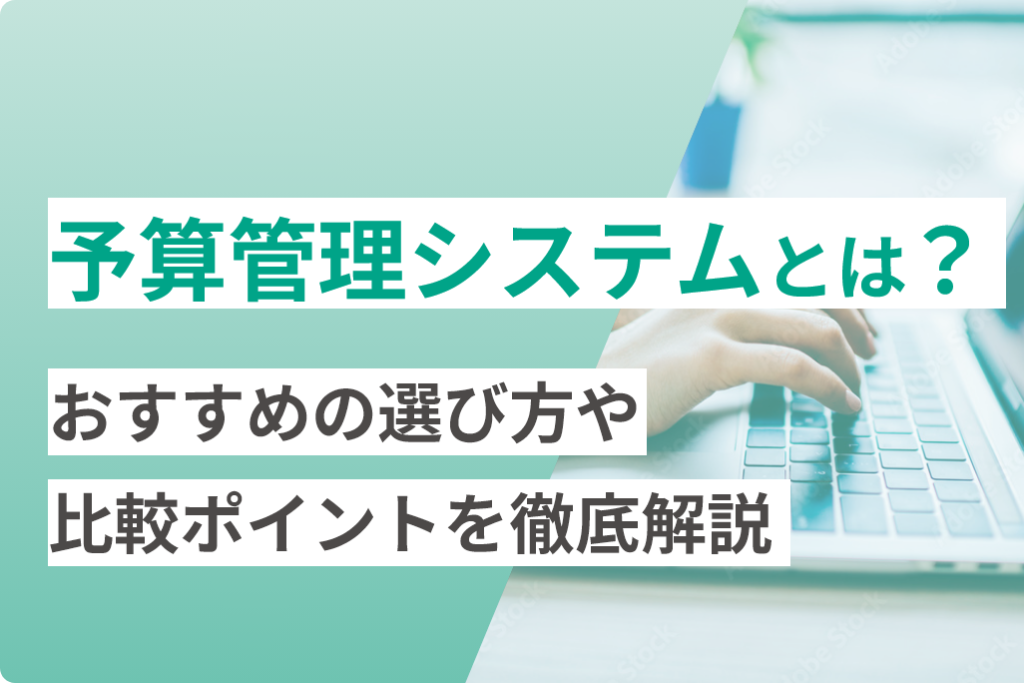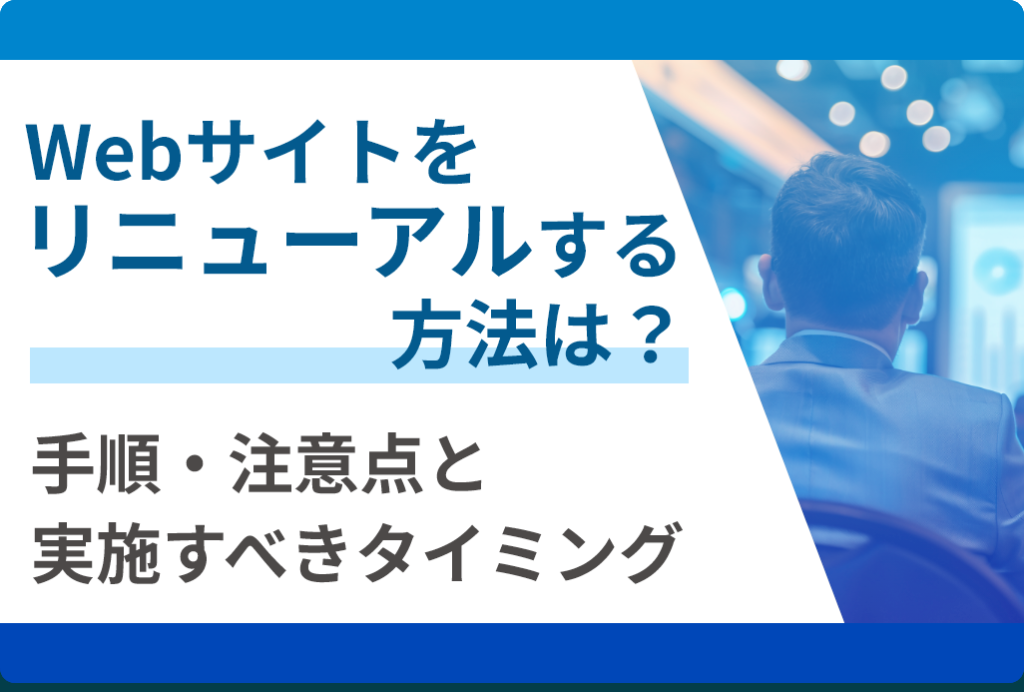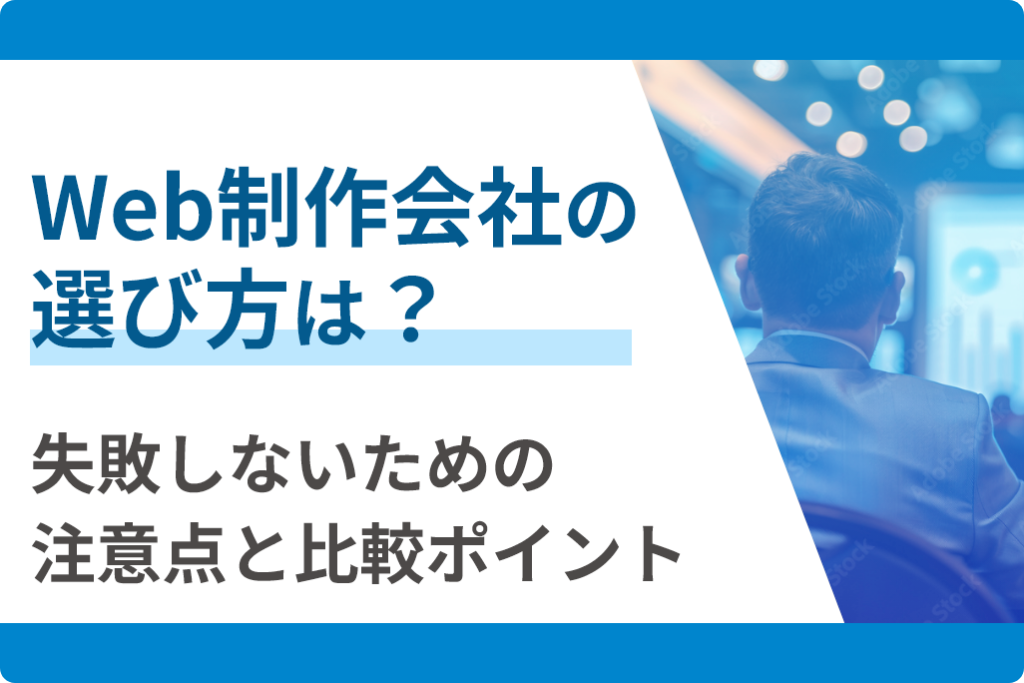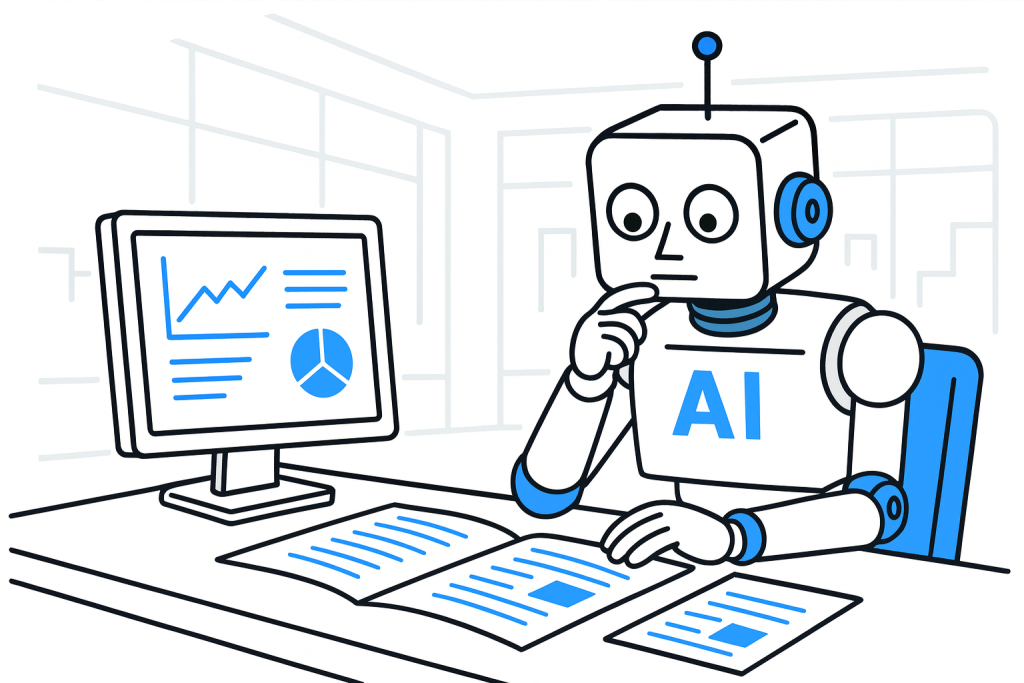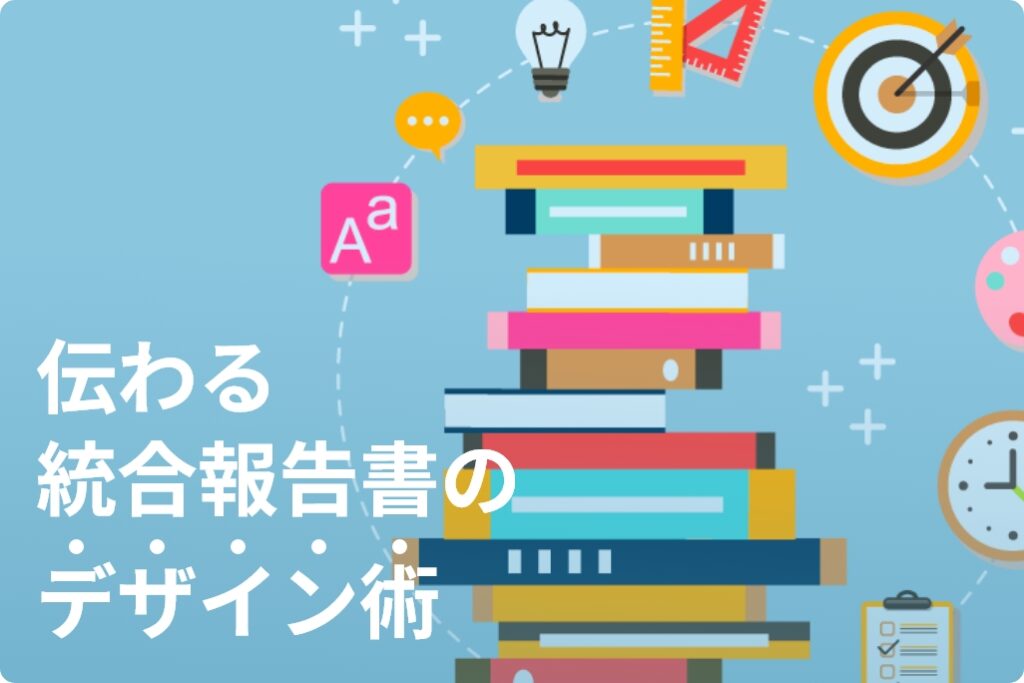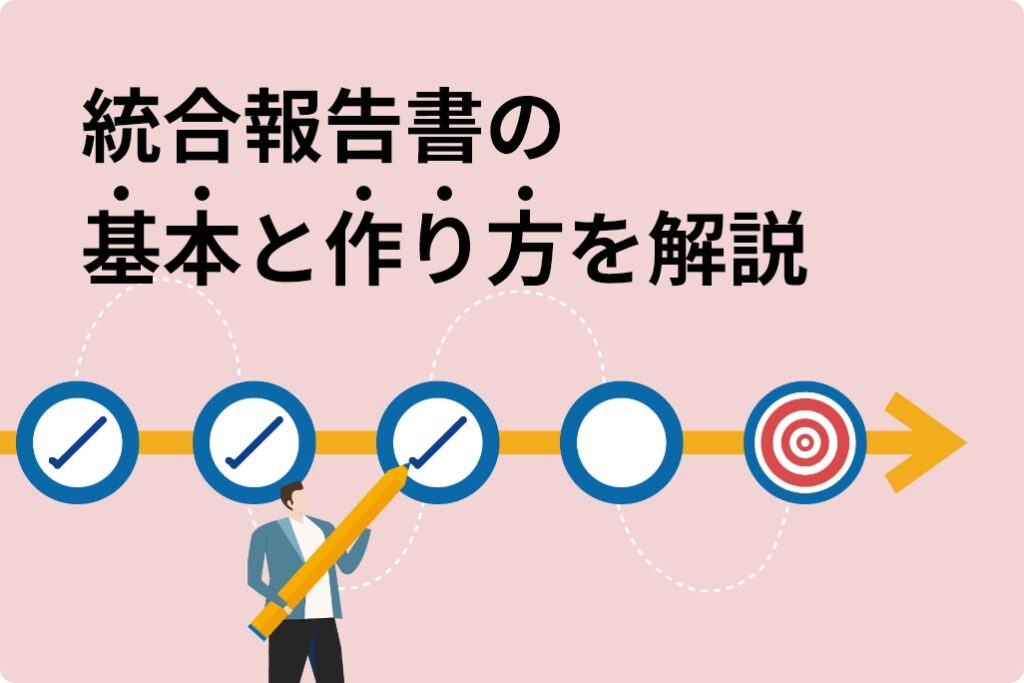企業の持続的な成長と価値創造に対する関心が高まるなか、統合報告書を発行する企業は年々増加しています。統合報告書の主な目的は、財務情報と非財務情報を統合的に開示し、自社の長期的な価値創造ストーリーや戦略をステークホルダーに伝え、深い理解と信頼を得ることでしょう。
ただ、統合報告書を作成・公開することで、具体的にどのようなメリットを企業にもたらすかイメージできないという方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、統合報告書を作成するメリットを解説したいと思います。
統合報告書とは
まずは統合報告書の概要について、次のポイントから改めて確認しておきましょう。
- 企業の財務情報・非財務情報を統合させた媒体
- 統合報告書を作成・公開する企業は増加傾向にある
企業の財務情報・非財務情報を統合させた媒体
“統合報告書”とは、企業の財務情報と非財務情報を統合させた媒体です。
財務情報は売上高や利益、資産状況などの定量的な経営成績が中心であり、非財務情報はESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みや知的資本、人的資本といった企業の持続的な成長を支えるための情報となっています。これらの情報を開示することで、短期的な業績だけではなく、持続的な成長戦略や中長期的な価値の創造についてステークホルダーにアピールできます。
統合報告書は、単純に財務情報と非財務情報を併記した媒体ではありません。財務情報とともに非財務情報を統合思考に基づいて企業価値に関連付けることで、企業の過去・現在・未来にわたる成長ストーリーとして、読者に対して説明する点に本質があります。
統合報告書を作成・公開する企業は増加傾向にある
2025年時点では、日本において統合報告書の作成・開示は義務化されていません。一方で、後述するさまざまなメリットから、統合報告書を発行する企業数は増えています。統合報告書発行状況調査2024”によると、2024年1月~12月末時点の統合報告書発行企業数は1,150社です。2019年時点の536社から5年間で倍増しており、前年同時期と比べても131社増加していることからも、統合報告書への注目度の高まりが分かります。
統合報告書の作成で企業が得ることができるメリット

統合報告書を作成することで、企業は次のようなメリットを得ることができると考えられています。
- 投資家とのコミュニケーションの質が高まる
- ステークホルダーとの信頼関係を強化できる
- 将来的な成長に対する期待感を醸成できる
- 自社ビジネスの持続可能性の促進につながる
- 組織内部の連携体制や意思疎通が強化される
- 自社の“価値創造プロセス”を広く共有できる
- 社内の“統合思考”の理解と実践につながる
- 企業やブランドのイメージ向上が期待できる
- 優秀な人材の獲得や定着で競争力が向上する
投資家とのコミュニケーションの質が高まる
統合報告書を作成することで、投資家や株主などの財務資本提供者に対して、自社の“価値創造プロセス”を分かりやすく伝えることができます。自社が将来的にどのようなキャッシュや価値を生み出せるか、それを実現するための戦略や取り組みを示すことで、財務資本提供者と建設的なコミュニケーションができるようになります。また、トップメッセージなど統合報告書でしか読めないコンテンツを取り入れることで、経営陣の熱意やコミットメントをステークホルダーにアピールすることにもつながるでしょう。
ステークホルダーとの信頼関係を強化できる
統合報告書では、財務情報に加えて、ESG課題への取り組みやリスク管理体制といった非財務情報を統合的かつ高い透明性により開示することで、ステークホルダーからの信頼を高めることができます。こういった取り組みにより、企業とステークホルダーの信頼関係を築くことができ、長期的なビジネスの発展に役立つことでしょう。また、統合報告書による情報開示によって、投資家と企業の間の情報のギャップを是正することで、自社に対する資本市場の評価が変わることも期待できます。
将来的な成長に対する期待感を醸成できる
有価証券報告書においてもサステナビリティ情報の開示が一部義務化されたように、企業の持続可能性(サステナビリティ)に対する市場の関心は高まり、投資判断においてサステナビリティへの取り組みが考慮されるようになってきています。統合報告書でサステナビリティ情報を成長戦略と紐づけて示すことで、自社の将来的な成長に対する投資家・資本市場の期待感を醸成できるでしょう。
自社ビジネスの持続可能性の促進につながる
統合報告書を作成する過程で、サステナビリティに対する自社の姿勢を考え直す機会が生じることにもつながります。この過程自体が社内の意識改革につながり、結果として持続可能性を高める取り組みが促進される効果も期待できます。
組織内部の連携体制や意思疎通が強化される
統合報告書に記載される情報は膨大な量にのぼります。その情報の洗い出しや整理を、ひとつの部署や担当者で対応することは困難な場合があるため、全社的な連携体制の構築が欠かせません。また制作の過程で、連携体制や意思疎通などが円滑になり、組織運営にも好ましい影響を与えることにつながるでしょう。
自社の“価値創造プロセス”を広く共有できる
統合報告書を作成する前提になるのが、自社がどんな姿を目指し、どのように取り組んで将来的に価値を生み出すかといった、価値創造プロセスを考える過程です。その過程が、自社のビジネスモデルや戦略、成長機会やリスクなどを改めて分析し、将来志向で見つめ直すきっかけになるとともに、ステークホルダーに伝えたり、社内で認識を共有したりするための絶好の機会になってくれます。
※関連記事
社内の“統合思考”の理解と実践につながる
統合報告書は、財務情報と非財務情報がIntegrated(統合)されていることが理想的です。そのためには、財務情報に焦点を当てた短期的思考から、中長期的な価値を創造するための意思決定と行動につながる“統合思考”が重要です。
IFRS財団の統合報告書発行状況調査2024では、統合思考を「組織の戦略、ガバナンス、実績及び見通しが、外部環境との関連において、どのように価値創造、維持又は毀損につながるのかについて、組織内の各部門が連携して能動的に考えること」と定義しています。
これを実践するためには、自社の価値や目指すべき方向性を理解する必要があり、この統合思考を組織全体に浸透させ、実践していくためには、部門横断的な協力体制の構築が不可欠です。
企業やブランドのイメージ向上が期待できる
統合報告書の読者は財務資本提供者だけではありません。自社の経営理念・価値観、環境や社会に対する取り組みなどが記載されるため、統合報告書は顧客の共感や信頼の獲得につながり、競合他社との差別化にもつながります。さらに、有価証券報告書などの法定開示書類では伝えきれない非財務情報や定性情報を示すことで、企業の社風や企業文化を感じてもらう効果も期待できます。
優秀な人材の獲得や定着で競争力が向上する
Z世代などの若年層は、持続可能性や企業の社会的責任への関心が強いと考えられます。そのため、統合報告書の記載内容が就職先・転職先の企業選びの要素として活用されることも想定されます。自社の情報を適切に伝わりやすく開示することで、優秀な人材の獲得・定着による競争力の向上も期待できます。
統合報告書を作成するデメリット・注意点

統合報告書を作成するデメリット・注意点として、次のようなものが挙げられます。
- 人的リソースやコストの負担が増大する
- 統一されたフォーマットがない
人的リソースやコストの負担が増大する
統合報告書を作成するためには相応の時間と工数がかかるため、人的リソースに余裕がない企業にとっては大きな負担が生じる場合があります。さらに、コンテンツづくりのため、社内の幅広い部門との連携・調整が必要なため、担当者の選任や体制構築なども重要になります。また、統合報告書を作成すると、その後も毎年公表し続けることが期待されるケースもあるため、安定した制作体制の構築も欠かせません。また統合報告書の作成を外注する場合に相応のコスト負担が生じるなど、リソースやコストについて事前にしっかりと検討をしておきましょう。
統一されたフォーマットがない
現状では、統合報告書の統一された基準やフォーマットは完全には確立されていません。そのため、統合報告書にどのような情報を含めるべきか分からず、方向性が定まらないケースもあります。ただし、IFRS財団の統合報告フレームワークや経済産業省の価値協創ガイダンス2.0は、統合報告書を作成する際の指針として活用できます。統合報告書のガイドラインや作成時の意識すべきポイントについては、次の記事で解説しているのでぜひご参照ください。
※関連記事
ステークホルダーが統合報告書から得ることができるメリット
統合報告書について、ステークホルダーにとってのメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 企業の長期的な価値を理解できる
- 適切な投資判断ができるようになる
- 購買や就職・転職の判断材料にできる
企業の長期的な価値を理解できる
VUCA時代といわれるように、近年の社会情勢や環境などビジネスを取り巻く状況が目まぐるしく変化する現況では、短期的な財務諸表だけで企業の価値を理解することはできません。
そこで注目されているのが、企業の持続可能性を示す“サステナビリティ情報”です。有価証券報告書でも一部開示が義務付けられましたが、統合報告書では、より長期的かつ多角的な視点から、企業の価値創造ストーリーや戦略、ESGへの取り組みなどが具体的に記述されるため、企業の将来性やリスク対応力などを深く理解するのに役立ちます。
そのため統合報告書を読むことで、財務資本提供者はもちろん、その他のステークホルダーにとっても、企業が将来的にどのようにキャッシュを生み出すか、優秀な人材を雇用・育成していけるかといった企業価値の把握に役立ちます。
適切な投資判断ができるようになる
投資家が投資を判断する際は、業績や戦略などの財務情報も重要ではありますが、サステナビリティやESGに注目が集まる昨今では、非財務情報は大きなファクターです。統合報告書は、投資判断に必要な財務情報と非財務情報を統合させたレポートなので、それを読むことで投資家が企業の未来に向けた成長性を判断でき、投資判断に役立ちます。
購買や就職・転職の判断材料にできる
企業の社会的責任やサステナブルな取り組みなどに関心がある消費者が、ブランドや製品を選ぶときに統合報告書が活用されるケースも考えられます。また、統合報告書が人材育成や労働環境などについて言及している場合、求職者が企業文化やキャリアパスを理解し、就職・転職先を選択するうえでの重要な判断材料となることでしょう。
統合報告書のメリットを活かすためのポイント

統合報告書を作成する際は、前述したメリットを最大限に活かすために、次のようなポイントを意識しましょう。
- 価値創造プロセスを明示する
- 経営陣の想いを盛り込む
- さまざまな視点を考慮する
- アウトカムを提示する
価値創造プロセスを明示する
“価値創造プロセス”は、統合報告書に記載すべきとされている要素を一枚絵に落とし込んだものであり、企業が中長期的な価値を生み出す過程を示すもので、統合報告書のサマリーといっても過言ではありません。価値創造プロセスを自社の価値をステークホルダーにアピールするためには、図表などを用いて分かりやすく明示することが大切です。ただし、それが非現実的なものにならないように、自社の実績や取り組み内容を踏まえた現実的な内容になるようにしましょう。
※関連記事
経営陣の想いを盛り込む
統合報告書には、社長(CEO)や経営陣のメッセージが記載されるケースが多くあります。これらのメッセージにはビジョンと価値観の明確化やステークホルダーへのコミットメント、組織文化と行動変革の促進といった内容が含まれており、ステークホルダーに大きなインパクトを与えます。トップの熱意を表現できれば、統合報告書の記載内容に対する信頼性や、企業価値への印象はさらに深まるでしょう。
さまざまな視点を考慮する
統合報告書は基本的に財務資本提供者を対象として作成・開示するものですが、IFRS財団の統合報告フレームワークでは、その他のステークホルダーにも有益であることが示唆されており、幅広いステークホルダーにとっても効果的と言えます。例えば、従業員の行動変容を起こしたい場合は、人材育成や労働環境など従業員に訴求できるコンテンツに重点を置くということも可能です。自社が統合報告書を発行する目的や対象読者を丁寧に検討し、対象によってコンテンツのメリハリを付けることが重要になります。ただし、統合報告書のメインはあくまで財務資本提供者である点も忘れないようにしましょう。
アウトカムを提示する
企業の活動(アウトプット)が、最終的にどのような影響(アウトカム)をもたらしたのかを具体的に記載することが重要です。IFRS財団の統合報告フレームワークでは、資本はインプットとして活用され、事業活動を通じて製品・サービス・副産物などのアウトプットに変換されます。さらにその結果として、資本の内部的および外部的アウトカムが生じるのです。アウトカムを報告する際には、ポジティブな影響だけでなく、ネガティブな影響(例えば、環境負荷や社会課題への負のインパクト)についてもしっかり開示し、今後の対応策を示すことが、ステークホルダーからの信頼を得るうえで重要です。
統合報告書に関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書を公開することで、企業にとっては、投資家とのコミュニケーションの強化や、資本市場と企業の情報の非対称性の解消につながるなどのメリットを得ることができます。こうしたメリットを最大限に活かすためには、一貫性のある価値創造プロセスやトップメッセージを盛り込むことが大事です。また自社リソースでの対応が難しいと感じる場合は、統合報告書の制作支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。
宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。
統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。