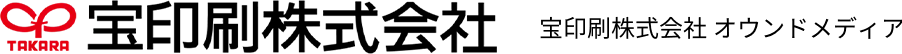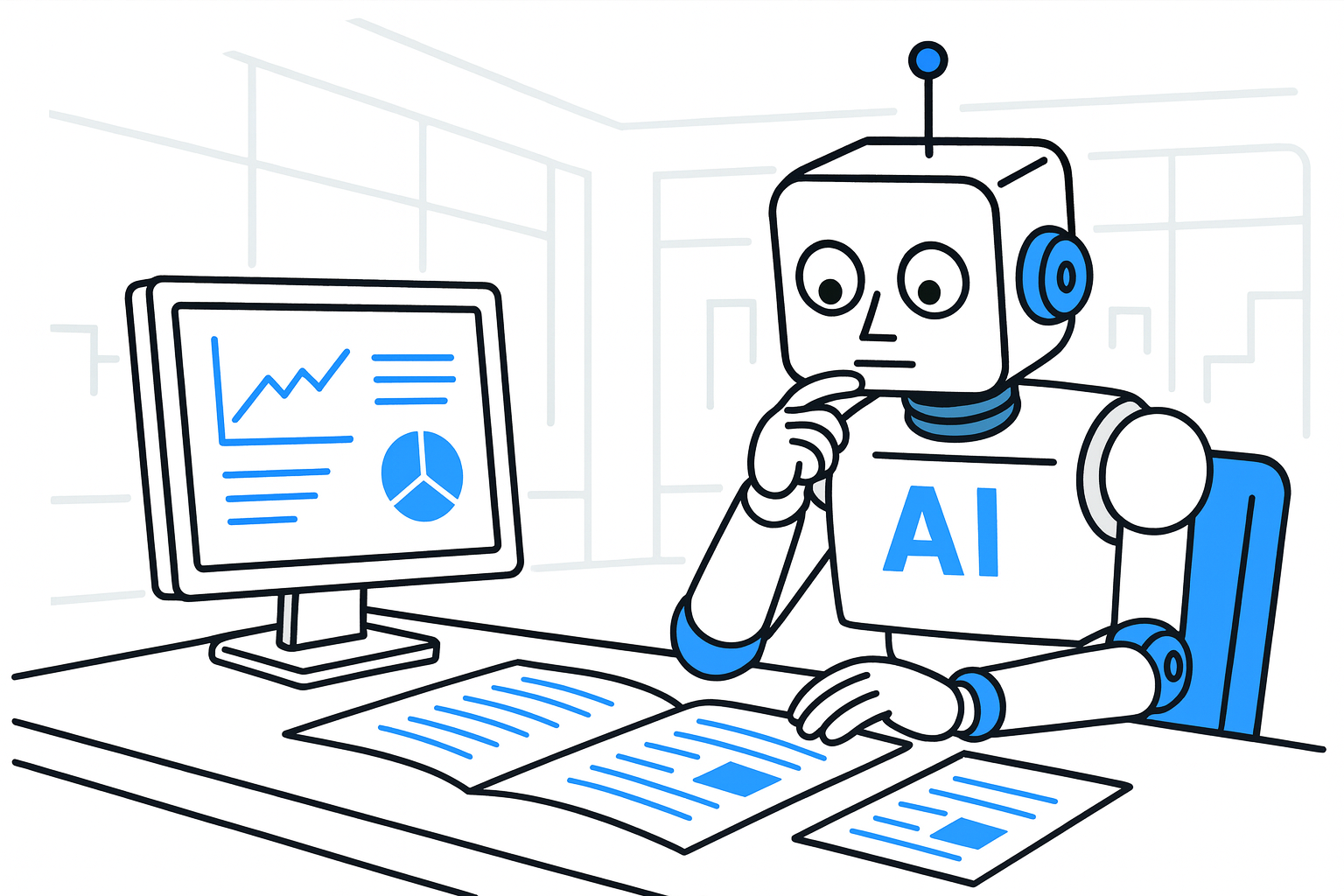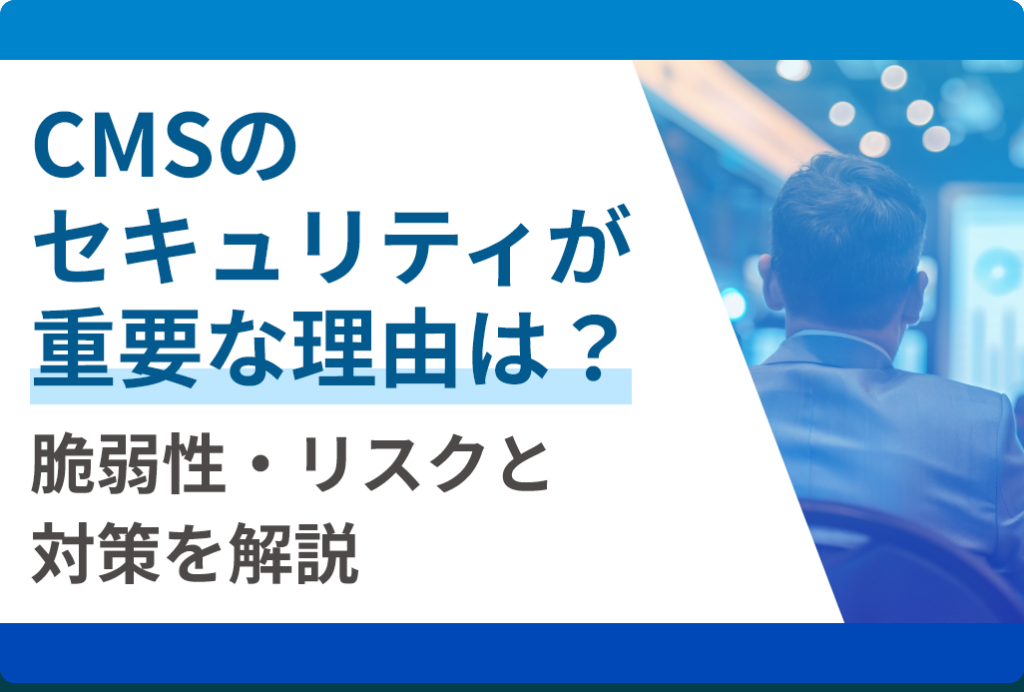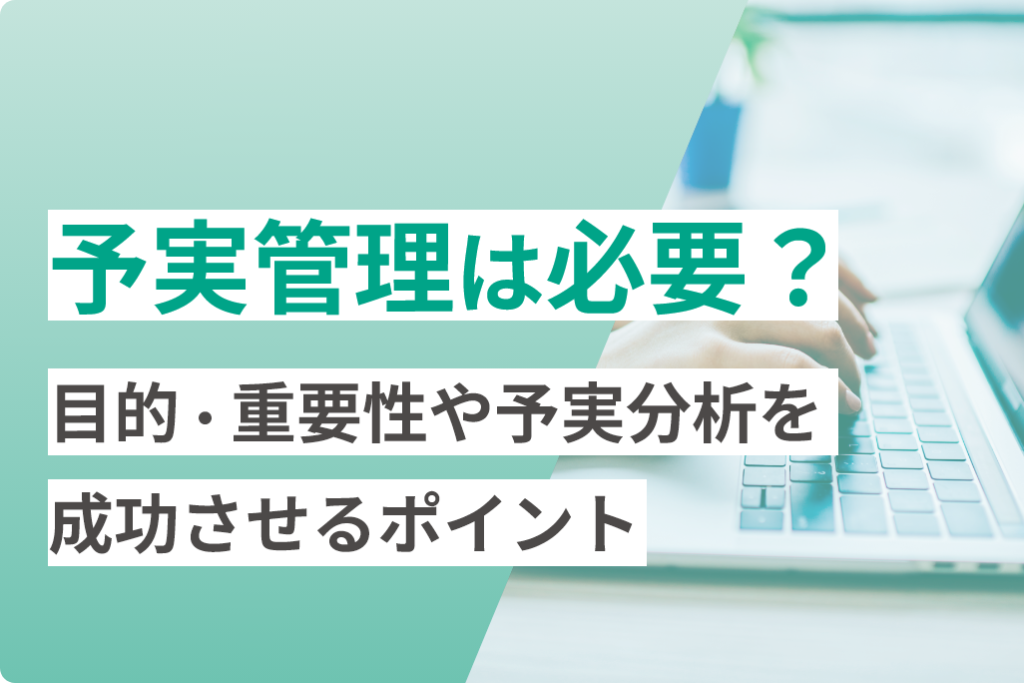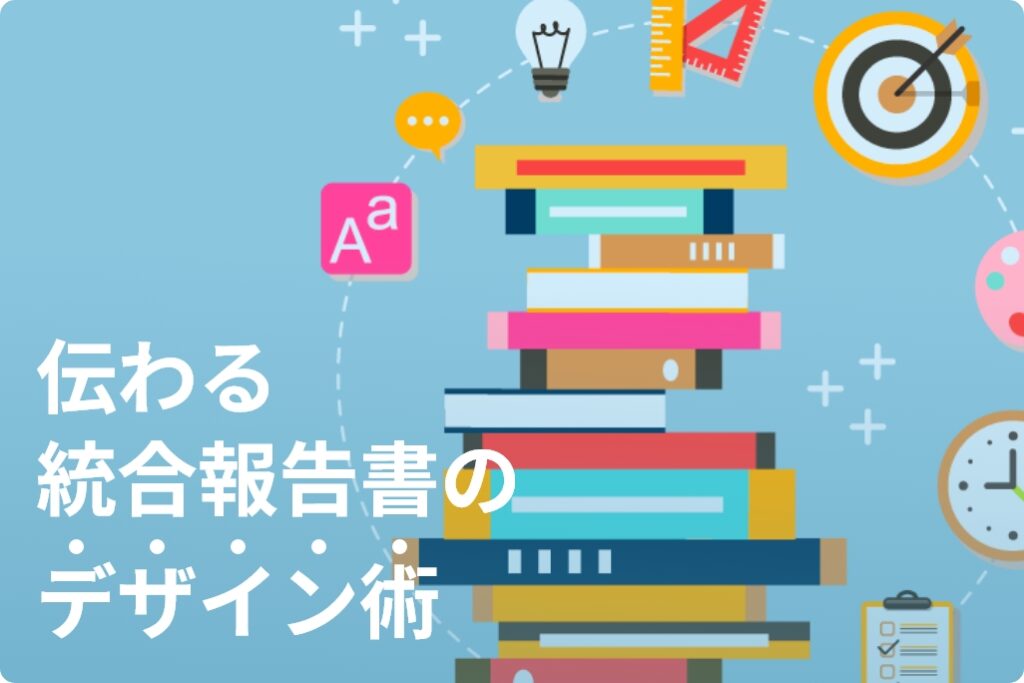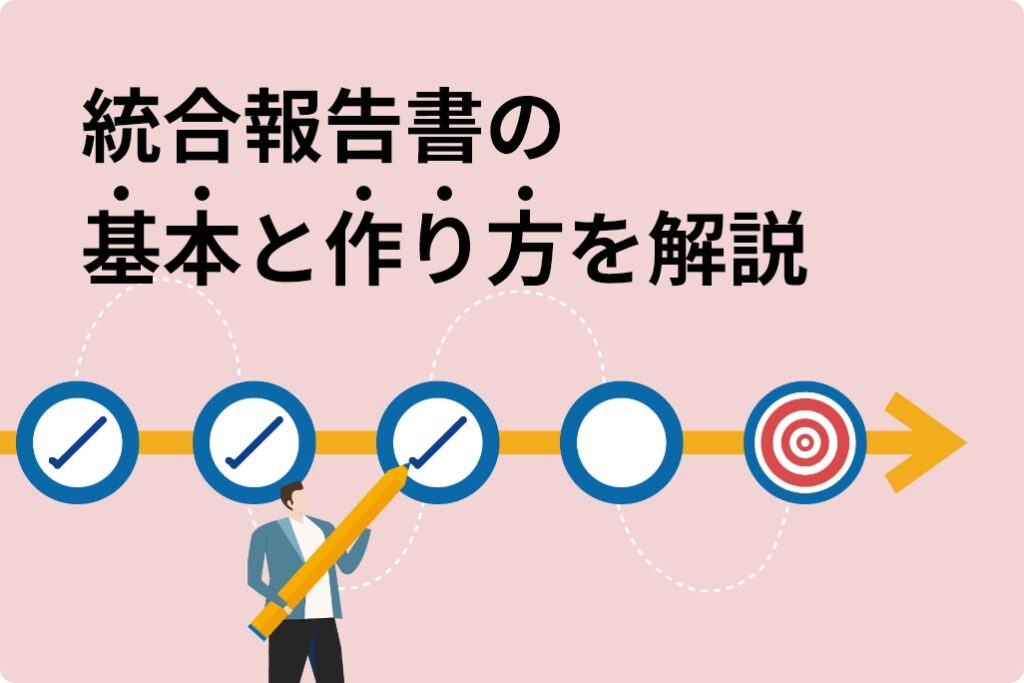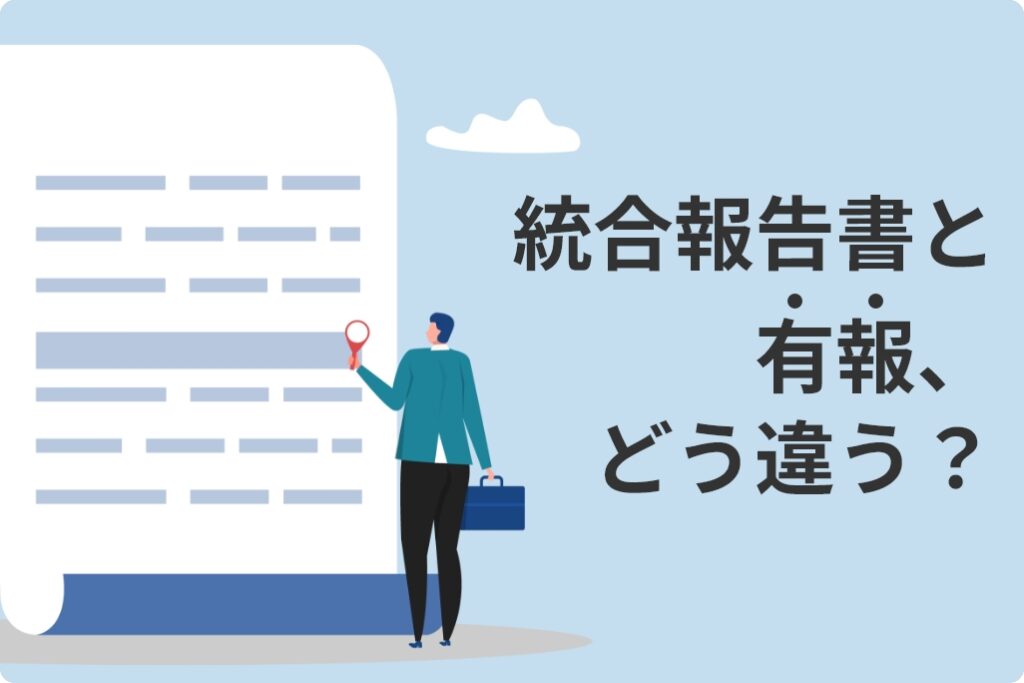ChatGPTの登場で変わる“読み手”
2022年のChatGPTの登場は、統合報告書の“読み手”を根本から変えました。これまで人間を想定していた統合報告書は、いまやAIにも読まれる時代を迎えようとしています。AIが企業の開示情報を自動解析・要約・比較する技術はすでに実用段階にあり、近い将来、投資家やESG評価機関がAIを使って報告書を読むのは当たり前になるでしょう。
統合報告書は“人が読む”ものから“AIにも読まれる”ものへ。その変化は、企業の情報開示のあり方を見直す大きな契機となります。
“AIに読まれる統合報告書”とは
AIに読まれるとは、AIが内容を正確に理解・要約できる構造を備えていることを意味します。
AIはデザインやレイアウトではなく、PDF内部のテキスト構造・メタデータ・アクセス設定に基づいて解析します。具体的には次の3点が重要です。
- 構造化されている
章立て・段落・表がタグで整理され、文脈を把握できる状態になっている。 - メタデータが整っている
タイトル・作成者・キーワードなどの基本情報が正確に付与されている。 - アクセス可能である
コピーや抽出を制限せず、AIが自由に解析できる設定になっている。
これらが揃って初めて、AIは統合報告書を理解できます。つまり、AIに読んでもらえる統合報告書とは、AIが理解できる“データとしての報告書”なのです。
宝印刷D&IR研究所の調査が示す現状
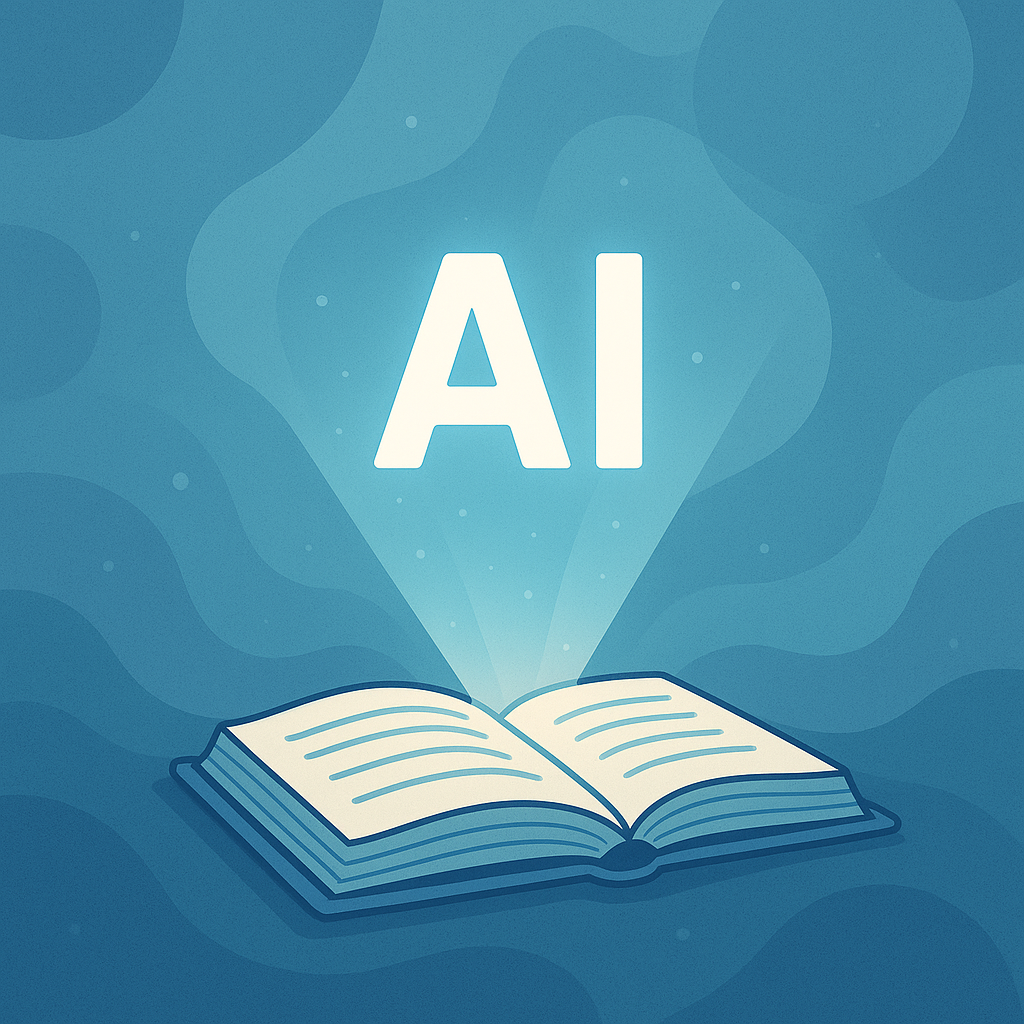
宝印刷D&IR研究所は、2024年に日経225構成銘柄210社(うち208社がPDF発行)を対象に、AIによる機械可読性(Machine Readability)を調査しました。その結果、AIが正確に理解できる統合報告書はごく少数であることが判明しました。
|
検証項目 |
対応企業の比率 |
内容 |
| 内容のコピーが可能 |
84% |
AIがテキスト抽出できる |
| メタデータの登録 |
40% |
文書を識別しやすい状態 |
| タグ付きPDF |
8% |
構造化により文脈を理解 |
| 優先言語の設定 |
80% |
言語誤認を防止 |
| フォント埋め込み |
99% |
文字化け防止 |
84%の企業が内容のコピーが可能な対応をしていたものの、構造化(タグ付きPDF)まで整備していたのはわずか8%。
つまり、AIが内容を理解できる状態の企業は1割にも満たないという結果でした。
AIが“読む”ことで変わる企業価値評価
AIが報告書を読むようになれば、企業の伝わり方が変わります。AIは単なる情報処理ツールではなく、企業のストーリーを要約・比較・評価するフィルターとして機能します。
たとえば投資家が「統合報告書からサステナビリティ方針を要約して」と指示して、AIが内容を瞬時に解析するようになれば、構造の整った報告書はより正確に理解され、信頼性も高く評価されます。
つまり、AIにどう読まれるかが、今後の企業評価の入口になっていく可能性があります。
AIに読まれる統合報告書をつくる3つの視点
- AIが理解できる構造を整える
メタデータ・タグ付け・章構成を整理し、“紙の延長”ではなくデータとして設計しましょう。 - ファイルサイズと品質の最適化
画像過多による重いPDFはAIの解析を妨げます。20MB以下を目安に軽量化をはかりましょう。 - 文体
AIは、文脈が明確で論理的に構成された文章をより正確に理解するといわれています。統合報告書では、ビジュアルやレイアウトの工夫によって価値創造プロセスを一貫したストーリーとして描くことが大切ですが、同時に伝わりやすい文体を意識することも重要です。
“AIに読まれる企業”が次の競争力を握る
タグ付けやメタ情報を整備している企業は、すでにAI時代の開示戦略を先取りしています。
宝印刷D&IR研究所によれば、こうした企業はそれほど多くありませんが、今後の“AIによる企業比較”において有利な立場を築く可能性があります。
統合報告書はもはや人間だけのための資料ではありません。AIが企業のストーリーを読み取り、要約し、伝える時代が始まっています。
“読まれる準備”を整えることこそが、次の企業価値を生み出す第一歩です。
出典 株式会社宝印刷D&IR研究所 『ESG/統合報告トピック調査:統合報告書と機械可読性』(2025年8月)